「大地の侍」を観て感動を受けた私は、さっそくゆかりの地である当別の街を訪れてみた。原作者である作家・本庄睦夫の「生誕の地碑」、そして領主伊達邦直が建てた「伊達邸別館」、「当別伊達記念館」と訪ねてきた。
本庄睦夫生誕の地碑
「大地の侍」の原作となった「石狩川」を著した本庄睦夫は当別町の出身である。その生誕の地は当別町の中心からは遠く離れたビトエという農村地区にあるとあった。ビトエという漠然とした地区名だけではたどり着けない。ところが幸いなことに、そのビトエという農村地帯に菓子会社「ロイズ」がふと美工場を建設していて、工場直売店を経営していた。疎この直売店で訪ねると、なんと工場敷地の一角に立っていると教えられた。
なるほど工場敷地の南東角に石碑は建っていた。直売店の方は「正確な生誕の地ではないが…」と言いながら教えてくれたが、広大な地で生まれ育ったことには違いなかった。なお、本庄は伊達家の岩出山藩の出ではなく、佐賀藩士の末裔であるということだ。

※ 当別町の広大な畑の真ん中に建つロイズふと美工場の外観です。

※ 工場直売店の店内には本庄睦夫に関してのいわれなどの説明板がありました。

※ 工場敷地の一角に建つ「本庄睦夫生誕の地碑」です。
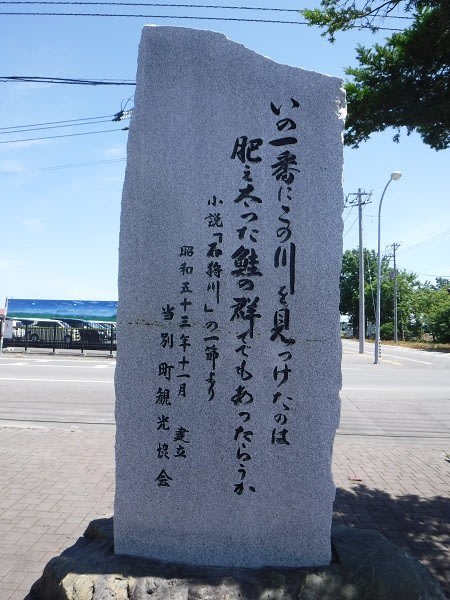
※ 石碑の裏側です。
当別町伊達記念館
「当別町伊達記念館」と「伊達邸別館」は隣り合っていたが、こちらは番地まで明示されていた(当別町元町105番地)のでナビに導かれ容易に見つけることができた。ところが!「伊達邸別館」の入口には頑丈なカギがかけられていた。一方「当別町伊達記念館」の方の入口には「当別町民以外は入場をお断りします」という掲示がかけられていた。ガーン!このように表示されていては仕方がない。一緒に行った妻と「帰ろうか」と話をしていたところ、記念館から学芸員のような方が姿を見せ、「どうぞ、どなたもいらっしゃらないので館内を見ていってください」と案内していただいた。思わぬ僥倖に私たちは喜んで館内を見学させていただいた。

※ 記念館の建物としてはやや寂しい外観の「当別町伊達記念館」です。
館内の展示は主として伊達邦直公、並びに奥方の遺物の展示だった。当時の困難な交通事情の中で、人力によって運ばれたと思われる数々は国主としての矜持を保つためにも欠かせぬものだったと思われた。

※ 伊達公の奥方様の化粧道具一式です。明治初期でも高貴な方はしっかり化粧していたとみえます。

※ 展示品の一つ、陣羽織や裃などです。

※ こちらは戦に備えての軍備品でしようか?
館内の一角には岩出山藩の開拓の様子がたくさんの版画によって描かれていたが、それは映画の内容と重なるところが多かった。

※ 東北からの移動の大変さ、開拓の困難さを伝える版画です。
伊達邸別館
学芸員の方は私たちを「伊達邸別館」へも案内してくれた。この「伊達邸別邸」は名士が来村した際の宿泊、懇談や村政執行のため諸会議に使用するため1880(明治13)年に建設されたそうだが、岩出山藩が当別に開拓の鍬を入れたのが1871(明治4)年であるから、開拓も一段落して安定期に入ったころに建設されたことがうかがわれる。別館は意外に小規模で、二階建てであるが一・二階にそれぞれ二部屋しかない小規模な建物であったが、造りはしっかりしたものであった。

※ 「伊達邸別館」の前には、その由来を伝える説明書きがありました。

※ 意外に小ぶりな「伊達邸別館」の外観です。

※ 応接室兼会議室です。

※ こちらは書斎兼控室だったようです。

※ 二階の日本間で客人の寝室ですが、写真では伊達公と奥方、それに開拓の状況を報告する家臣が人形で表現されています。
当別神社 & 開拓記念樹
別邸の直ぐ近くには、領主邦直が御祭神として祀られている「当別神社」がある。そこへもまた件の学芸員氏が案内してくれた。学芸員氏は、神社横に立つ「開拓記念樹」について説明してくれた。ここに立つイチイの木は、当初入植した聚富(しっぷ)が開拓に適さない地だったことから当別の地を調査した踏査隊が露営したという樹齢350年という大木で、開拓当時に村人が心の拠り所とした木だったことから「開拓記念樹」とされたようだ。しかし、数年前に上部が朽ち果て倒れてしまったという。今も根元だけは残っていたが、根元だけでも十分にその大木ぶりを見て取れた。


※ 残念ながら上部が欠けてしまった「開拓記念樹」です。
そしてその奥に建つ「当別神社」は広大な敷地の中にあり、岩出山藩士たちの末裔が支える神々しさに満ちた神社だった。

※ 第一鳥居から見た「当別神社」の本殿です。




















