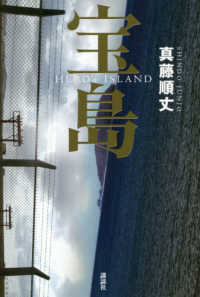八七〇
一此度吹直被仰付候小判・壹歩判之儀、來ル廿日より追々
引替可遣候、尤有來小判壹歩判之儀も、追て及沙汰候迄
は新金取交受取方・渡方・両替共無滞可致通用、上納金
も可為同前事
一引替金之儀は、小判・壹歩判之無差別、たとへハ皆小
判・皆壹歩判ニて差出候とも、引替方之儀は小判七歩・
壹歩判三歩之割合を以取交引替候筈候條、來ル廿日より
後藤三右エ門方役所を始、別紙名前之者共方え差出引替
可申候
一武家其外町人え相對ニて申付、右名前之者共方へ差出引
替させ候儀も勝手次第ニ候事
一引替ニ可差出小判・壹歩判共員數相知レ候事候間、貯置
不申、段々引替可申候、若隠置不引替もの相知レ候ハヽ、
吟味之上急度可申付事
右之趣可被相觸候
文政ニ卯九月
八七一
一嘉千代様御事、先月朔日御弘被仰出候、依之嘉之文字は
勿論文字違候共、同唱之假名又は名乗ニ付居候者は改可
申旨被仰付候、此段觸支配方へも可被達候、以上
十一月十四日 奉行所
八七二
一少将様を先月十日より濱町様と可奉稱旨被仰出候、此段
被奉承知申達候様、觸支配方へも可被相達候、以上
文政ニ卯十一月廿日 奉行所
八七三
一旦那寺替いたし候節之儀ニ付、安永七年・文化十三年諸
寺院え別紙之通及達置候、右は畢竟町在無辨之者之心得
ニ及達候儀ニて、御家中之面々ニは不及達儀ニ候得と
も、近年ニ至旦那寺替等いたし候面々、間ニは寺院え之
懸合不行届内輪申分も有之哉ニ相聞候、依之先年申達候
趣一統為存知せ置可申旨ニ付、寫之相添候條左様被相心
得、御支配方えも可被相達候、以上
十一月廿八日 御奉行中
新ニ旦那寺替いたし候ハヽ、此節旦那寺ニ相願候寺院
より元旦那寺被及取遣、支無之との書付受取候上、且家
ニ受込可申との儀候、安永七年寺院一統委細及達置候通
候處、間ニは右達之趣等閑ニ相心得、猥ニ改宗又は旦那
寺替等いたし候もの有之、右之通ニて自然御難題ヶ間敷
儀等差起候ては恐入候事ニ付、以來改宗等致度段申出候
者有之候ハヽ、元旦那寺より故障無之との書付いたし、
一派之法頭幷役寺五ヶ寺組より裏書を用ひ連印いたし、
改宗等申出候本人ニ相渡申度、右之通手數ニ相成不申候
ては、後日之證據ニ相成不申段被究置度由、浄土宗一派
之寺々連印を以願出ニ相成、書面之趣無餘儀相聞候間、
願之通取計可有之段及達候、然處右一段は御政體ニも懸
り可申筋故、區ニ有之候ては難相濟事ニ付、諸宗一統右
之通取計ニ相成、向後違亂無之様可被相心得候、以上
文化十三年十一月十一日 寺社御奉行所
在中之者共無據譯有之宗旨替又は寺替いたし候節は、双
方之寺院得斗懸合納得之上受込可申處、其後無之、下方
之者は不束成處より猥ニ相成、間々出入有之様子ニ相聞
候、以來新タニ旦那寺ニ相頼候寺院より、元旦那寺へ及
取遣支無之との書付受取候上且家受込可申候、尤娵入い
たし候者ハ向々之宗旨ニ相成候事世間通例ニ候得は、右
躰之筋ハ双方之寺院へ届ハ不及候、若譯有之實方之旦那
寺ニて居候節ハ、向方之旦那寺へ右之譯届置可申候事
安永六年九月
八七四
一太守様益御機嫌能被遊御座、今度日光御靈屋向幷諸堂社
御修復御用被遊御勤候付、御宮御靈屋え被遊御参拝度、
尤來年例之通御國許え之御暇被仰出候は、其節御参拝直
ニ御歸國被遊度段、御伺書御掛り土居大炊頭様え御使者
を以被遊御差出置候處、先月廿九日御伺之通被仰出候段
申來奉恐悦候、此段觸支配方えも知せ置可申旨ニ付、被
奉承知御支配方えも可被相知候、以上
文政ニ卯十二月廿五日 御奉行中
八七五
一御家中子弟、近來間ニは心得方不宜、漁獵之往来等猥成
振廻も有之、或は大勢寄合不穏唱も相聞、且亦長者年少
之人ニ對し不法之戯等有之、其外追々及達置候趣ニも致
相違、不都合之次第候條、不敬之面々より屹ト加教戒、
親類よりも無油断心を附、若不改形有之族ハ處置之筋も
可有之事ニ候、右付ては追て及達筋茂可有之候得とも、
寛政十二年・文化十三年及達置候寫別紙相添候條、此段
組支配方へも可被達候、以上
十二月廿七日 奉行所












 藤崎八旙宮繪縁起
藤崎八旙宮繪縁起 
 明治初期の北岡神社(祇園社)
明治初期の北岡神社(祇園社)