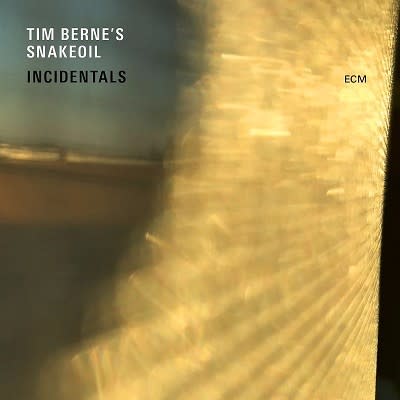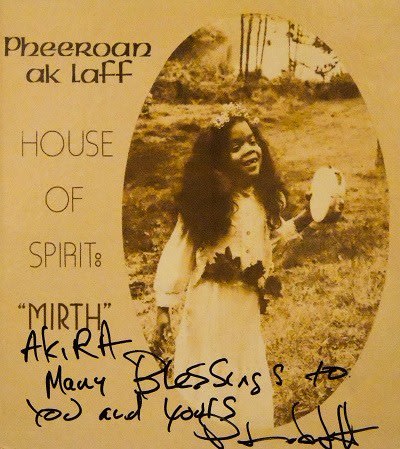マルクス兄弟の中でもっとも人気が高いのはハーポだろう。次にグラウチョ(小林信彦流の表記)、チコ。ゼッポは存在感希薄。
ハーポは年齢に関係なく妖精のようであり、なにしろハープを弾く。映画のなかでうっとりと顔を振りながら弾くハーポ(ソフトフォーカス)はきっと「待ってました」的な場面だっただろう。何かが突然ハープに姿を変え、おもむろにハーポが弾き始める爆笑の名場面はどの映画だったか。
ハーポはおそらく3枚のレコードを出している(『Harp by Harpo』1952年、『Harpo in Hi-Fi』1957年、『Harpo at Work』1958年)。そのうちわたしは後の2枚を持っている。1888年生まれだから、このとき70歳近く。既にコメディアン業からは引退していたわけであり、それほどに人気があったということだろう。
『Harpo in Hi-Fi』では、ハーポは、フレディ・カッツ・オーケストラをバックに弾いている。フレディ・カッツとはチェリストとしてチコ・ハミルトンとの共演歴もあった人らしい。またハーポの息子ビル・マルクスが何曲かでアレンジを手掛けている。「Yesterdays」、「My Funny Valentine」、「Tenderly」、「Autumn Leaves」、「Honeysuckle Rose」などのスタンダードを演奏しているのだが、いまとなっては、ヘンにモダンでダサく(チャーリー・パーカーのストリングス盤がそうであったように)、もっとハープを前面に出して欲しかったと思う。
一方、『Harpo at Work』はもっとシンプルで、素直にメロウなアレンジである。「My Blue Heaven」、「The Man I Love」、「All the Things You Are」、「Solitude」、「In a Sentimental Mood」、「I Got Rhythm」などを、軽やかに跳ねたりしっとりと弾いたりして、ハーポのハープがもっと楽しめる。
この2枚はカップリング版CDにもなっているようで、そうなるとサウンドの印象もまた異なるのかもしれない。