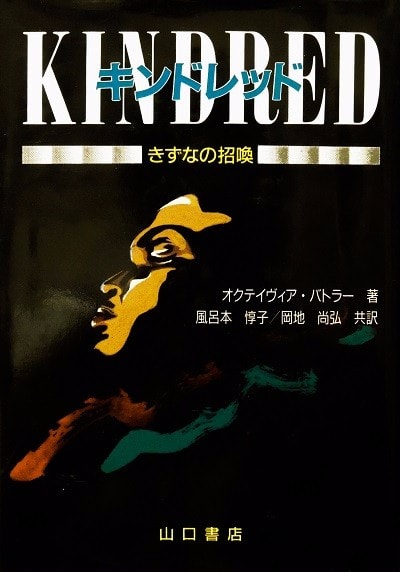すずえり、フィオナ・リー『Ftarri de Solos』(Ftarri、2017年)を聴く。

suzueri すずえり (upright piano, toy piano, self-made instruments, objects)
Fiona Lee (DIY electronics, objects)
これはFtarriが店舗を開いて5年が経ったことを記念して作られたCDの1枚である。先日のライヴで記念品としていただいた。
すずえり、フィオナ・リー、ふたりともライヴ演奏を実際に観たことはまだない。それぞれ自作楽器を使って奇妙で愉快な音楽を創り出している。twitterなどでの報告を読むと明らかに視覚的な面白さがあるはずである。しかしそれを音だけで鑑賞することで、実は観るのとは違うように脳に入ってくるに違いない。
すずえりさんのサウンドを聴いていると、半自動のユニークな残忍さといおうか、容赦なさといおうか、そういったことによってヘンに愉快な気分にさせられる。この色彩はメトロノームによってさらに濃くなり、最後にピアノで救われるという魅力。急停止して振り落とされるのもまた愉快。
フィオナ・リーの音は、電気で動く球面内のボールなのだろうか。ぎゅわわんという金属音そのものの面白さを執拗に提示することの愉しさは、それが人間的な電気を使っていることによってさらに増している。