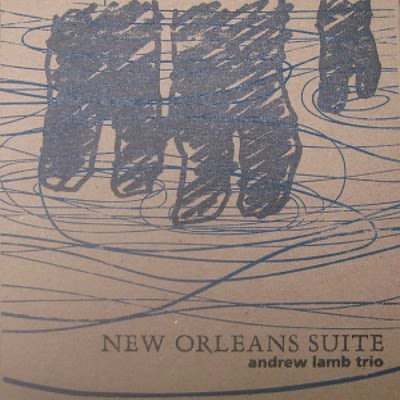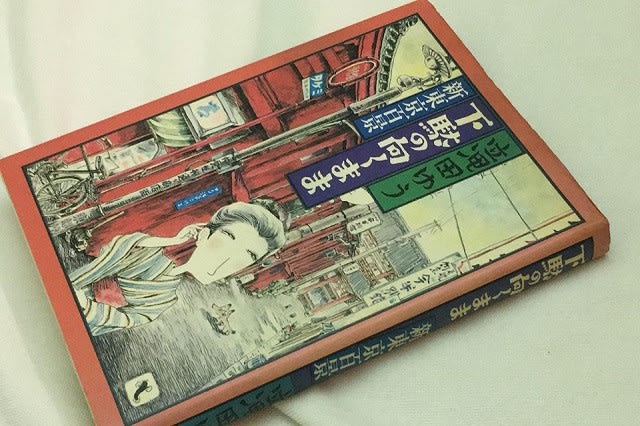金城功『近代沖縄の糖業』(ひるぎ社おきなわ文庫、1988年)を読む。

沖縄における砂糖(伝統的には黒糖が中心)の歴史をまとめた本である。名嘉正八郎『沖縄・奄美の文献から観た黒砂糖の歴史』よりも体系的・分析的に記述されている。
古くは15世紀の三山統一の頃には砂糖が生産されていたらしい。もとは中国の技術である。その後、1609年の島津による侵略を経て、17世紀には、琉球王国は多額の借金を島津に負わされた。その返済のためにはじめられたのが、砂糖の専売である。平たく言えば経済的な支配のはじまりである。
江戸末期からは「前代」という農民への借金制度が導入され、明治期に本格化した。甘蔗(さとうきび、なお甘藷はサツマイモ)の農民には生産や資本のためのオカネが足りない、そのために借りるのはいいとしても、容易に想像できるように、それは生産した砂糖を安く買い叩かれることとセットであり、農民はたいへんな困窮へと追いやられることとなった。また明治期には砂糖消費税も課せられ、それは卸売価格や消費者価格へは上乗せされる結果にはならず(いまの感覚では当然だが)、やはり、農民の生産原価を圧迫した。
一方、1895年から領有した台湾においても甘蔗と砂糖の生産が本格的に進められた。台湾では構造的にうまく砂糖生産地としての形を作ることができたにも関わらず、同じく植民地支配を行った沖縄では、さほどうまくいかなかった。より消費者に求められるようになった砂糖は黒糖ではなく精製する分蜜糖であったが、その転換もできなかった。明治になって大きな期待とともに八重山でも糖業が開始されたが、やはり結果は思わしくなかった。
本書からは、その根本的な原因が、糖業をモノカルチャー化してしまい、また農民を抑圧するだけでは産業として健全に育成することは難しかったところにあったのだということがよくわかる。
沖縄といえば黒糖だ、といういまのローカルフード的な目線を外してみるための良書。
●沖縄の糖業
名嘉正八郎『沖縄・奄美の文献から観た黒砂糖の歴史』
●ひるぎ社おきなわ文庫
郭承敏『秋霜五〇年―台湾・東京・北京・沖縄―』
加治順人『沖縄の神社』
金城功『ケービンの跡を歩く』
保坂廣志『戦争動員とジャーナリズム』
宮里一夫『沖縄「韓国レポート」』
望月雅彦『ボルネオ・サラワク王国の沖縄移民』