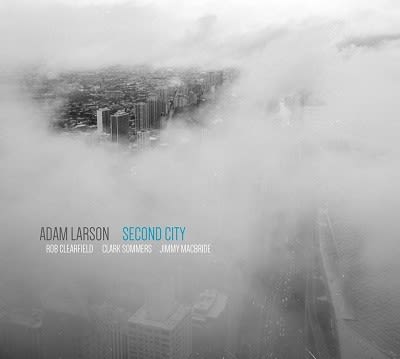昼のなってるハウス(2018/5/6)。

Jun Numata 沼田順 (g, electronics)
Hisaharu Teruuchi 照内央晴 (p)
Ryuichi Yoshida 吉田隆一 (bs)
ぱっと見た時点でえええと笑ってしまったメンバー。これは目撃しないわけにはいかない、と、入院中の病院から抜け出して駆けつけた。何でも仕掛け人は沼田社長(この日、ぎっくり腰)。
ファーストセットから面白い。照内さんはピアノでピアノとして参入するが、そのうちになぜか眼鏡をふっ飛ばしてしまい、足許にも見つからず続行。しかし横のふたりの音に恍惚としているように見える。そしてプリペアドへと移行し、沼田さんとともに割れた音でナマ音感のバリトンサックスを挟むような構造になった。
セカンドセットでは、事前に「意外とメロディアスだったのでめちゃくちゃにしよう」という協議があったらしい。照内さんは最初から内部になにやら放り込みまくり、うちわで扇ぎ、もっと割れた。吉田さんのバリサクにはめちゃくちゃさによってさらに火が点いたようで、ウェットなマシンガンと化し、ひたすら吹き続けた。沼田さんのエレクトロニクスも暴走が面白いのだが、さらに面白いことは、天気予報のアナウンスなどのサンプリングによって収束を目指す先が、なぜか夕陽のあたる昭和の街角になっていることであった。
●沼田順
中村としまる+沼田順『The First Album』(2017年)
RUINS、MELT-BANANA、MN @小岩bushbash(2017年)
内田静男+橋本孝之、中村としまる+沼田順@神保町試聴室(2017年)
●照内央晴
『終わりなき歌 石内矢巳 花詩集III』@阿佐ヶ谷ヴィオロン(2018年)
Cool Meeting vol.1@cooljojo(2018年)
Wavebender、照内央晴+松本ちはや@なってるハウス(2018年)
フローリアン・ヴァルター+照内央晴+方波見智子+加藤綾子+田中奈美@なってるハウス(2017年)
ネッド・マックガウエン即興セッション@神保町試聴室(2017年)
照内央晴・松本ちはや《哀しみさえも星となりて》 CD発売記念コンサートツアー Final(JazzTokyo)(2017年)
照内央晴+松本ちはや、VOBトリオ@なってるハウス(2017年)
照内央晴・松本ちはや『哀しみさえも星となりて』@船橋きららホール(2017年)
照内央晴・松本ちはや『哀しみさえも星となりて』(JazzTokyo)(2016年)
照内央晴「九月に~即興演奏とダンスの夜 茶会記篇」@喫茶茶会記(JazzTokyo)(2016年)
田村夏樹+3人のピアニスト@なってるハウス(2016年)
●吉田隆一
藤井郷子オーケストラ東京@新宿ピットイン(2018年)
MoGoToYoYo@新宿ピットイン(2017年)
秘宝感とblacksheep@新宿ピットイン(2012年)
『blacksheep 2』(2011年)
吉田隆一+石田幹雄『霞』(2009年)