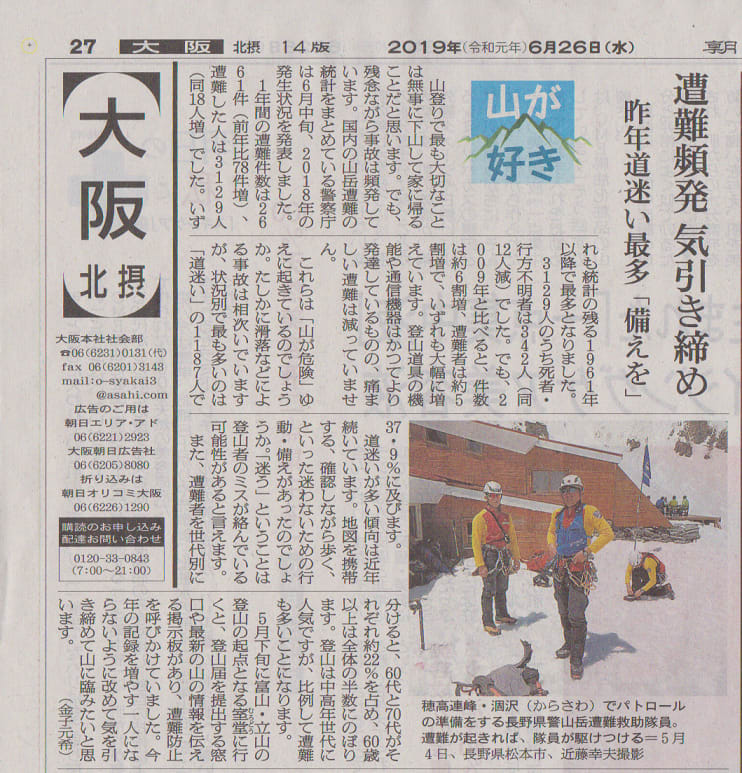「城塞」(下)司馬遼太郎
上中下の最終巻を読んだ。
夏ノ陣が描かれる。
家康の陰湿さとあくどさが、克明に描かれる。
まわりの大名は、保身の為の忖度とよいしょの嵐だ。
上中下の最終巻を読んだ。
夏ノ陣が描かれる。
家康の陰湿さとあくどさが、克明に描かれる。
まわりの大名は、保身の為の忖度とよいしょの嵐だ。
逆に、真田幸村と後藤又兵衛の潔さが引き立つ。
P102
「秀頼を討つ」
とは、さすがの家康も公言しなかった。
(中略)
「諸大名への命令はこうせよ。大坂移封のために軍を発する、と」
P231
家康は関ヶ原の戦勝のあと、この大教団の存在をおそれ、別個に本願寺をつくった。ふつう東本願寺とよばれる存在がそれであり、このためモトの本願寺は西本願寺と通称された。(幕末でも、東本願寺=佐幕派、西本願寺=討幕派だったそうだ)
P263
討死とは敗北であろう。戦国にあっては合戦は勝つために存在し、みすみす負けるときまったいくさは避けた。避けざるをえない場合は降伏した。降伏しない場合は、その悪条件をもってなんとか勝つべく知恵をしばり、不可能と思われる行動までとった。
死をもって美と考えるようになったのは江戸初期、ことに中期前後からのことで、泰平が生んだ特異な哲学であったが、ともかくも戦国にあっては武士はあくまでも勝たねばならず、ひとびとは勝利をのみねがい、たとえ万策が尽きて一時降伏してもそれはあとで勝つための便法であることが多かった。
ところがこの大坂夏ノ陣ぐらいから、死への賛美がはじまるのである。それも勝って死ぬのではなく負けて死ぬことを壮烈とした。
【感想】
起死回生のチャンスは何度もあった。
真田幸村と後藤又兵衛にもっと好きにさせていたら・・・。
淀殿も秀頼も大野修理も戦の素人なんだから、もっと任せるべきだった。
家康はそこのところを巧妙かつ、執拗に突いてきた。
結果、家康は勝利と引き換えに、後世の悪名を背負った。
そこまで頭が回らなかったのだろう。