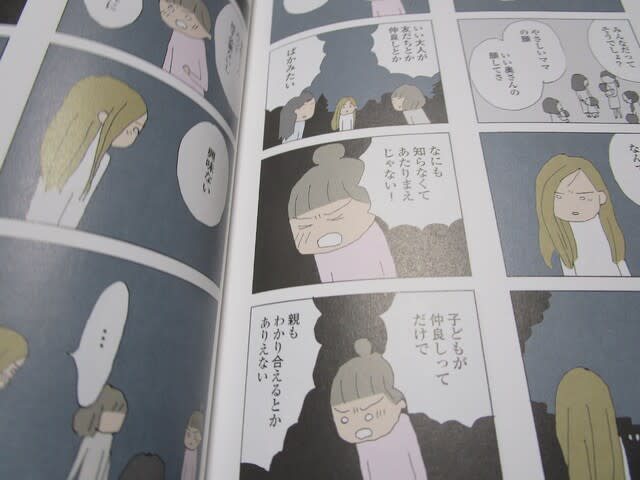「ルワンダ中央銀行総裁日記」服部正也
著者は、1965年から1971年まで、中央銀行総裁として着任。
周りは素人ばかり。孤軍奮闘して経済改革を断行していく。
日本人も捨てたもんじゃないな、と思った。
なお、私は増補版で読んだ。94年ルワンダ動乱をめぐる一文も掲載されていたのでよかった。実際の報道との違い、著者の現場経験からの考察が書かれている。
着任早々・・・
P21
まずい飯を食べていたらチトーがやってきて、「旦那様がお望みなら、きれいな女をつれてきましょうか」とささやく。この野郎と思ってこわい顔をしたら退散した。
P44
通貨は空気みたいなものです。それがなくては人間は生きていられません。空気がよごれておれば人間は衰弱します。しかし空気をきれいにしても、人間の健康が回復するとはかぎりません。空気は人間に必要であっても、栄養ではなく、人間が生きるためにはさらに食物をとり水を飲むことが必要なのです。通貨改革をすることは空気をきれいにすることです。財政を均衡させることは生きていくに足る栄養をとることです。しかし健康を回復するためには、栄養の内容が重要になってきます。経済でいえば財政の均衡の内容とその基礎になっている経済条件が、国民の発展に合うようになっていなければならないのです。
P303
ルワンダと隣国ブルンディの人口はともに、長身のツチ族が人口の10パーセント強、フツ族が90パーセント弱、その他少数のツワ族から構成されている。(なんとなく清朝の漢民族支配を思い出した)
P319
緒方貞子国連難民高等弁務官が、「愛国戦線」首脳と会見後、「彼らは口では良いことを言っているが、自分は、本当にすべてが良いと納得するまでは、難民たちにルワンダに帰れと言うつもりはない」と言ったと伝えられている。(さすが慧眼だ)
P322
冷戦が終わったから軍縮だというのはおめでた過ぎるのではないだろうか。平和、平和と叫ぶよりは、戦争は必ず起こるものとして、その被害を局限するための自衛策をとり、また、小国の争いでは犠牲を限定するため、武器輸出禁止を大国間で合意すべきであろう。国際収支のため武器輸出をすることや、累積債務の支払いのため武器輸出で外貨を稼がざるを得ない状況に追い込むことは、資本主義の道義的破綻といわざるを得ない。
P336
平和といい、貿易といい、援助というものは、究極的には国民と国民との関係という、いわば人の問題である。
P337
途上国の発展を阻む最大の障害は人の問題であるが、その発展の最大の要素もまた人なのである。
【ネット上の紹介】
一九六五年、経済的に繁栄する日本からアフリカ中央の一小国ルワンダの中央銀行総裁として着任した著者を待つものは、財政と国際収支の恒常的赤字であった―。本書は物理的条件の不利に屈せず、様々の驚きや発見の連続のなかで、あくまで民情に即した経済改革を遂行した日本人総裁の記録である。今回、九四年のルワンダ動乱をめぐる一文を増補し、著者の業績をその後のアフリカ経済の推移のなかに位置づける。
1 国際通貨基金からの誘い
2 ヨーロッパと隣国と
3 経済の応急措置
4 経済再建計画の答申
5 通貨改革実施の準備
6 通貨改革の実施とその成果
7 安定から発展へ
8 ルワンダを去る
増補1 ルワンダ動乱は正しく伝えられているか
増補2 「現場の人」の開発援助哲学