■ 今春の長野県の高校入試に田中修氏の『植物はすごい』中公新書から出題された。私は偶然にも入試の直前にこの本を読んでいたが、植物のいろんなビックリが分かりやすく書かれていてなかなかおもしろかった。
同じ著者の『植物のあっぱれな生き方』幻冬舎新書を読んでいるが、植物のいろんなビックリがより柔らかな表現で書かれていて、大変おもしろい。
「石橋をたたいても渡らないタネたち」
「ひと味違う婚活」
「花の中は「家庭内別居」」
これらの小見出しからもおもしろそうな内容であることが伝わると思う。
発芽の3条件は「適切な温度、水、空気(酸素)」だということを小学生か、中学生の時に教わるそうだが、更に光が当たることという条件が必要だという。これだけの条件が整えば植物のタネは発芽するかというと、そうではないものもあるとこの本にある。
**秋に発芽すれば、すぐにやって来る冬の寒さで枯れてしまうからです。秋に結実する植物たちのタネは、冬の寒さが通過したあとでなければ、発芽しないのです。タネは、冬の通過を確認するために、「寒さ」を感じます。(中略)冬の寒さに出会う前のタネには「アプシシン酸」という物質が多く含まれています。この物質は発芽を抑えています。寒さを感じると、タネの中でこの物質が減ります。一方、暖かくなるにつれて、「ジベレジン」という発芽を促す物質がつくられます。春には、発芽を抑える物質が減り、発芽を促す物質が増えて、発芽がおこります。**(25頁)
後半に越冬芽にも同じことがおこると、紹介されているが、その文章には**私たちが何かを達成して「ひと花咲かせる」ためには、苦難の時期を耐えねばなりません。**(152頁)とも書かれている。植物が私たちに生き方も教えているというわけか・・・。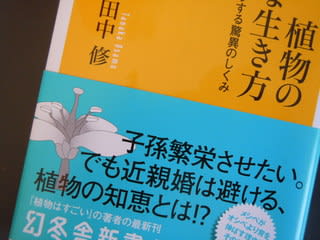
この本の帯に花のイラストが載っているが、なぜ、オシベより真ん中のメシベの方が背が高いのか? この理由が分かりやすく説明されている。近親婚を避けるための姿だそうだ。
難しいことを分かりやすく書くことは難しいと思うが、著者はそれを難なくこなしている。











