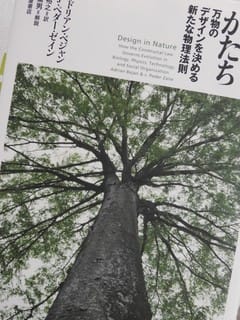
■ 4月に読み終えた本は『流れとかたち 万物のデザインを決める新たな物理法則』エイドリアン・べジャン&J・ペダー・ゼイン/紀伊國屋書店、この1冊のみ。
ヒトの体中に行きわたっている血管も肺の気道も河川の流域の様子も、みんなこの本の表紙の大木の形によく似ている。
なぜか?
**有限大の流動系が時の流れのなかで存続する(生きる)ためには、その系の配置は、中を通過する流れを良くするように進化しなくてはならない**(11頁) 要するに動きのある万物はより流れを良くするために進化するということだが、著者はこのように定義されるコンストラクタル法則で上記したことの理由を説明できるという。しかも人間の組織・社会も流動系(生物・無生物関係なく動くものはすべて流動系)として捉えることができて、この法則が当て嵌まるという! 会社組織の階層構造と河川流域の構造、なるほど確かに両者の模式図はよく似ている。
一見全く関係ないと思われるものどうしが、実は共通する法則で説明でき、つながっているということを説いた本。このような大局的なものの見方には魅せられる。
本書には次のような、なるほどと思わせるエピソードが紹介されている。少し長くなるが引用する。**一九六〇年代のルーマニアで、店頭から肉が消え始めたころ、獣医だった私の父は、ある解決策を思いついた。鶏の雛を孵すことにしたのだ。父は、卵の内部を電球で照らし出して胚が成長しているかどうかを確認できる、検卵用の箱を持っていた。当時一〇代だった私は、日々目の前で繰り広げられる血管系の成長の場面を驚異と畏敬の念を持って見つめた。卵の殻に内側に血管が伸び、やがてびっしりと広がっていった。私は、そのとき見えていたデザインが、学校で描いていた色塗りの地図の河川流域のデザインと同じであることにも気がついた。(後略)**(121頁)
こういう人だから、生物から社会システムに至るまで、あらゆる流動系は流れの抵抗を低減するように、つまり流れをより良くするように進化するという共通のパターン、コンストラクタル法則を導き出すことができたのだろう。
大変興味深い内容だった。
人や物、情報の流れも速くなっている・・・。













