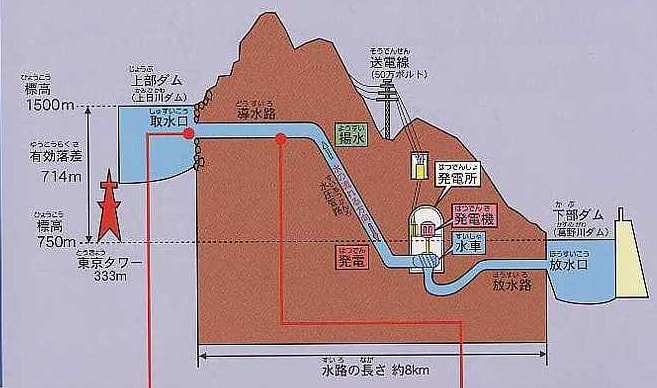「雪積む樒」(ゆきつむしきみ) 馬場 駿
寒中のわりには暖かい日だった。西高東低の気圧配置が大崩れをしたらしい。コーポラスの三階から見るいつもの景色が陽光をたっぷり受けて輝いている。遠い山々が霞み、浮かんでいる雲さえ半ば橙色に染まって春を思わせる。<o:p></o:p>
「それ終わったらコーヒー頼むな、自分で淹(い)れると濃さが変なんだ」<o:p></o:p>
「きょう本を整理するって言ってなかった?」<o:p></o:p>
炬燵(こたつ)に戻ろうとする私に、妻がベランダで洗濯物を干しながら言った。
出張先に置いてある書籍類が還ってくる。あと一と月で六十五歳、定年で仕事が終わるのだ。老夫婦だけの小さな年金生活が始まる。そう思って早々に本棚を一つにしてしまった関係で、出戻り本の収納場所が無い。もう二度と読まないものや、長年月を経て用をなさなくなった資料などを資源ゴミとして出す必要があった。<o:p></o:p>
「そう、なんだけど…」と、処分をためらう自分がグズグズと居座っている。<o:p></o:p>
書籍というものは、購入して傍らに置いたときから特別なものになる。書店に並んでいたときとは違う何かが、「関係」として生まれるのだ。実際に紐解いたり、学んだりすればその絆はより深くなる。自分が作者や編集者ならなおさらだ。<o:p></o:p>
そんなことを想いながらも観音開きの扉を開けて、最上段から一冊ずつ、指で背表紙に触れていく。<o:p></o:p>
本棚の二段目の色褪せた朱色の小冊子――<o:p></o:p>
レザックの背表紙にタイトルがやっと刷れる程度の厚みで、分厚いハードカバー本の間に遠慮がちに挟まっている。タイトルは平仮名で『しきみのように』、平成元年十二月に逝去した母、雪の自伝だ。享年七十四。仲良しの貧乏神と一生連れ添うことになった女の、前半生がこの中に遺されている。<o:p></o:p>
引き出して左掌に載せてみた。書籍用紙で九十三頁なので、比較的軽い。<o:p></o:p>
『重かったけどな、あの原稿用紙は…いや、内容も、編集も…』<o:p></o:p>
懐かしい冊子をパソコンの前に置いて、自作の編集後記を開いてみる。<o:p></o:p>
からからからっというサッシ戸が締まる音が、それに重なった。室内の空気が小さく渦巻いたような気がした。<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
『一周忌に配布すべく編集にかかりながらとうとう三回忌ぎりぎりの発刊となった。ひとえに私の怠慢に因るが弁解が許されるなら一言発したい、<o:p></o:p>
「これ以上はないというほど困難な作業だった」と。<o:p></o:p>
長兄から母の遺稿を手渡され、本にして欲しいと依頼された私は、一読して正直なところ途方に暮れた。<o:p></o:p>
「自でん」と題された母の遺稿は一つではなかった。四百字詰原稿用紙百二十八枚に及ぶ第一稿と、その改訂稿とも言うべき六十七枚の第二稿があり、それぞれが異質な香りを放っているばかりではなく読み比べていくうちに相互に矛盾する叙述に幾度か遭遇したのである。私は先ずどちらの作品を基本として編集していくのかで迷った。文章の出来で選ぶなら第二稿であり、めちゃめちゃではあっても心情の吐露の完全さで、文章のボルテージの高さで選ぶなら第一稿であった。<o:p></o:p>
結果的に私は、本作品の前半では第一稿を、後半では第二稿を採るのだが、ここで母の作品(原作)の文章上の特徴を羅列しておこう。<o:p></o:p>
先ず、句読点が全く無い。文章に段落というものがない結果、行変えという操作をしていない。分かりやすく言えば原稿用紙のマスは全て字で埋め尽くされている。台詞のルール(「」又は『』)に従わず直接話法の形で無造作に文中に入っている。加えて主語、述語の欠落が目立ち、文章の前後がかみ合わないところへもってきて、意味上の倒置法を多用し、本人にしか分からない事実を一方的に省略しているので、第三者は立ち往生せざるをえない。接続詞は皆無に等しく、誤字、脱字、あて字が氾濫している。<o:p></o:p>
それにもかかわらず、否、そうであればなおさらに、母の無知、苦悩、逡巡、善意がせつせつと胸に迫り涙をさそうのは不思議である。』<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

「駿、これ何て読むの? どういう意味?」<o:p></o:p>
いったい何回問われただろう、この母に。<o:p></o:p>
かつて一世を風靡した漫才のミヤコ蝶々が上方トンボに「何とゆう字?」と何度も訊いたことから相方の芸名が南都雄二(なんとゆうじ)に改まったという逸話は有名だが、私も母にとっては同様な存在だったのだろうか。当用漢字を読めるというだけでは応えきれないと悟った私は、母が差し出す単行本や学会雑誌、宗教新聞そのものを読破するようになった。当時の新興宗教に関するものだけに、日蓮の「御書」をはじめ仏教用語の数々、歴史上の人物の名や官位名・職名といったものまで調べる羽目に陥っている。一体が罰当たりなので、長じても宗派の折伏(しゃくぶく)に理論的に抗して宗教的な中立を護ってはいたが、母のお陰で信者に匹敵する知識を蓄えてしまった。もっとも小学校一、二年の頃までは母に従って朝の勤行(ごんぎょう)もしていた。母が私を傍らに座らせ拝ませるときの殺し文句は、「丈夫になる」と、「頭が良くなる」の二つだったと記憶している。このいずれのご利益も時を経て、自分自身でその存否を判定することではあるまい。<o:p></o:p>
そう言えば、ずっと蟠(わだかま)っていたことがある。勉強とか、学問とか、教育とか、そういったものに母は、表面上全くと言ってもいいほど関心を示さなかったが、実際はどうだったのかということだ。試験で満点を取っても、毎年委員長になっても、児童会長になっても、何に表彰されても、「それがどうした」という顔で通した母。成績の通信票などは出しても見向きもしなかった。「自分でハンコ押しな」と認め印のある場所を指差すだけなのだ。中学生になるとさすがに私も諦め、何も報告しなくなった。生活に追われ、それどころではないのだろうと勝手に納得もした。「いい成績なのになぁ」と私は、口を尖らせて校庭の隅で空を見上げた 記憶がある。「勉強しろ」とか「宿題やったか」といった類の台詞を一度も吐かなかった母の真意が奈辺(なへん)にあったのかは不明だ。一方、大工だった父には名言がある。「教室で先生に習ってまた家で勉強してるってのは頭が悪いからか」。これを聞いてから私は、家での予習、復習や試験準備を一切止めている。<o:p></o:p>
昭和三十九年県立高校一年の秋、父が何度目かの脳溢血で倒れた。父は塩を嘗め嘗め冷酒をあおるような男だった。<o:p></o:p>
私は思い詰めて確かこんな質問をした。<o:p></o:p>
「大学まで行かせてくれるの、どうなの?」<o:p></o:p>
針を動かし繕(つくろ)い物をしていた母は、私の顔も見ずにただ黙りこくっていた。そんなこと聞くほうが可笑しい、とでも言うように。否定を伝えるには最も有効な対応だった。<o:p></o:p>
結局私は、寝たきりの父の「義務教育は終ったんだから働いて食い扶持(くいぶち)を入れろ」という言葉を間接的に知らされて愕然とし、その年の暮を待たずに、任意退学をしている。あえて言えばこのときの学級は選抜クラスだった。決断した場面でも母のコメントは何も無かった。胸の中で名状しがたい虚しさが渦巻いたのを憶えている。<o:p></o:p>
「独学とアルバイト生活の二十年」はこのときから始まる。(続く)
====連載を始めるにあたって、後藤和弘============
小生の友人に木内光夫さんという人がいます。伊豆の伊東市に住んでいて、岩漿文学会のお世話をしています。その同人誌、「岩漿」の毎号に、筆名の馬場 駿で力作の小説を掲載しています。
今年、発行の21号では、短編「雪積む樒」という小説を発表しています。貧困だった生い立ちを自分の母を主人公にした感動的な話でした。母親の深い情愛と破天荒な生き方が描き出されていて、しかもストーリー展開が面白いのです。小説はやっぱりストーリーが面白いことが一番重要だと改めて知りました。
そこで著者の馬場 駿さんへその小説、「雪積む樒」をこのブログで連載にして掲載することをお願い致しました。
本日、快諾のご返事とともに全文が送られてきました。原稿は縦書きですが、ブログでは横書きに変更せざるをえませんでした。
慎重に推敲のなされた文章は読んでいて気持ちの良いものです。
馬場 駿の文章世界をお楽しみ下されば嬉しく思います。
是非、ご覧下さい。なお挿絵の写真は樒(しきみ)の花です。
なお関連記事は:総合文芸誌、「岩漿」第21号のご紹介です です。あわせてご覧下さい。
================================