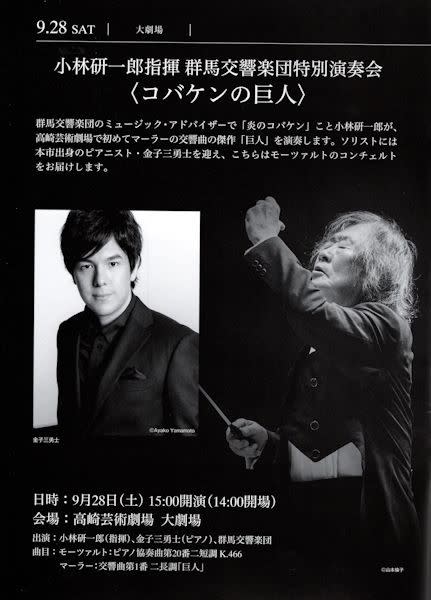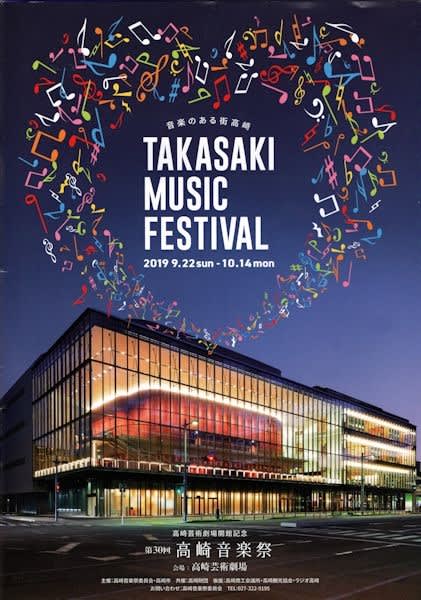長野県伊那市で、ワルシャワ室内歌劇場によるモーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」の公演があったので、出かけてきました。比較的近いところで聴けるのはありがたいことです。

(出 演)
指揮:ピョートル・スワコフスキ
演出・リシャルト・ペリット
アルマヴィ-ヴァ伯爵:スタニスラフ・クフリュク
伯爵夫人:エヴァ・トラッチ
スザンナ:イングリダ・ガポヴァ
フィガロ:アルトゥル・ヤング
ケルビーノ:ヤン・ヤクブ・モノヴィド
マルチェリーナ:エルジュビェタ・ヴルブレフスカ
その他
管弦楽:ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場管弦楽団
合唱:ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場合唱団
(感 想)
「フィガロの結婚」のストーリーは、当時の封建制時代なら刺激的で受けたのかもしれませんが、現代ではそれほど面白いものではありません。登場人物が多くて、ストーリーがこんがらかるような気もします。しかし、出てくるアリアなどは、ヒット曲満載なので、それを中心にして観劇していました。
演出がシンプルで、余分な小道具や過剰な演出はなく、簡素でよかった。また、オーケストラも40人位と少人数ですが、伴奏という点からは十分でした。歌手に有名な人はいませんが、フィガロを歌ったアルトゥル・ヤング(バリトン)は、まずまずで「もう飛ぶまいぞこの蝶々」は楽しめました。
常設の歌劇場のためか、出演者の演技はこなれたもので、その点は感心しました。チケットは、S席(SSはなし)でも7千円なので、お得感がありました。そのためもあってか、会場は、7~8割くらいは席が埋まっていました。こういった公演が近くであれば、長野県内でもオペラやクラシックのファンが増えるかもしれません。
映像作品も多く出回っていますが、オペラはなんといっても実演が面白い。オペラについては、東京に行かなければほとんど観ることができないので、日程、予算がままならならず難しいのが残念なところです。
【参考に観たブルーレイディスク】

ダニエル・バレンボイム指揮 シュターツカペレ・ベルリン。ドロシア・レシュマン、ルネ・パーペ、ロマン・トロケルら出演。
【長野県伊那文化会館と周りの春日公園の光景】

伊那文化会館のあるところは、伊那市の春日公園の一角で、樹木や散策コースが整備されています。右側に見えるのが、会館です。

入口。

フィガロの結婚の立て看板。

伊那文化会館の下の方になります。午後3時の開演まで時間があったので、この場所で本を読んでいました

枯葉。秋が深まっています。