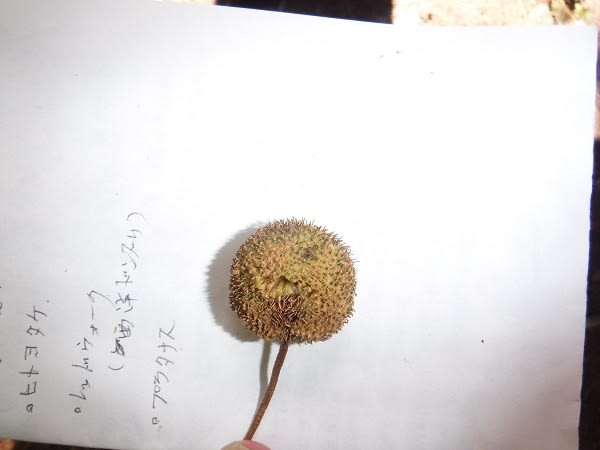今春は枝垂れザクラにこだわっている。22日、23日、昨日、そして本日とこれまで4日間にわたって札幌市内で枝垂れザクラがあるというところ巡って歩いた。その結果、“まずまず” のところもあれば、“まだまだ” のところもあった…。
私が枝垂れザクラ桜にこだわることに特に大きな理由はない。ただ、枝垂れザクラの場合はその木が一本でもあれば、それで十分に楽しめるところがあると思っている。対して、その他のサクラの場合はある程度まとまって咲いていて初めて美しいなぁ、と感ずるところが私にはあるように思えるところから、ちょっと枝垂れザクラにこだわってみようと思ったのである。
そこで私が事前に持っていた情報、そしてネットで調べた情報から、次の5ヵ所を枝垂れザクラ巡りのポイントと狙いを定めた。その5ヵ所とは…、
① 中島公園
② 円山公園
③ 発寒公園
④ 北海道大学構内
⑤ 旧軽川沿い
の5ヵ所である。
まず22日(土)である。中島公園の日本庭園内にある枝垂れザクラは、開花はしているもののまだまだという感じだった。
続いて、23日(日)、旧軽川に行ったのだが、旧軽川に至る前に中の沢川を歩きはじめたら雨が降ってきたこともあって、わずかに歩いただけで断念した。ただ、引き返す際に近隣の住宅地を車で走っていると、見事な枝垂れザクラに出会った。個人宅の庭だったが、周辺では有名なようで何人かの方が写真を撮っていた。サクラの樹の下には「糸桜」という札が書かれていた。残念ながらとっさのことだったので場所が特定できないのが残念である。


昨日25日(火)、地下鉄を使って精力的に巡り歩いた。まずは北大附属病院前を訪れたが、枝垂れザクラはほんどがつぼみ状態で “まだまだ” だった。
続いて発寒公園を訪れた。こちらはどこに枝垂れザクラが?という感じで、地元の人らしい方に伺うと、「池の周りに植わっているでしょう」と言われて確かめてみると確かに枝が枝垂れている樹が何本か確認できた。しかし、いかにも小さい。件の地元の方も「まだまだ小さくて、それほどではないですよ」とのことだった。こちらが見ごろとなるには、最低でも十数年後のことかもしれない。
訪れるかどうか迷ったのだが、一応中島公園にも寄ってみた。すると満開とは言えないかもしれないが8分咲き程度で十分に美しい状態だった。これ以上のジャストタイミングを図るには日参する必要がありそうなので、私としてはこれで満足ということにしたい。



最後に円山公園に向かった。ここの枝垂れザクラはまだ青年の樹といった感じなのだが、ネットでの写真を拝見すると十分に観賞に耐えられると思いリストに加えた。そこで行ってみたのだが、北大附属病院前のものよりさらに固いつぼみ状態だった。素人診断では満開状態になるのはゴールデンウィークに入ってからではと思えるほど “まだまだ” の状態だった。
そして本日午後、旧軽川に向かった。旧軽川は直線化された軽川にその役目を譲り、河川としての役割はほぼ終えた感じの小さな流れだった。ところがサクラ並木は素晴らしかった。高い河壁の上から覆いかぶさるように咲き誇る桜並木は、私がこれまで見た札幌の並木のなかでは最も素晴らしいのではないかと思われた。


※ 旧軽川沿いに咲いていたこれらのサクラは枝垂れザクラではありません。
そんな並木の中を福島県の「三春瀧桜」のクローンだという枝垂れザクラを探したのだがなかなか見つからない。初めは左岸を遡ったのだが見つけることができなかった。上流の旧軽川の行き当たりから折り返して右岸を下流に向かって探し続けたところ、川の中盤付近でようやく発見することができた。枝垂れザクラは運良く満開状態だった。樹の根元には「天然記念樹 三春の瀧桜」と記されていた。枝垂れザクラの樹としてはまだ小ぶりであるが、枝垂れたサクラの様子は将来本家の福島県の「三春瀧桜」のような姿になるのだろうか?それはともかく、苦労して見つけ出しただけに、満足一杯の思いで帰路についた。なお、場所的には手稲区前田8条4丁目辺りではないかと思われる。

※ 思っていたよりは小ぶりでしたが、まぎれもなく探していた枝垂れザクラでした。


“まだまだ” 状態だった残り2ヵ所の枝垂れザクラをこの後も追ってみたいと思っている。