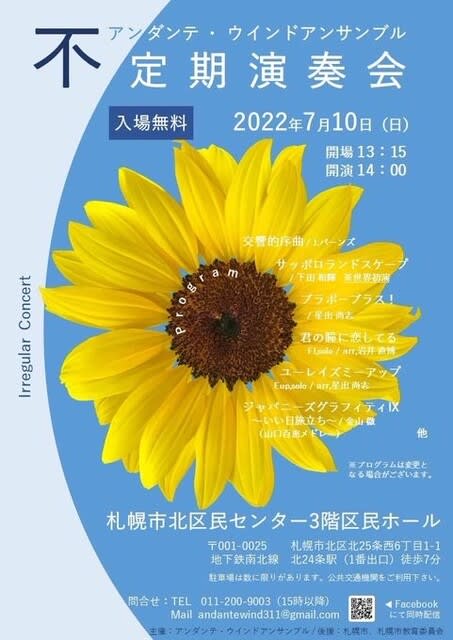7月10日から始まっていたライデン国立古代博物館所蔵の「古代エジプト展」に昨日、満を持して足を運んだ。古代エジプト人が紀元前3,000年前にもはやヒエログリフという象形文字を持っていたことが私にとっては一つの驚きだった。

北海道立近代美術館で開催されているライデン国立博物館所蔵の「古代エジプト展」は大変な人気である。連日、続々と観覧者が詰めかけているのが我が家から見て取れる。先日18日は「海の日」で祝日だったが、開館前の9時30分には入口前に長蛇の列ができていた。その数は百数十人が行列を作っていたように見えた。「私もいつかは…」と思っていたが、行列を見ていささか恐れを抱いた。そこで考えた作戦は、夏休みが始まる前の平日の午後、しかも閉館前が狙い目ではと考えた。
私は作戦どおり昨日20日(水)午後3時に近代美術館に向かった。作戦はまあまあ的中したのではと思う。観覧者はけっして少なくはなかったが、大混雑という状況ではなかった。

展覧会はオランダのライデン国立古代博物館が所蔵する大小250点のコレクション(出土品)が展示されていた。そこで印象的だったのは、出土品の中に彩色されているものが多かったこと。そして、“ヒエログリフ” と称される象形文字が彫刻されていることだった。この象形文字を19世紀初頭、フランスの研究者シャポリオンが解読したことによってエジプト研究は飛躍的に進んだという。
そして今回の展覧会の目玉は、ミイラとそれを保管していた豪華な棺が10点以上展示されていたことだ。古代エジプト人は来世での永遠の生があると考え、位の高い人たちは遺体を豪華な棺に入れ、副葬品にもたくさんの豪華な品々を添えたといわれ、それらが数多く展示されていた。棺の表面には “ヒエログリフ” がびっしりと描かれているのも印象的だった。

※ 近代美術館の中で唯一写真撮影が許されたところにあった「内棺」の模型です。この棺(右側)にミイラを入れ、左側の蓋をしたようです。これは内棺で、さらにこれを外棺で覆い埋葬したようです。
また、もう一つの呼び物は全身を包帯に包まれたミイラをCTスキャンによって内部を透視する画像が公開されていたことである。技術の進展が古代文明の解明に大いに寄与している一例かと思われた。

※ 近代美術館の西側エントランスです。18日の開館前はここがびっしりと観覧者で埋まっていました。
それにしても、と私は考えた。なぜ古代エジプトの貴重な出土品がオランダに保管されているのだろうか?と…。ライデン国立古代博物館には約25,000点ものエジプト・コレクションが収納・展示されているという。それはオランダがエジプトの地で発掘調査を続けてきた結果かもしれない。また、19世紀から20世紀にかけてオランダが世界に冠する海洋国家だったことも影響しているのだろう。おそらくエジプト一国では 古代エジプト文明の解明もここまで進んでいなかったことは十分予想される。また、これら出土品がオランダで保管されていたからこそ、私たちが今日札幌で目にすることができた、ということも言えるだろう。それにしても…、という思いが私の中では拭えない。
それはまた、私が若き日に訪れた体験を持つ、ロンドンの大英博物館、パリのルーブル美術館の膨大な海外からのコレクションを目の前にしたときも同じような思いに駆られたことを思い出している…。