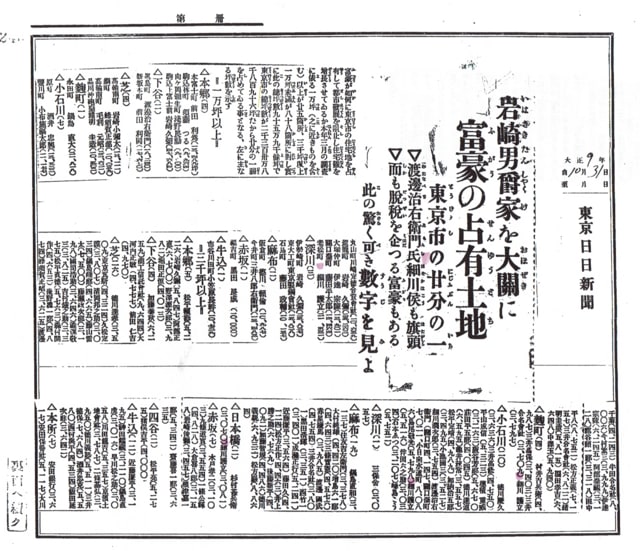元禄十五年の今日三月十四日、肥後細川藩士・佐分利七兵衛が死去している。俳人の佐分利越人に比定されているが?
この人物は一時期名古屋に過ごし、芭蕉門下の俳人(十哲の一人)として名を成したと言われている。
後代の熊本に於ける俳人・久武綺石(文化二年歿)の墓石に刻まれた次のような文章がある。
「俳諧者滑稽之流也、而其始也戯謔而也、及芭蕉翁同其體栽、而燮風旨、然後言近而指遠者有焉、謂之正風、吾藩佐分利越人、嘗出居濃洲、學於蕉門、及其後歸也、職事鞅掌、不暇傳人、正風自綺石子云」
これによると、佐分利越人は紛れもない蕉門の人物で、熊本俳壇の先駆者ということになる。
佐分利越人に比定されたこの人物は佐分利家の分家・(南東47-10)佐分利彦右衛門家の初代・七兵衛氏恒である。
本家・(南東45-3)佐分利加左衛門家の初代・作左衛門の息・兵太夫の時に分家し、その息・彦右衛門(兵大夫)に至ったが「寛文十一年(1671)八月六日知行(五百石)被召上、倅七兵衛ニ元禄四年(1691)三拾人扶持被下候」という事態が起こっている。
この七兵衛が越人に比定されている人物だが、肥後先哲遺蹟は先の久武綺石の墓石文と共に次のような人物紹介をしている。
佐分利越人 七兵衛と称し、名は氏恒、越人は其俳名なり。芭蕉の門に入り俳諧を善くせしを以て名あり。
佐分利家は熊本藩の佐分利流槍術家なり。越人は其家の養子たるものなり。故ありて肥後を辞し、
尾州名古屋に来り、紺屋を業となす。元禄十五年三月十四日没す。享年未詳、墓は坪井流長院。
父親・彦右衛門(兵太夫)が「故ありて」細川家を召し放されてから、七兵衛が30人扶持で再度召し直されるまで、20年経過しているのだが、この間名古屋へ出て染物屋を生業として、蕉門にあって名を挙げた人物だとしている。
上の紹介文にある様に七兵衛は養子であり、実は島又左衛門(何代か不明)の三男である。
これに著作「うらやまし猫の恋 越人と芭蕉」を通して真向から異論をとなえたのが著者・吉田美和子氏である。
「芭蕉の弟子・越人」を熊本の佐分利氏だとする説を完全否定している。(この本はものすごく面白い)
吉田氏は、幕末文政年間に出された遠藤曰人著「蕉門諸生全伝」が「肥後熊本の出身、細川越中守の近習佐分利流槍術家佐分利勘左衛門であるとする誤伝」だと断定されている。
吉田氏に著書の中にある「越人・芭蕉 略年譜」によると、越人の没年は享保二十年(1735)頃としてあり、全くの別人である。
大いに説得力のある史料であり、先の久武綺石の墓碑にあるものも、こういう風説を承知しこれに倣ったものなのではなかろうか?
これ等の事は、熊本に於いて検証を加えるという事は成されなかったのだろうか。熊本の文学界はどうとらえているのか、その意欲はないのか・・・??
名著「肥後先哲遺蹟」の記述内容が間違いを犯しているという、重要な問題でもある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに「うらやまし猫の恋」は、去来が著した「去来集」に芭蕉の言葉を要約した文章にある次の句に由来する。
うらやましおもひ切時猫の恋 越人
先師(芭蕉)、伊賀よりこの句を書き贈りて曰く、「心に風雅あるもの、一度口にいでずといふ事なし。かれが風流、
ここに至りて本性をあらはせり」となり。これより前、越人、名四方に高く、人のもてはやす発句おほし。しかれど
も、ここに至りて初めて本性を顕すとはのたまひけり。
猫の恋とは春の季語で、「恋に憂き身をやつす猫のこと。春の夜となく昼となく、ときには毛を逆立て、ときには奇声を発して、恋の狂態を演じる。雄猫は雌を求めて、二月ごろからそわそわし始め、雌をめぐってときに雄同士が喧嘩したりする。」