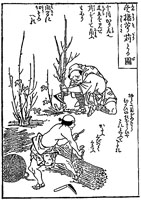2013-07-13 05:48:13 「メモ」という一文で、沢村大学の帰参についての資料をご紹介した。
寛永元年沢村大学は知行地の豊前至津村の百姓がおこした訴訟に関し、三齋の機嫌を損ない豊前をあとにして備前岡山藩主松平宮内少輔(池田忠雄)のもとに厄介になる。忠雄の仲介も有り忠利は「召し直し」をするのだが、その折帰参後に住まう屋敷について指示をした文書をご紹介した。
以前は大学が住んでいたのであろうか、ここのは後に大学の養嗣子となる松井宇右衛門が住んでいる。これを立退かせ転居を指示するものである。
今般東京で「御軸・御道具」を扱っておられるF様からお手紙をいただいた。松井宇右衛門宛ての忠利書状のコピーが同封されてあった。
一見して大学の帰参に関する書状だということが判り、この間の事情を補強するものだと確信をした。
これがまさしく上記のことを、直接宇右衛門に指示をした書状であった。その大意は以下の如くである。
この度大学を召し直すに当たり、宇右衛門に遣わした家を大学に戻したい。
度々の引越し迷惑だと思うが後々の事は良きように取り計らうのでその旨を伝えておく。
このことが切っ掛けになったのかどうかは判らないが、八年後の寛永十年大学は宇右衛門を養嗣子とするのである。
忠利の肝煎りであることは容易に想像に難くない。三齋の肝煎りではないと思われるのは、三齋と大学の和解はこれから十七年の後に成るからである。