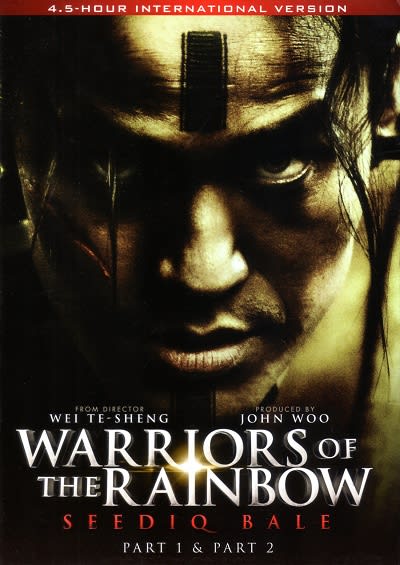ブッチ・モリス『Possible Universe / Conduction 192』(NBA/SAJazz、2010年)を聴く。

David Murray (ts, bcl)
Evan Parker (ts)
Pasquale Innarella (as)
Greg Ward (as)
Joe Bowie (tb)
Tony Cattano (tb)
Meg Montgomery (el-tp)
Riccardo Pittau (tp)
Jean-Paul Bourelly (g)
On Ka'a Davis (g)
Harrison Bankhead (b)
Silvia Bolognesi (b)
Chad Taylor (ds, vib)
Hamid Drake (perc)
Alan Silva (syn)
Lawrence D. "Butch" Morris (conductor)
・・・というか、再生するまでDVDだと思っていた。ニューヨークのDowntown Music GalleryでもDVDの棚に置いてあったし。故ブッチ・モリスの「コンダクション」が、実際にはどのような指示を出し、どのようなプレイヤーの自由度をもって繰り広げられていたのか興味があっただけに、とても残念。
それはそれとして、なかなか豪華なメンバーである。トロンボーンがいることで、サウンドの分厚さが強調されているように聴こえる。アラン・シルヴァのシンセも目立っている。そして何より、エヴァン・パーカーとデイヴィッド・マレイが一緒に座ってテナーサックスを吹くなんて考えられない。ここではパーカーも見せ場を作るのではあるけれど、マレイの味が目立ちまくっている。
いやホントに、映像であったらどんなに愉しかっただろう。