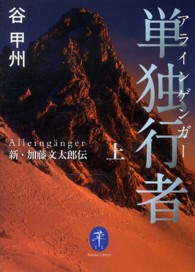
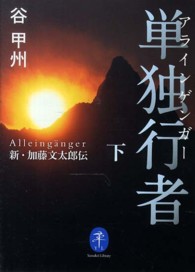
「単独行者(アラインゲンガー)新・加藤文太郎伝」(上・下)谷甲州
以前から気になっていた作品。
加藤文太郎伝と言えば、新田次郎氏の「孤高の人」。
故にサブタイトルが「新・加藤文太郎伝」と「新」と付いている。
いったい、どう違うのか?
一番大きな違いは、山岳シーン中心に書かれていること。
職場の人間関係、家族との関係は最小限に抑えられている。
人生最大の節目である結婚さえ、軽く流している。
しかし、山岳シーになると、細かく非常にリアル。
それもそのはず、著者は山屋として文壇でもトップクラスの経験と実力を持っている。
故に、自然描写、冬山シーン、ルートの描き方も見事。
当時のデータも交えて描写される。
P365
たとえば陸軍の歩兵は通常、一日につき六合の精米が支給されることになっている。重量にして約0.9キロだから、加藤の行動食と重量の点ではそれほど差がないことになる。とはいえ米よりも多少軽量化されていて、緊急時には調理不要なのだから甘納豆の方が有利ではある。(一合の米=お茶碗3杯~4杯である。私なら六合の米で1週間過ごせる・・・昔の人は大食いなのか?おかずを食べないから、1日でこれだけ、食べることが可能なのか?昔の人は燃費が悪いのか?)
前半の山場は昭和5年の立山山行。
他のパーティと目標が重なり、一緒に行動しようとする。
しかし、徹底して疎外される。
この描写もすばらしく、読んでいて我が事のように感じられ、忸怩たるものがある。
この山行後、迷いを吹っ切り、「単独行者」としての登山を確立する。
後半の山場は、昭和11年1月、最後の山行となった北鎌尾根。
どうして遭難したのか、リアルに再現している。
こうしていたら、ああしていたら、と胸がふさがる思い。
悲劇に向かって怒濤の展開である。
先ほど、「孤高の人」との違いに触れたが、さらに2点追加しておく。
「孤高の人」では宮村健、「アラインゲンガ―」では吉田登美久の描き方が異なる。
「孤高の人」では加藤文太郎の足をひっぱって、その結果、遭難したかのような描き方。
「アラインゲンガ―」では、若き優秀な登山家として描かれている。
少なくとも、登攀技術では、加藤文太郎を凌駕している。
二人の気が合う様子も納得の描写である。
加藤文太郎は、自分にないものを感じたのであろう。
もう一つ、本書の特徴は、当時の案内人と登山者の関係を丁寧に説明している事。
当時では、通例、案内人を雇う。
社会人も大学山岳部も同様。
また、当時の登山者が、エリートであったこと。
これらが、分かりやすく説明されている。
主人公の疎外感と自負心、当時の登山界の雰囲気を感じることが出来た。
【関連図書】

【ネット上の紹介】
昭和十一年一月、厳冬の槍ヶ丘・北鎌尾根に消えた加藤文太郎。冬季登山の草創期、ガイド登山が一般的だった時代に、ただひとり、常人離れした行動力で冬季縦走を成し遂げていった「単独行者」は、なぜ苛烈な雪山に挑みつづけたのか。構想三十五年、加藤文太郎の真実の人間像に挑む本格山岳小説。
















