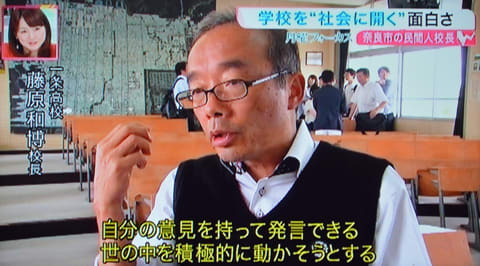昨夕(10/17)の関西テレビ「みんなのニュースワンダー」で、奈良市立一条高校の「よのなか科」の取り組みなどが紹介された。昨朝には民間人校長・藤原和博(ふじはら・かずひろ)さんがご自身のFacebookに
関西TVを見られる人限定!本日、一条高校のスマホを使った授業の様子がニュース報道されます。18時15分~19時までの間(18時25分くらいという噂)ですが、事件や災害があればスイマセン飛びます。校長室、図書館改造後のプログラミング倶楽部の生徒達、よのなか科、女子テニス部も登場か?
と書き込みされていた。「女子テニス部」は少しミスマッチな感じだが、藤原さんはテニスがお得意なので、部活の指導もされるのだろう。gooテレビ番組によると、

スマホは検索にも使う。教師の「ググってみよう」のかけ声で、一斉に検索を始める
奈良市立一条高等学校ではスマートフォンを使用した授業が行われている。藤原和博民間人校長は「おそらく世界でもどこもやっていない試み」「非常にチャレンジングなことになってくる」など語る。今回は藤原民間人校長がしかけた教育改革に迫る。
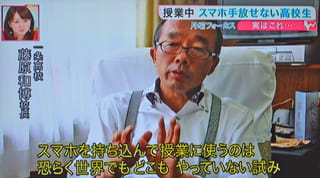
ことしWi-Fi環境が整備された奈良市立一条高等学校ではスマートフォンを使用して生徒たちの意見などを集めるなど、スマートフォンを活用した授業が行われている。生徒たちは「普段手を挙げるなどあまりできないが、スマホは匿名なので素直な意見が言える」「色んな意見を見られるから勉強にもなるし、楽しく出来ると思う」など述べている。教師側も「生徒の意見を短時間で集められるメリットがあるなどとしている。

「近代化の過程で失ったものは何だろう?」の問に、スマホで自分の考えを専用サイトに送る
スマホ授業を導入した藤原和博民間人校長は「高校生にとってはスマホが手足かあるいは脳の一部のように使っている。もっとスマホを使うことで学びが豊かになったり、先生たちへのフィードバックができるようになったりなどで思考力・判断力が深まることになればいいと思うなど述べている。藤原校長は東京・杉並区の和田中学校で初の民間人校長を務める。夜間授業などの創設で注目を集めた。
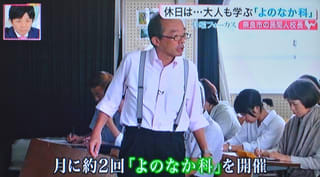
藤原和博さんは生徒との距離を埋めるため部活動にも顔をだし一緒に汗を流す。休日には月2回の「よのなか科」の授業を保護者や地域の人にも来てもらっている。なぜ高校生活の貴重な時間を部活に使うの?という議題では「達成感」「愛を体に覚えさせるため」などの答えが出た。授業について生徒は「大人の人に全部教えてもらうのではなく ちょっと助けてもらって自分で考えることが、すごい想像力がつよくなる」などと話した。

放課後の図書室でも社会とのつながりが生まれていた。旅行予約サイトなどの職員が定期的に訪れ観光を良くする方法を一緒に考えている。藤原和博さんは「もっと開かれた事業が公立で増えて行けばいいと思う」などと話した。木本武宏は「スマホを使う授業は楽しくて 素直に自分の中に入ってきそうな感じもする」などと話した。

教師が「近代化の過程で失ったものは何だろう?」と問いかける。すると生徒たちは一斉に各自のスマホから専用のサイトに自分の意見(匿名)を書き込む。30人の意見が出たところで「公開」し、教師がコメントする、という仕組みだった。

藤原校長は「スマホを持ち込んで授業に使うのは、おそらく世界でもどこでもやっていない試み」という。確かにこれはグッドアイデアだ。私も短大で授業をしているが、こんな仕組みで即座に皆の意見が拾えたら、とても便利だろう。

おお、これはじゃらんのSさん!
しかし、さらに驚いたことがある。休日に月2回程度実施している「よのなか科」の授業では、生徒だけでなく、保護者や地域の人も参加しているというのだ。大人は上から目線で説教するのでなく、生徒が考えを深めるためのちょっとしたヒントを出すのだ。これは生徒のタメになるし、大人にとっても良い刺激になることだろう。

Sさんから、鋭いツッコミが入る

私は藤原氏の本は、何冊か読んでいる。『処世術』『藤原和博の必ず食える1%の人になる方法』『本を読む人だけが手にするもの』…。『必ず食える…』では、読者を「社長タイプ」「自営業タイプ」「公務員タイプ」「研究者タイプ」の4つに分け、それぞれのタイプごとに7つの条件を示す。たった7つの条件さえクリアできれば、誰でも1%の人になれる、特別な才能はまったくいらないという話で、これは興味深い。ただしそれには大前提となる「3条件」があって
1.パチンコをしない人になれ!
2.ケータイゲームを電車の中でしない人になれ!
3.本を月1冊以上読む人になれ!
というものだ。たいていの志ある人は、この3条件くらいはクリアしているのではないだろうか。ちなみに私は「経済以外の価値(家族、友達、個人的な活動、社会貢献)を重視するプロ(独立)志向の研究者タイプ」と出た。そのためには上記3条件に加え「一生捧げてもいいと思えるほど好きなものがあるか」「あなたのファンをつくれるか」などの4条件をクリアしないといけない。

宮崎哲弥を久々に見た。やや肥った?
自分のタイプを見定めたら、1%の人間(100人に1人の人間)になるために努力しなければならない。藤原氏の言葉を借りると(東洋経済ONLINE)、
1つの分野を極めて頂点に立つには、熾烈な競争に勝たないといけないんです。たとえば、オリンピックのメダリストになるのはだいたい「100万人に1人」。ノーベル賞を受賞するのは「1000万人に1人」です。普通の人はどんなに努力しても難しいですよね。
でも、「100人に1人」なら努力すれば誰でもなれる。だから、1つの分野でまず「100人に1人」になって、そうしたらそのまま突き進むのではなくて、横にスライドして別の分野で「100人に1人」になる。また横にスライドして別の分野で「100人に1人」になる。そうすれば、「100人に1人」×「100人に1人」×「100人に1人」=「100万人に1人」と、オリンピックのメダリスト級のレアな人になれるというわけです。
あなたがベテランのツアーコンダクターだとする。これは100人に1人(1%)程度のことだろう。そこにブリーダーや盲導犬訓練士にチャレンジして100人に1人の犬のプロになる。すると1%×1%=0.01%の人、つまり1万人に1人のレアな人材になり、「犬連れツアコン」という新ビジネスを立ち上げることができる、ということになる。

話が脱線してしまったが、つまるところ「よのなか科」とは([よのなか科]ネットワーク)、
藤原和博氏が提唱している「学校で教えられる知識と実際の世の中との架け橋になる授業」のこと。教科書を使った受身の授業とは異なり、自分の身近な視点から世界の仕組み、世の中の仕組みなど、 大人でも簡単に答えを出せないテーマ(「ハンバーガー1個から世界が見える」、「模擬子ども区議会」、 「少年法の審判廷ロールプレイング」など経済・政治・現代社会の諸問題)を扱う。授業の特徴として藤原氏は以下の特徴を挙げている。
(1)ロールプレイやシミュレーションなどゲーム的手法によって子ども達の主体的な学びを創造する。
(2)大人も授業に参加することで、ともに学び合う力を付ける。
(3)カリキュラムの目的に沿ったゲストを迎え、生徒の思考回路を刺激し、ときに通常の授業では得られない種類の知的な感動を与える。
ということで、これは斬新かつ効果的な試みである。一条高校の今後の取り組みに、大いに注目したい。
関西TVを見られる人限定!本日、一条高校のスマホを使った授業の様子がニュース報道されます。18時15分~19時までの間(18時25分くらいという噂)ですが、事件や災害があればスイマセン飛びます。校長室、図書館改造後のプログラミング倶楽部の生徒達、よのなか科、女子テニス部も登場か?
と書き込みされていた。「女子テニス部」は少しミスマッチな感じだが、藤原さんはテニスがお得意なので、部活の指導もされるのだろう。gooテレビ番組によると、

スマホは検索にも使う。教師の「ググってみよう」のかけ声で、一斉に検索を始める
奈良市立一条高等学校ではスマートフォンを使用した授業が行われている。藤原和博民間人校長は「おそらく世界でもどこもやっていない試み」「非常にチャレンジングなことになってくる」など語る。今回は藤原民間人校長がしかけた教育改革に迫る。
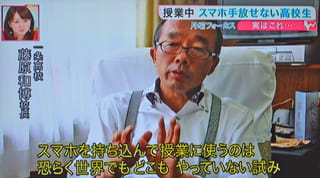
ことしWi-Fi環境が整備された奈良市立一条高等学校ではスマートフォンを使用して生徒たちの意見などを集めるなど、スマートフォンを活用した授業が行われている。生徒たちは「普段手を挙げるなどあまりできないが、スマホは匿名なので素直な意見が言える」「色んな意見を見られるから勉強にもなるし、楽しく出来ると思う」など述べている。教師側も「生徒の意見を短時間で集められるメリットがあるなどとしている。

「近代化の過程で失ったものは何だろう?」の問に、スマホで自分の考えを専用サイトに送る
スマホ授業を導入した藤原和博民間人校長は「高校生にとってはスマホが手足かあるいは脳の一部のように使っている。もっとスマホを使うことで学びが豊かになったり、先生たちへのフィードバックができるようになったりなどで思考力・判断力が深まることになればいいと思うなど述べている。藤原校長は東京・杉並区の和田中学校で初の民間人校長を務める。夜間授業などの創設で注目を集めた。
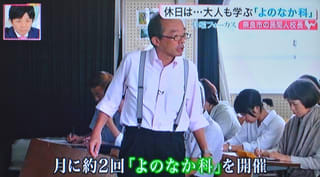
藤原和博さんは生徒との距離を埋めるため部活動にも顔をだし一緒に汗を流す。休日には月2回の「よのなか科」の授業を保護者や地域の人にも来てもらっている。なぜ高校生活の貴重な時間を部活に使うの?という議題では「達成感」「愛を体に覚えさせるため」などの答えが出た。授業について生徒は「大人の人に全部教えてもらうのではなく ちょっと助けてもらって自分で考えることが、すごい想像力がつよくなる」などと話した。

放課後の図書室でも社会とのつながりが生まれていた。旅行予約サイトなどの職員が定期的に訪れ観光を良くする方法を一緒に考えている。藤原和博さんは「もっと開かれた事業が公立で増えて行けばいいと思う」などと話した。木本武宏は「スマホを使う授業は楽しくて 素直に自分の中に入ってきそうな感じもする」などと話した。

教師が「近代化の過程で失ったものは何だろう?」と問いかける。すると生徒たちは一斉に各自のスマホから専用のサイトに自分の意見(匿名)を書き込む。30人の意見が出たところで「公開」し、教師がコメントする、という仕組みだった。

藤原校長は「スマホを持ち込んで授業に使うのは、おそらく世界でもどこでもやっていない試み」という。確かにこれはグッドアイデアだ。私も短大で授業をしているが、こんな仕組みで即座に皆の意見が拾えたら、とても便利だろう。

おお、これはじゃらんのSさん!
しかし、さらに驚いたことがある。休日に月2回程度実施している「よのなか科」の授業では、生徒だけでなく、保護者や地域の人も参加しているというのだ。大人は上から目線で説教するのでなく、生徒が考えを深めるためのちょっとしたヒントを出すのだ。これは生徒のタメになるし、大人にとっても良い刺激になることだろう。

Sさんから、鋭いツッコミが入る

私は藤原氏の本は、何冊か読んでいる。『処世術』『藤原和博の必ず食える1%の人になる方法』『本を読む人だけが手にするもの』…。『必ず食える…』では、読者を「社長タイプ」「自営業タイプ」「公務員タイプ」「研究者タイプ」の4つに分け、それぞれのタイプごとに7つの条件を示す。たった7つの条件さえクリアできれば、誰でも1%の人になれる、特別な才能はまったくいらないという話で、これは興味深い。ただしそれには大前提となる「3条件」があって
1.パチンコをしない人になれ!
2.ケータイゲームを電車の中でしない人になれ!
3.本を月1冊以上読む人になれ!
 | 藤原和博の必ず食える1%の人になる方法 |
| 藤原和博 | |
| 東洋経済新報社 |
というものだ。たいていの志ある人は、この3条件くらいはクリアしているのではないだろうか。ちなみに私は「経済以外の価値(家族、友達、個人的な活動、社会貢献)を重視するプロ(独立)志向の研究者タイプ」と出た。そのためには上記3条件に加え「一生捧げてもいいと思えるほど好きなものがあるか」「あなたのファンをつくれるか」などの4条件をクリアしないといけない。

宮崎哲弥を久々に見た。やや肥った?
自分のタイプを見定めたら、1%の人間(100人に1人の人間)になるために努力しなければならない。藤原氏の言葉を借りると(東洋経済ONLINE)、
1つの分野を極めて頂点に立つには、熾烈な競争に勝たないといけないんです。たとえば、オリンピックのメダリストになるのはだいたい「100万人に1人」。ノーベル賞を受賞するのは「1000万人に1人」です。普通の人はどんなに努力しても難しいですよね。
でも、「100人に1人」なら努力すれば誰でもなれる。だから、1つの分野でまず「100人に1人」になって、そうしたらそのまま突き進むのではなくて、横にスライドして別の分野で「100人に1人」になる。また横にスライドして別の分野で「100人に1人」になる。そうすれば、「100人に1人」×「100人に1人」×「100人に1人」=「100万人に1人」と、オリンピックのメダリスト級のレアな人になれるというわけです。
 | 本を読む人だけが手にするもの |
| 藤原和博 | |
| 日本実業出版社 |
あなたがベテランのツアーコンダクターだとする。これは100人に1人(1%)程度のことだろう。そこにブリーダーや盲導犬訓練士にチャレンジして100人に1人の犬のプロになる。すると1%×1%=0.01%の人、つまり1万人に1人のレアな人材になり、「犬連れツアコン」という新ビジネスを立ち上げることができる、ということになる。

話が脱線してしまったが、つまるところ「よのなか科」とは([よのなか科]ネットワーク)、
藤原和博氏が提唱している「学校で教えられる知識と実際の世の中との架け橋になる授業」のこと。教科書を使った受身の授業とは異なり、自分の身近な視点から世界の仕組み、世の中の仕組みなど、 大人でも簡単に答えを出せないテーマ(「ハンバーガー1個から世界が見える」、「模擬子ども区議会」、 「少年法の審判廷ロールプレイング」など経済・政治・現代社会の諸問題)を扱う。授業の特徴として藤原氏は以下の特徴を挙げている。
(1)ロールプレイやシミュレーションなどゲーム的手法によって子ども達の主体的な学びを創造する。
(2)大人も授業に参加することで、ともに学び合う力を付ける。
(3)カリキュラムの目的に沿ったゲストを迎え、生徒の思考回路を刺激し、ときに通常の授業では得られない種類の知的な感動を与える。
ということで、これは斬新かつ効果的な試みである。一条高校の今後の取り組みに、大いに注目したい。