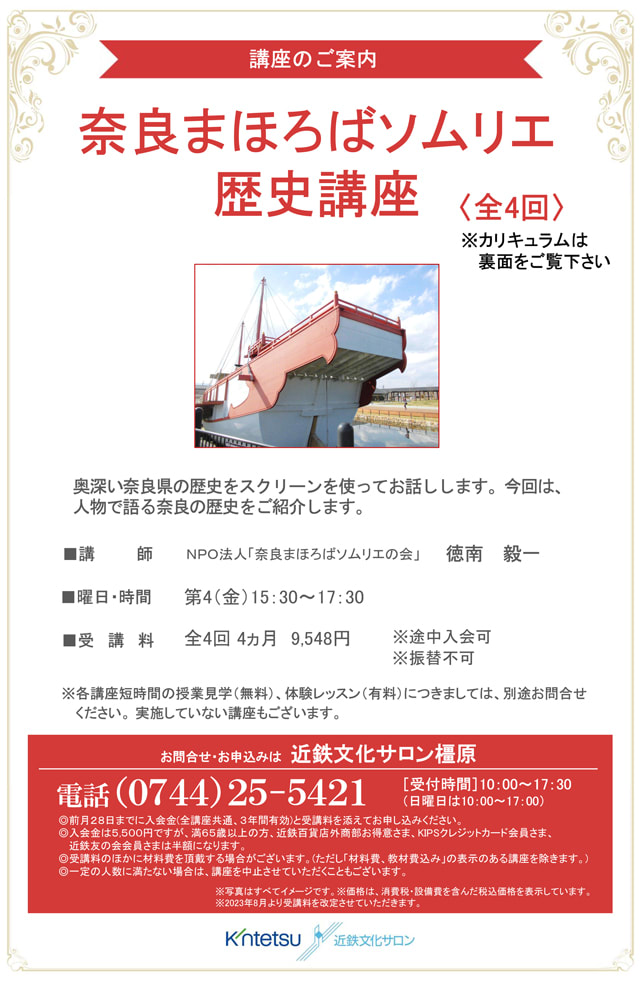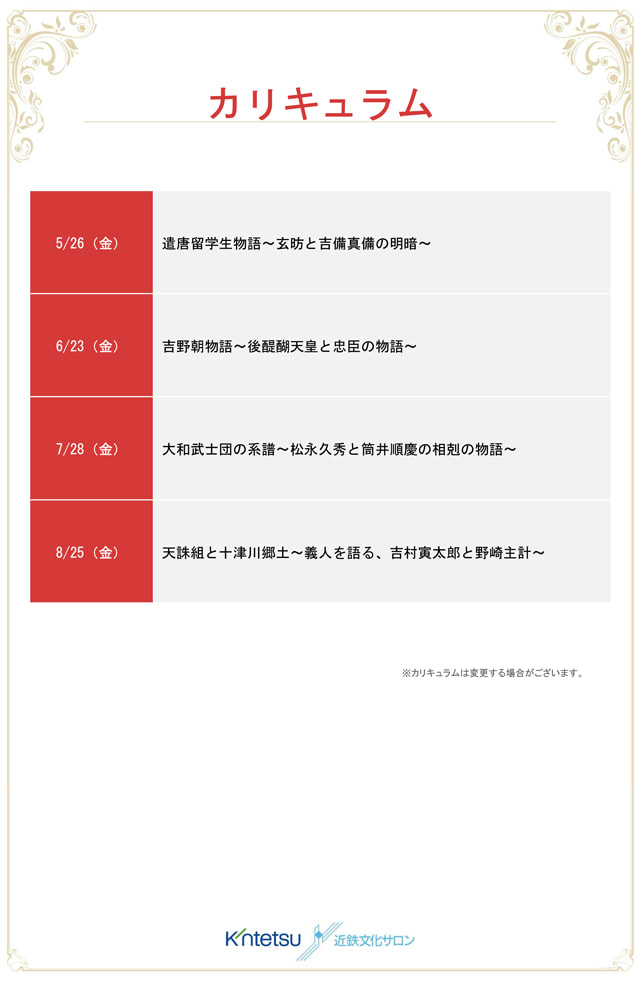ウクライナのゼレンスキー大統領を迎え、広島市で開催されている「主要7ヵ国首脳会議」(G7サミット)最終日である今日(5/21)の「田中利典師曰く」では、「白光真宏会・富士聖地 SOPP 平和の祈りに参加!!」(師のブログ2011.5.24付)を紹介する。
※トップ写真は、吉野水分(みくまり)神社の桜(2023.3.31撮影)
白光真宏会(びゃっこうしんこうかい)は富士宮市に本拠を置く宗教団体で、祈りによる世界平和を提唱している。よくお寺や神社の境内で「世界人類が平和でありますように May Peace Prevail on Earth」というポール(ピースポール)を見かけるが、あれもこの団体の活動の一環である。
利典師はSOPPに登壇、「修験道 平和の祈りのメッセージ」を披露された。なおSOPPは「Symphony of Peace Players〜世界平和交響曲宗教・宗派を超えて共に世界の平和を祈る~」というイベントで毎年1回、富士山が望める場所で開催されている。2011年のSOPPは、
仏教修験道、ヒンズー教、神道、ユダヤ教、キリスト教東方正教会、イスラム教スーフィズム、白光真宏会の代表者が、それぞれの歴史、背景を纏うような美しい正装姿で胸に響くスピーチをされ、平和の祈りを先導してくださった。法螺貝の風趣さ溢れる音色で仏教修験道の祈りが始まった。
とあるので利典師がトップバッターで、法螺貝の音色とともに登壇されたようだ。満を持してのメッセージである。今はロシアによるウクライナ侵攻が収まる気配を見せないなか、より切実に世界平和への祈りが求められている。では、全文を紹介する。英訳もあるので、それは末尾に貼っておく。
白光真宏会・富士聖地SOPP平和の祈りに参加!!
ご縁があって、白光真宏会が主催される・富士聖地SOPP平和の祈りの集いに仏教界からのメッセンジャーとして5月22日に出演させていただいてきた。SOPPは昨年のゲスト参加以来、2回目である。
お祈りは法螺師3名を伴って、世界遺産登録記念の際に、全国の修験教団で以て採択した「修験道平和の祈りのメッセージ」を読み上げ、般若心経を5000人余の参加者の前でお唱えした。
このSOPPにお誘いを受けて以来、いつかこのメッセージを披露したいと思っていたので、念願をかなえてのステージであった。参加者との大合唱によるお祈りは壮観な時空を体感させていただいた。以下、メッセージを紹介する。
********************:
修験道「平和の祈りのメッセージ」
”人が信じる、すべての仏に、神々に、合掌”
私たち人間は、地球の住人です。その地球、そして大宇宙の森羅万象の中で、私たち人間は特別に優れているとか、劣っているとか、そういうことはありません。あらゆる命、あらゆる存在が、全て等しくこの世にあります。
しかし、人間はその真理を忘れ、今に至りました。欲望を満たすことだけが生きる意味ととりちがえ、森羅万象をないがしろにする。
人間同士、些細な理由で互いをわけへだて、差別する。宗教、人種、歴史、文化…。互いの価値観のちがいを、ことさらにあげつらい、蔑み、妬み、争い、ときには殺し合う。なんとあさはかなことでしょう。
歯止めのきかない自然環境破壊、頻発するテロや戦争、すべてが、その結果です。今、人間はみずから播いた災いの種に苦しめられています。そして、この苦しみは、私たちの子や孫の世代まで、そのもっと、ずっと先の世代まで続くのです。
「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」とユネスコ憲章の中にあります。禍の根源にあるのは、私たち一人ひとりの心です。見えざる大きな力が働いているわけではありません。この心を正すことなくして、地球に平穏は訪れません。
世界自然憲章の前文は「人間は自然の一部である」と語ります。「自然は人間を癒す」とも語ります。人間は、自然との深い関わりなしに、その歪んだ心を正すことはできないのです。
山に伏し、野に伏し、自然を、そこに坐す神仏を祈る修験道は、そうした人間の心に巣食う罪、過ちを戒め、五体を通した修行の中で、清め、再生することを実践してきました。大自然の霊気に接することで、山を、木々を、一切の存在、命を敬い、感謝する心を育んできました。また釈尊は「すべての生きとし生きるものよ幸いあれ」と述べました。
人と人は、過去にとらわれず、互いを思いやる。すべてを咎めず、許す。その精神は「恕(じょ)」の一文字に集約されます。私たちは、第7回SOPP世界平和交響曲・平和の祈りの集いに際し、日本独特の宗教である修験道から、この「恕」の心を、世界に、未来に発信します。
そして、地球上の山川草木、さらには大宇宙のありとしある全存在とともに、宗教、人種、歴史、文化の違いを超え、すべての人間に、森羅万象の一切に、「地球平穏・世界平和」への祈りを捧げ続けることを宣言します。 金峯山寺 田中利典
*******************
ちなみに真宏会の通訳はおられたが、法螺師で同行した弟子も英語が堪能なので、鈴掛姿で、英訳を朗読させた。素晴らしいお祈りの一日だった。
追伸 帰りの新幹線で、静岡駅財布置き去り事件を起こしたが、無事、届けられることになった。とても大きな御利益をいただいた気がする。(^^;)
MESSAGE of PRAYER for WORLD PEACE
“Prayer for World Peace to the Buddha and Deities We Believe in”
We human beings are inhabitants on this Earth.
On Earth, and in all creation, we human beings are neither above nor below other beings. All beings and all lives exist equally in this world.
However, we human beings have forgotten this truth, mistakenly thinking that life is only about fulfilling our desires. As a result, we have turned our backs on the world of nature.
We gain wealth and abundance by looking down on and doing harm to beings whose lives are equally precious.
We discriminate against people based on their religion, race, history, culture, and other trivial matters, leading us to despise, oppress, and humiliate others, and even to kill.
As a result, we have brought about ceaseless environmental destruction and repeated acts of terror and war. These seeds of destruction that we have sown will continue into future generations, so that we are taking the future away from our children and grandchildren.
In the UNESCO Constitution, it is written: “…since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.” This is indeed the truth. The cause of war is not in some great invisible force, but in the heart of each individual.
Furthermore, in the UN World Charter for Nature, it is written: “Mankind is a part of Nature”.
Unless we can humbly examine our deep connection with nature, we will be unable to set our crooked minds straight.
In Shugendô, ascetic training takes place in the mountains and fields, with prayers to Buddha, the Deities, and the world of nature. Our aim is to guard against the mistakes and wrongdoings which lodge themselves in our minds, to purify ourselves through physical and spiritual ascetic practices, and thus to be born anew.
By contacting with the spirits of great nature, Shugendô has helped to cultivate respect and appreciation for mountains, trees, all life and everything in creation.
Shakyamuni Buddha left us this message: “May all living things be happy.”
Consideration for one another without regard for the past; forgiveness without blame.
This spirit—the way human beings should be—is summed up in the Japanese character jo (恕), meaning ‘tolerance and forgiveness.’
On the occasion of the 7th annual Symphony of Peace Prayers, we of the Shugend – a faith, which is unique to Japan, send the spirit of Jo out to the world and to the future.
We continue to offer prayers for ‘Peace on Earth and Peace in the World,’ with respect and gratitude for all human beings—transcending all differences of religion, race, history, and culture—for mountains, rivers, grasses, trees, and all of nature, and for the entire universe and everything in creation.
※トップ写真は、吉野水分(みくまり)神社の桜(2023.3.31撮影)
白光真宏会(びゃっこうしんこうかい)は富士宮市に本拠を置く宗教団体で、祈りによる世界平和を提唱している。よくお寺や神社の境内で「世界人類が平和でありますように May Peace Prevail on Earth」というポール(ピースポール)を見かけるが、あれもこの団体の活動の一環である。
利典師はSOPPに登壇、「修験道 平和の祈りのメッセージ」を披露された。なおSOPPは「Symphony of Peace Players〜世界平和交響曲宗教・宗派を超えて共に世界の平和を祈る~」というイベントで毎年1回、富士山が望める場所で開催されている。2011年のSOPPは、
仏教修験道、ヒンズー教、神道、ユダヤ教、キリスト教東方正教会、イスラム教スーフィズム、白光真宏会の代表者が、それぞれの歴史、背景を纏うような美しい正装姿で胸に響くスピーチをされ、平和の祈りを先導してくださった。法螺貝の風趣さ溢れる音色で仏教修験道の祈りが始まった。
とあるので利典師がトップバッターで、法螺貝の音色とともに登壇されたようだ。満を持してのメッセージである。今はロシアによるウクライナ侵攻が収まる気配を見せないなか、より切実に世界平和への祈りが求められている。では、全文を紹介する。英訳もあるので、それは末尾に貼っておく。
白光真宏会・富士聖地SOPP平和の祈りに参加!!
ご縁があって、白光真宏会が主催される・富士聖地SOPP平和の祈りの集いに仏教界からのメッセンジャーとして5月22日に出演させていただいてきた。SOPPは昨年のゲスト参加以来、2回目である。
お祈りは法螺師3名を伴って、世界遺産登録記念の際に、全国の修験教団で以て採択した「修験道平和の祈りのメッセージ」を読み上げ、般若心経を5000人余の参加者の前でお唱えした。
このSOPPにお誘いを受けて以来、いつかこのメッセージを披露したいと思っていたので、念願をかなえてのステージであった。参加者との大合唱によるお祈りは壮観な時空を体感させていただいた。以下、メッセージを紹介する。
********************:
修験道「平和の祈りのメッセージ」
”人が信じる、すべての仏に、神々に、合掌”
私たち人間は、地球の住人です。その地球、そして大宇宙の森羅万象の中で、私たち人間は特別に優れているとか、劣っているとか、そういうことはありません。あらゆる命、あらゆる存在が、全て等しくこの世にあります。
しかし、人間はその真理を忘れ、今に至りました。欲望を満たすことだけが生きる意味ととりちがえ、森羅万象をないがしろにする。
人間同士、些細な理由で互いをわけへだて、差別する。宗教、人種、歴史、文化…。互いの価値観のちがいを、ことさらにあげつらい、蔑み、妬み、争い、ときには殺し合う。なんとあさはかなことでしょう。
歯止めのきかない自然環境破壊、頻発するテロや戦争、すべてが、その結果です。今、人間はみずから播いた災いの種に苦しめられています。そして、この苦しみは、私たちの子や孫の世代まで、そのもっと、ずっと先の世代まで続くのです。
「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」とユネスコ憲章の中にあります。禍の根源にあるのは、私たち一人ひとりの心です。見えざる大きな力が働いているわけではありません。この心を正すことなくして、地球に平穏は訪れません。
世界自然憲章の前文は「人間は自然の一部である」と語ります。「自然は人間を癒す」とも語ります。人間は、自然との深い関わりなしに、その歪んだ心を正すことはできないのです。
山に伏し、野に伏し、自然を、そこに坐す神仏を祈る修験道は、そうした人間の心に巣食う罪、過ちを戒め、五体を通した修行の中で、清め、再生することを実践してきました。大自然の霊気に接することで、山を、木々を、一切の存在、命を敬い、感謝する心を育んできました。また釈尊は「すべての生きとし生きるものよ幸いあれ」と述べました。
人と人は、過去にとらわれず、互いを思いやる。すべてを咎めず、許す。その精神は「恕(じょ)」の一文字に集約されます。私たちは、第7回SOPP世界平和交響曲・平和の祈りの集いに際し、日本独特の宗教である修験道から、この「恕」の心を、世界に、未来に発信します。
そして、地球上の山川草木、さらには大宇宙のありとしある全存在とともに、宗教、人種、歴史、文化の違いを超え、すべての人間に、森羅万象の一切に、「地球平穏・世界平和」への祈りを捧げ続けることを宣言します。 金峯山寺 田中利典
*******************
ちなみに真宏会の通訳はおられたが、法螺師で同行した弟子も英語が堪能なので、鈴掛姿で、英訳を朗読させた。素晴らしいお祈りの一日だった。
追伸 帰りの新幹線で、静岡駅財布置き去り事件を起こしたが、無事、届けられることになった。とても大きな御利益をいただいた気がする。(^^;)
MESSAGE of PRAYER for WORLD PEACE
“Prayer for World Peace to the Buddha and Deities We Believe in”
We human beings are inhabitants on this Earth.
On Earth, and in all creation, we human beings are neither above nor below other beings. All beings and all lives exist equally in this world.
However, we human beings have forgotten this truth, mistakenly thinking that life is only about fulfilling our desires. As a result, we have turned our backs on the world of nature.
We gain wealth and abundance by looking down on and doing harm to beings whose lives are equally precious.
We discriminate against people based on their religion, race, history, culture, and other trivial matters, leading us to despise, oppress, and humiliate others, and even to kill.
As a result, we have brought about ceaseless environmental destruction and repeated acts of terror and war. These seeds of destruction that we have sown will continue into future generations, so that we are taking the future away from our children and grandchildren.
In the UNESCO Constitution, it is written: “…since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.” This is indeed the truth. The cause of war is not in some great invisible force, but in the heart of each individual.
Furthermore, in the UN World Charter for Nature, it is written: “Mankind is a part of Nature”.
Unless we can humbly examine our deep connection with nature, we will be unable to set our crooked minds straight.
In Shugendô, ascetic training takes place in the mountains and fields, with prayers to Buddha, the Deities, and the world of nature. Our aim is to guard against the mistakes and wrongdoings which lodge themselves in our minds, to purify ourselves through physical and spiritual ascetic practices, and thus to be born anew.
By contacting with the spirits of great nature, Shugendô has helped to cultivate respect and appreciation for mountains, trees, all life and everything in creation.
Shakyamuni Buddha left us this message: “May all living things be happy.”
Consideration for one another without regard for the past; forgiveness without blame.
This spirit—the way human beings should be—is summed up in the Japanese character jo (恕), meaning ‘tolerance and forgiveness.’
On the occasion of the 7th annual Symphony of Peace Prayers, we of the Shugend – a faith, which is unique to Japan, send the spirit of Jo out to the world and to the future.
We continue to offer prayers for ‘Peace on Earth and Peace in the World,’ with respect and gratitude for all human beings—transcending all differences of religion, race, history, and culture—for mountains, rivers, grasses, trees, and all of nature, and for the entire universe and everything in creation.