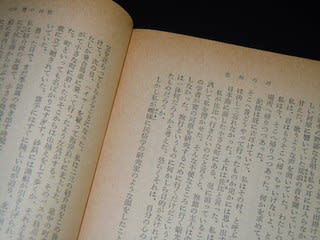
■ 福永武彦の『忘却の河』。今日、何回目かの再読を終えた。
**それは裏山の中腹にあったの墓地に較べても、あまりに見すぼらしい石の群落にすぎなかった。名前を刻み込んだ石碑などは一つもなかった。僅かに朽ち果てた卒塔婆が幾つか倒れかかっていることによって、この一廓が墓地であることを示していた。(中略) そして私の恋人が眠っているところも、まさにこの無縁墓地のほかにはなかった。どこの誰とも分からぬ男のために子を宿し、一家の恥として西が浦に身を投げた娘の葬られるべき場所は、名誉ある出征兵士の骨を埋めた山の墓地ではなく、この海沿いの、荒涼の飛沫(しぶき)が散りかかる無縁墓地のほかにはなかった。**(復刊版324頁)
**ここが地の果て、生のどん詰まりなのだ。更に言えば、ここにあるものは決して済われることのない罪そのものの感じなのだ。眼の前には轟く海がある。何の感情の見せない冷たい石の河原がある。(中略)この賽の河原は、あらゆる罪障の捨て場所としてあったのではないだろうか。私が今ここへ過去の罪を捨てに来たように。**(同323頁)
心の底を流れる河。この世に生を受けてからしだいに穢れ、淀む河。河の源流をたどる男の孤独な旅路。この小説を読むことは男の旅にそっと同行することに他ならない。
作者には恋人の子どもを宿して故郷に帰り、海に身を投げた女性の手記を残して欲しかったと思う。たぶん涙なくして読むことはできないだろう・・・。
初読から30年。またいつか読むことになるだろう。
2954









