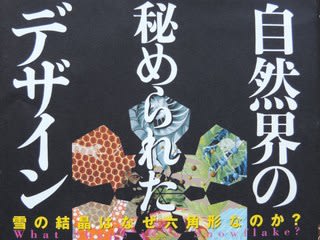■ 5月の読了本は3冊。

『集合知とは何か ネット時代の「知」のゆくえ』 西垣 通/中公新書
本書のあとがきからポイントを引用しておく。**二〇世紀は、専門家から天下ってくる知識が、「客観知」としてほぼ絶対的な権威をもった時代だった。(中略)
二一世紀には、専門知のみならず一般の人々の多様な「主観知」が、お互いに相対的な位置をたもって交流しつつ、ネットを介して一種のゆるやかな社会的秩序を形成していくのではないだろうか。それが二一世紀情報社会の、望ましいあり方ではないのだろうか。**
専門的で理解の及ばないところも少なくなかったが、二一世紀の知とはどうあるべきか論じた本書はなかなか興味深い内容だった。
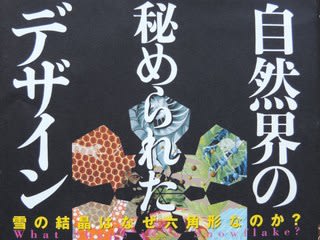
『自然界の秘められたデザイン 雪の結晶はなぜ六角形なのか?』イアン・スチュアート/河出書房新社
何年か前に読んでいる本。入院中に再読しようと持っていったが、病室で読むことはできなかった。麻酔の影響だと思うが、入院中頭痛が続いて安静にしていたから。で、退院後に読んだ。
自然のデザイナーは数学が好き。多種多様な形は数学的なルールに基づいてできている。
自然科学に関しては、海外の研究者の書いた本の方が総じて面白い。あることを説明するときの喩え話は巧みで分かりやすいし、専門以外のことに関する話題も豊富だと思う。専門領域に限定された説明より、読んでいて楽しい。この本には建築家のバックミンスター・フラーが考えたジオデシックドームがでてくる。話題は広く内容は深い。

『ときめき昆虫学』 メレ山メレ子/イースト・プレス
この本の著者、メレ山メレ子さんのことは今まで全く知らなかった・・・。硬軟織り交ぜた文章で綴る虫のはなし、虫好きの人たちとの楽しい交流。
**造網性のクモが網から外され、棒の上にとまらされて同族と戦うというのは、人間でいうとオフィスで内勤していたらUFOによって緑色の光で吸い上げられ、気がついたら火星でタコ型宇宙人から「星々に火星ゴルフ会員権を売りこんできてクダサイ。トップ営業になるまでは地球に帰れマセン」と言われるくらいハードモードだ。**(59頁)
以上クモの章から硬軟の「軟」の文章の引用。これは鹿児島県始良市加治木で毎年行われているクモ合戦観戦記。
**ホタルの光り方には(中略)産地ごとにわずかな差があるという。違う地域の異なる言語でコミュニケーションを取っているホタルを人為的に混ぜると、オスメスの交信まで混乱するので、結果的に共倒れとなってしまう可能性があるのだ。地域的絶滅に至らないまでも、人為的な移入による遺伝子汚染を問題視する生物学者も多い。**(74頁)
以上ホタルの章から、硬軟の「硬」の文章の引用。
この本を読めば虫スイッチON間違いなし。そしてメレ子さんにもときめいてしまうかも。
メレ山メレ子さんのブログ ← どの記事もユーモラスに綴られている。旅行記は特におもしろい。