■ 映画「GATTACA ダカタ」を観た。SF映画ということだが、SFというより、ヒューマンドラマと言った方が内容的にふさわしい。映像的には建築シーンなどに近未来的な雰囲気も。
遺伝子の優劣で人生が決まってしまう近未来の差別的社会。遺伝子操作によってマイナス要素を無くして完璧な状態で生まれてくる「適格者」、自然な妊娠、出産によって生まれくる「不適格者」。
適格者でないとなることができない宇宙飛行士。幼いころから宇宙飛行士になりたいと思い続けていた不適格者の若者・ヴィンセントが、適格者として生まれながら、事故、いや自殺未遂で車いす生活を余儀なくされた若者・ジェロームの協力のもと、「ガタカ」の局員になる。この組織はNASAのようなものか。
ヴィンセントが何回も実施された血液検査や尿検査を巧妙に通過し、ピンチも切り抜けて木星の衛星タイタンを目指してロケットで旅立つまでを描いている。
ロケット搭乗直前の尿検査で分かる「不適格者」という結果を見逃してくれる医師、ジェロームがヴィンセントに託した手紙の中身・・・。
この映画に込められたメッセージは、自分で限界の線引きをしないで、目標に向かって努力することが大切だ、ということか。「何ができて何ができないか決めつけるな」というセリフもでてくる。協力者だって必ずいる。ただし真っ当な努力だけでは報われないこともあるということも同時に示していると理解すべきかもしれない。
これで自らに課した夏休みの宿題の内、読書3冊と映画3本はクリアした。残るは火の見櫓のある風景のスケッチ3点。




















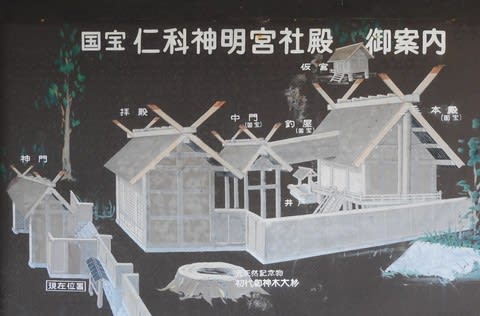













 ①
① ②
② ③
③











