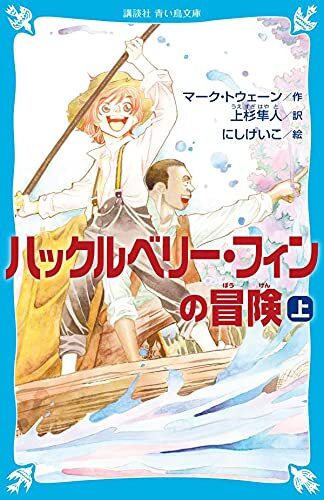make believe (that)...で、「~であるふりをする、~と見せかける」。
今日のGetUpEnglishはこの表現を学習する。
○Practical Example
"She got my money by making believe she loved me."
「あの女、わたしを愛していると見せかけて、私のお金を奪った」
●Extra Point
「(~の)真似ごとをする、(~)ごっこをする」の意味でも使われる。
◎Extra Example
"Let's make believe we're pirates, Thor."
「海賊ごっこをしようよ、ソー」
☆Extra Extra Point
make-believeとハイフンが付くと名詞(「見せかけ、偽り」「架空」)や形容詞(「見せかけの、偽りの」「架空の、想像上の」といった意味で使われる。
Oxford Advanced Learner's Dictionaryには、次の定義がある。
imagining or pretending things to be different or more exciting than they really are
そしてFANTASYの同義語であると定義されている。
現在、翻訳中の本に、以下の表現があった。
Poster Art of the Disney Parks, Second Edition
by: Danny Handke, Vanessa Hunt
https://books.disney.com/book/poster-art-of-the-disney-parks-second-edition/
★Extra Extra Example
“Here is the world of imagination, hopes, and dreams. In this timeless land of enchantment, the age of chivalry, magic, and make believe are reborn—and fairy tales come true. Fantasyland is dedicated to the young and the young at heart, to those who believe that when you wish upon a star, your dreams come true.”
—Walt Disney
ここはイマジネーションと希望と夢の世界。 この永遠の魔法の国で、騎士道や魔法や夢想の時代が再現され、おとぎ話が現実になる。ファンタジーランドは子供たちちと子供の心を持つ人たち、星に願えば夢がかなうと信じる人たちのための場所。
――ウォルト・ディズニー
make believeはmake-believeだが、①A, B and Cのように羅列される場合にAもBもCも大体同じ意味であるはずである、そして②fantasy(ファンタジー、空想)と同義であると考えれば、「架空」を「夢想」くらいに訳せばいいだろう。
for one's moneyは、「 …に関する限りでは[に言わせれば]、…の考えでは」の意味で使われる。
今日のGetUpEnglishはこの表現を学習する。
○Practical Example
"If you're looking for someone you can completely trust, Mr. Sasaki is the man for my money."
「全面的に信頼できる人物をお探しなら、笹木さんこそうってつけの男だと思いますよ」
●Extra Point
今年いちばん気合を入れて、毎日コツコツ訳している本に、この表現があった。
◎Extra Example
"And then, despite all that success, he wrote his fourth novel, The Great Gatsby, which for my money was the best one written in English in the 20th century."
「フィッツジェラルドはそれだけの成功を収めていたが、四作目の小説『グレート・ギャツビー』(××ページ)を書いた。『グレート・ギャツビー』は、わたしが思うに、英語で書かれた二十世紀最高の小説だ」
韓国の人気グループBTSの最年長メンバーのジンさんが、兵役で韓国軍に入隊した。ほかの6人のメンバーも順次、兵役に就く予定で、グループ地しての活動はきしばらく休止する。
https://www.asahi.com/ajw/articles/14791544
今日のGetUpEnglishは以下の文にある表現を見てみよう。
Six other younger BTS members are to join the military in coming years one after another, meaning that South Korea’s most successful music band must take a hiatus, likely for a few years.
まずhiatusは「すき間、とぎれ」「休憩時間」。ほぼ10年前のGetUpEnglishでも学習した。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/84069043c90bd28b1978d257cbb03f8c
Asahi Weekly, January 1-8もこの記事を取り上げて、この文に出てきたmustをhave toと比べて説明している。
https://www.asahi.com/english/weekly/20230101/
-----------------------
mustはhave toと同様に「強制」を表します。前者は話し手によって課された義務(主観的強制)を表し、後者は外部の事情によって課された義務(客観的強制)について使う傾向があります。この区別は英国英語で顕著です。
例)You must come to class on time.(授業に遅れてはならない:教師の生徒への命令)
I have to stay home today.(今日は家にいなければならない:外部の要因から在宅していなければならない)
ただし、厳密に守られているわけではなく、mustのほうがはるかに改まった感じで堅い表現なので、日常会話では柔らかい感じのhave toが断然好まれます。
------------------------
とてもよくまとまった説明だ。
Asahi Weeklyは英語のニュースがたくさん読める上に、詳細な注がついていて、文法説明まで充実している。
ぜひすべての英語学習者にお勧めしたい。
またデイビッド・セイン、古正佳緒里『ネイティブが教える ほんとうの英語の助動詞の使い方』(研究社)にもあるように、need toもよく使われる。
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-45260-5.html
■「義務・必要」を表わすmust
「…しなくちゃ」くらいの「軽い義務」を表わすのであれば、今述べたよう
に、must ではなくneed to(…しなくてはいけない)を使うのが自然です。
need to は、客観的な理由から何かをしなくてはいけない時に使う語で、「(外
的な理由により)…する必要がある」というニュアンスになります。そのため、
仕事などの外的な理由で何かをしなければならない時は、普通need to を使
います。
こちらも併せて読んでおこう。
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-45260-5.html
仕事があるというのはありがたいことだ。わたしの場合は本業の合間に翻訳ほかの仕事をするので、年末年始はずっと机に張りついていた。
ただ、英語力、知識の向上は常にはかりたいし、あらゆる本をなるべく読んだり、Audibleで聴いたりしている。
今読んでいる本に、この以下の表現があった。
本日のGetUpEnglishで紹介する。
There are seven billion people alive now, roughly, and 107 billion who have lived and are now dead. We, the living, are in the minority. And it’s this majority, the dead, who outnumber us 15-1, and whose under-representation in most people’s reading habits I want to talk about.
Reading books by dead people is absolutely, numero uno, without any doubt, by a million miles the very best thing you can do to guarantee success in your education, and, I’d argue, your life. Why?
現在の地球上には約七十億の人がいるが、これまでに生まれ、没した人の数は一〇七〇億だ。現存する者のほうがずっと少ない。現在生きているわたしたちの人数に対し、すでに没した人たちの数は十五倍にもなる。すでに没している作家たちの作品は現存する作家の十五倍読まれているかと言えば、そうではなく、ここでこのことについて論じてみたい。
すでに亡き人たちの本を読むことで、学びにおいて、そして人生において、正真正銘最大の効果がもたらされると疑いなく言える。わたしはそう考えるが、なぜか?
numero unoはイタリア語から入ってきた言い方で、「第一人者、トップ、最高のもの、第一のもの」
by a million milesは、by miles [a mile] が「大きく、大幅に、ずっと、断然」、それをa million(すばらしい、みごとな、最高の、すごい)で強調した言い方。
よって、
Reading books by dead people is absolutely, numero uno, without any doubt, by a million miles the very best thing you can do to guarantee success in your education, and, I’d argue, your life. Why?
は、
「すでに亡き人たちが残した本を読むことで、学びにおいて、そして人生において、正真正銘唯一絶対最大限の効果がもたらされると疑いなく言える。わたしはそう考えるが、なぜか?」
くらいに訳せばよい。