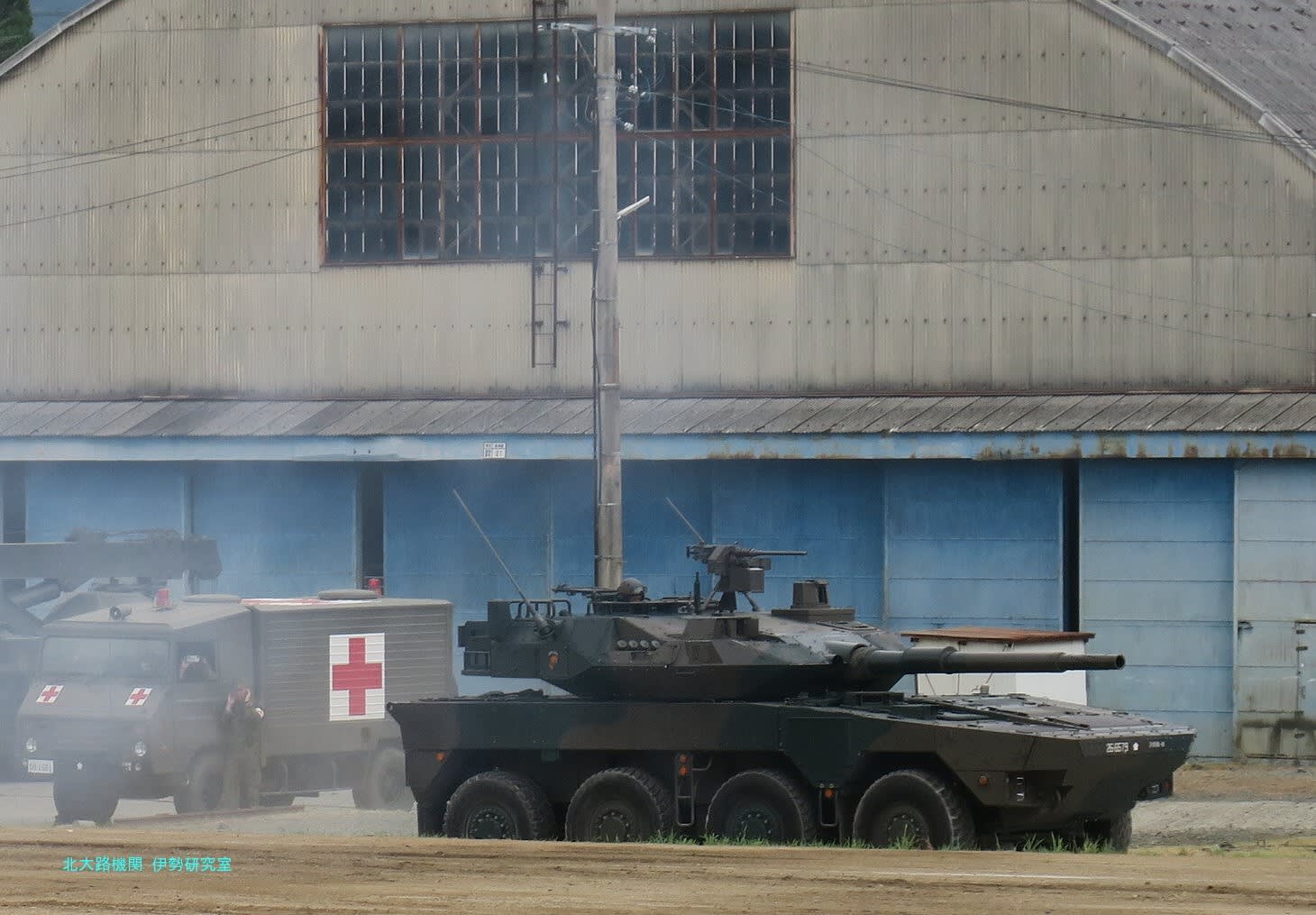■建造8年-しらね型より大型
フリゲイトバーデンヴュルテンベルクは。

バーデンヴュルテンベルク級フリゲイト、ドイツ海軍というのは戦艦ビスマルクなど第三帝国時代に在っても大きな艦艇を建造したものの、ジュットランド海戦のような大規模な戦闘を展開する能力を逸したまま、第二次大戦とその後の冷戦時代を迎えました。

ビスマルクなどは強力な戦艦という印象はあり、実際、イギリス海軍最大の戦艦であるフッドを撃沈した事で、処女航海である通商破壊作戦の際に撃沈されたものの、二番艦テルピッツなどは重大な脅威であるとして認識されていましたが。

3000t以上の水上戦闘艦の建造を禁止する。第二次世界大戦後、強力なドイツ海軍の復活を阻止するという、フランス政府とソ連政府の強い要求があり、また欧州に反対する国もなかったことからドイツ海軍には大型水上戦闘艦の建造が禁止されています。

リュッチェンス級ミサイル駆逐艦として例外的に大型艦の建造が認められたのは1969年の話であり、もっとも海上自衛隊もこの大きさの規模となりますと、1965年の護衛艦あまつかぜ竣工まで時間があったのですが、制約があったのでした。

冷戦時代一杯、ドイツ海軍に求められたのは有事の際のバルト海のソ連海軍行動阻止、これはミサイル艇や小型潜水艦が重要であると認識されておるのですが、そしてNATOへ補給物資を輸送する北大西洋におけるシーレーン防衛の支援が任務でした。

冷戦後、テロとの戦いや地域紛争の時代を迎えますと、欧州最大の経済大国となったドイツは、最早軍事力を自国防衛だけに集約し欧州全体の安全保障に不関与であることが認められる環境は無く、ここで水上戦闘艦の大型化が加速するわけです。

ザクセン級フリゲイトとしまして、2004年から満載排水量5690tの水上戦闘艦を建造するのですが、しかしこれとて、海上自衛隊の護衛艦むらさめ型よりも若干小型であり、世界規模の任務に対応するには大きさが過小であると評価されたものでした。

バーデンヴュルテンベルク級フリゲイトは満載排水量7316t、かなり大型化しまして、自衛隊のイージス艦ほどではありませんが、はるな型ヘリコプター搭載護衛艦の6800tや、しらね型ヘリコプター搭載護衛艦の7200tよりも大型、行動力が増大します。

世界規模の作戦運用を検討し、基地を出航し補給するだけの連続展開期間を連続2年、年間5000時間即ち208日間の作戦可動が可能、ドックに入居しての整備間隔は5年に1回、乗員交代を 4ヶ月ごととして艦艇は外地に置き乗員だけ交代させる性能が。

ドイツ海軍はこれで世界の海に戻ることができる、という希望と共に設計されたのですが、進水式の際に子供に艦が傾いていると指摘され、実際、建造するとともに重心の設計ミスと復元性の問題が指摘され、連邦海軍に受け取りを拒否されるという事態に。

モジュール方式で様々な装備品を搭載できるという利点が強調されていたものの、結局重心と復元性の問題から全く対潜装備を搭載しないという特色や、戦闘システムの開発遅延などから起工式から数えて8年間、進水式から竣工まで6年を要しました。

軍艦建造のノウハウは一朝一夕には完成させられない、いったん失うとその再現には非常に時間を要する、という事を端的に示したような事例でして。しかし日本までやってこれるようになったのか、と感慨深く迎えた東京港での一日でした。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
フリゲイトバーデンヴュルテンベルクは。

バーデンヴュルテンベルク級フリゲイト、ドイツ海軍というのは戦艦ビスマルクなど第三帝国時代に在っても大きな艦艇を建造したものの、ジュットランド海戦のような大規模な戦闘を展開する能力を逸したまま、第二次大戦とその後の冷戦時代を迎えました。

ビスマルクなどは強力な戦艦という印象はあり、実際、イギリス海軍最大の戦艦であるフッドを撃沈した事で、処女航海である通商破壊作戦の際に撃沈されたものの、二番艦テルピッツなどは重大な脅威であるとして認識されていましたが。

3000t以上の水上戦闘艦の建造を禁止する。第二次世界大戦後、強力なドイツ海軍の復活を阻止するという、フランス政府とソ連政府の強い要求があり、また欧州に反対する国もなかったことからドイツ海軍には大型水上戦闘艦の建造が禁止されています。

リュッチェンス級ミサイル駆逐艦として例外的に大型艦の建造が認められたのは1969年の話であり、もっとも海上自衛隊もこの大きさの規模となりますと、1965年の護衛艦あまつかぜ竣工まで時間があったのですが、制約があったのでした。

冷戦時代一杯、ドイツ海軍に求められたのは有事の際のバルト海のソ連海軍行動阻止、これはミサイル艇や小型潜水艦が重要であると認識されておるのですが、そしてNATOへ補給物資を輸送する北大西洋におけるシーレーン防衛の支援が任務でした。

冷戦後、テロとの戦いや地域紛争の時代を迎えますと、欧州最大の経済大国となったドイツは、最早軍事力を自国防衛だけに集約し欧州全体の安全保障に不関与であることが認められる環境は無く、ここで水上戦闘艦の大型化が加速するわけです。

ザクセン級フリゲイトとしまして、2004年から満載排水量5690tの水上戦闘艦を建造するのですが、しかしこれとて、海上自衛隊の護衛艦むらさめ型よりも若干小型であり、世界規模の任務に対応するには大きさが過小であると評価されたものでした。

バーデンヴュルテンベルク級フリゲイトは満載排水量7316t、かなり大型化しまして、自衛隊のイージス艦ほどではありませんが、はるな型ヘリコプター搭載護衛艦の6800tや、しらね型ヘリコプター搭載護衛艦の7200tよりも大型、行動力が増大します。

世界規模の作戦運用を検討し、基地を出航し補給するだけの連続展開期間を連続2年、年間5000時間即ち208日間の作戦可動が可能、ドックに入居しての整備間隔は5年に1回、乗員交代を 4ヶ月ごととして艦艇は外地に置き乗員だけ交代させる性能が。

ドイツ海軍はこれで世界の海に戻ることができる、という希望と共に設計されたのですが、進水式の際に子供に艦が傾いていると指摘され、実際、建造するとともに重心の設計ミスと復元性の問題が指摘され、連邦海軍に受け取りを拒否されるという事態に。

モジュール方式で様々な装備品を搭載できるという利点が強調されていたものの、結局重心と復元性の問題から全く対潜装備を搭載しないという特色や、戦闘システムの開発遅延などから起工式から数えて8年間、進水式から竣工まで6年を要しました。

軍艦建造のノウハウは一朝一夕には完成させられない、いったん失うとその再現には非常に時間を要する、という事を端的に示したような事例でして。しかし日本までやってこれるようになったのか、と感慨深く迎えた東京港での一日でした。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)