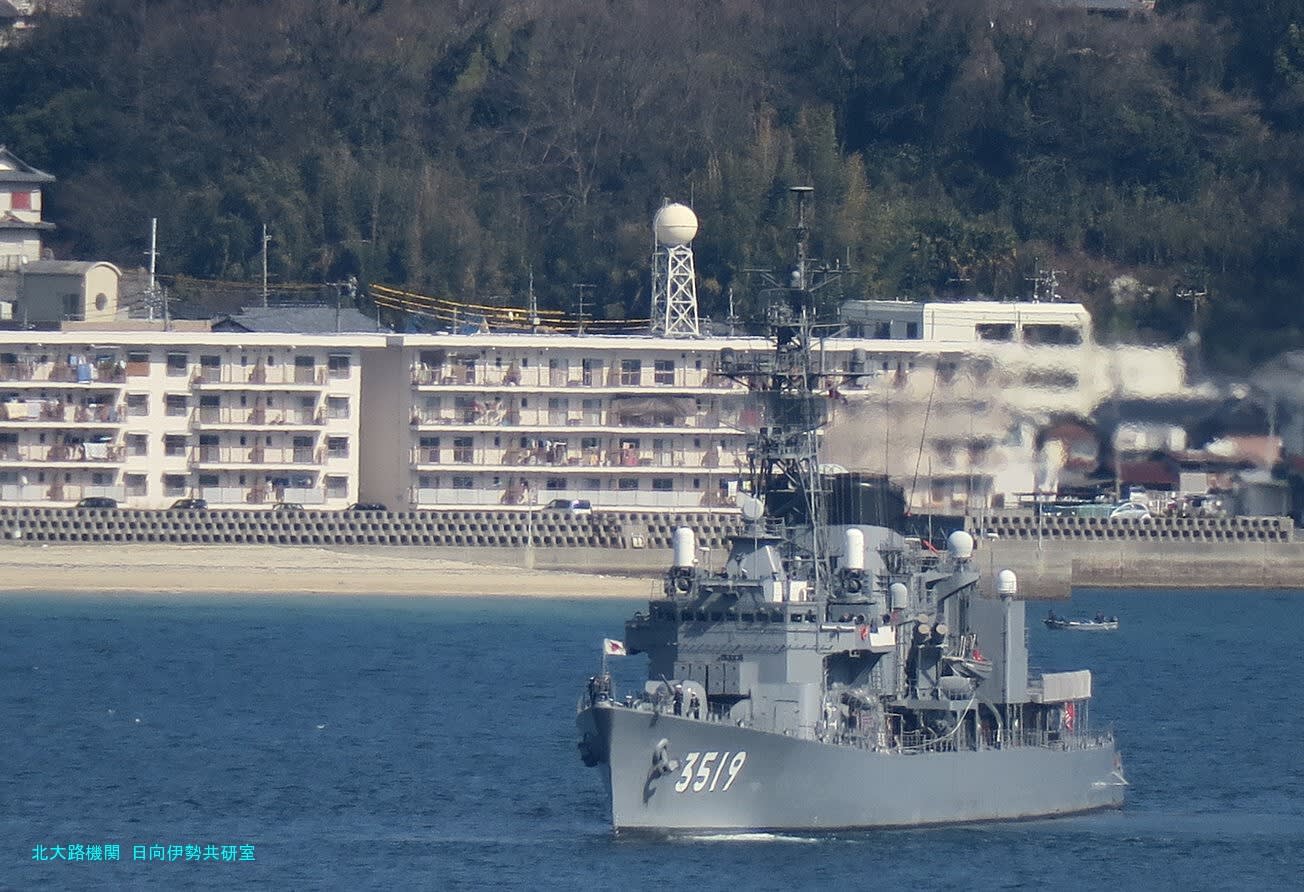■普通科,第15連隊と第50連隊
第14旅団記念式典観閲行進は前回の第15普通科連隊観閲行進に続き第50普通科連隊、そして第14偵察隊の観閲行進へと進みます。

善通寺駐屯地の歴史は1961年の第2教育団善通寺移駐から始まりました。1959年に大久保駐屯地にて創設された第2教育団は信太山第4陸曹教育隊、大久保第107教育大隊、信太山第108教育大隊、大津第109教育大隊、善通寺第110教育大隊、という編成でした。

大久保駐屯地は京都府宇治市、京都市内から地下鉄で一本の大久保です。実はこの大久保駐屯地、困ったときは大久保駐屯地、という程に草創期の自衛隊には重視されていた駐屯地で、一時は中部方面総監部にあたる管区総監部も大久保に置く、という話が合ったほど。

管区総監部を置くという背景には当時京阪神地区の旧軍施設は朝鮮戦争に伴う国連軍施設として最大限活用されており、活用されていないものは大蔵省管理、日本経済は朝鮮特需により戦後不況を脱するかに見えていたものの財政状況は最悪で、とても土地余裕が無い。

宇治市では、しかし大阪中心部には遠すぎるという事で、しかし国連軍接収が解かれた場所はそのまま大蔵省管理となる為、書類上管理が終了する前に実質的に撤収した大阪中心部の適地を自衛隊が先に確保する、という構図で幕僚がジープにて巡回したという逸話も。

大阪第二空港、戦前から残る大阪の小型機用ローカル空港とその周辺の空き地が旧軍により飛行場とされていましたが、朝鮮戦争と共に国連軍が大阪第一空港だけでは必要な空輸能力を満たせず、大阪第二空港を拡張使用していましたがその近くに空き地があるという。

大阪第二空港の近くとはいっても空地は兵庫県側に在るといい、元々旧軍時代には大阪城が陸軍第四師団司令部庁舎として使用された歴史を振り返れば、大阪第二空港は大阪中心部からは遠いものの、神戸大阪に近い利点も。大阪第二空港はまたの名を伊丹空港という。

管区総監部、中部方面総監部と1962年の師団改編により創設された第3師団は、伊丹空港近くの伊丹駐屯地と千僧駐屯地に総監部と司令部を置く事となり今日に至ります。続いて続々入隊する新隊員へ第2教育団が大久保に置かれたのですが、手狭である事は否めない。

第4施設団と、新たに普通科連隊を従来の普通科大隊に戦車中隊までを有する大型編成を改め中隊基幹の小型編成とする際に大久保駐屯地には新編第45普通科連隊も将来的に置かれる事となります、要するに次の部隊が待っているので先にできた部隊は動く必要が、と。

1961年に善通寺駐屯地へ第2教育団は移駐しました。四国は京阪神地区や山陽広島地区と中京地区等と人口ではそれほど大きくはありませんが、多くの新隊員が志願しており、四国にて前期教育を終えた隊員は緊張高まるソ連を睨み北海道防衛の第一線へと赴きました。

四国防衛は広島第13師団、現在の第13旅団の所管となっています。第13師団の警備隊区は非常に広く、山陽山陰四国9県、つまり、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、一つの方面隊に匹敵する師団警備隊区といえますね。

当時の第13師団は師団司令部以下、米子第8普通科連隊、善通寺第15普通科連隊、山口第17普通科連隊、第13特科連隊、第13戦車大隊、第13偵察隊、第13通信大隊、第13武器大隊、第13輸送大隊、第13補給大隊、第13衛生隊、第13音楽隊、という編成です。

広島海田市へ師団司令部を置く一方で山陽地区に普通科連隊が無いのは有事の際の即応に問題が、という事で1970年に海田市へ第46普通科連隊が新編され、普通科連隊四個を基幹とする定員9000名の甲師団となりました。しかし、管区が広すぎる事に代わりはない。

山陽山陰四国9県は実際に広大だったようで、これを象徴する師団の装備がありました。第13飛行隊の装備でL-19観測機、という航空機が陸上自衛隊で最後まで装備されていたのです。L-19観測機、1965年の大怪獣ガメラやバルジ大作戦で登場した古い観測機ですね。

飛行隊にL-19観測機、既に観測ヘリコプターとしてOH-55やOH-6の配備が進んでいた時代ですが、第13師団の当時の管区は広すぎまして、連絡飛行にOH-55では全く航続距離が足りなかった為、固定翼機としてL-19が残されていたという構図です。それ程に広い。

四国善通寺に第2混成団が新編されたのは1981年、1976年に制定されました初の防衛大綱には四国への作戦部隊配置が明記されていまして、1976年は我が国が石油危機に伴う高度経済成長の終焉、狂乱物価と景気後退に見舞われている中の四国混成団創設決定でした。

緊張緩和の時代ではありましたが、我が国防衛政策は画定に10年を要する為、これも現在の中国脅威への西方シフトというべき統合機動防衛力整備事業が本格化したのは中国海洋進出が本格化した十年後に当る頃ではありますが、緊張緩和時代に決定したという訳です。

新冷戦がソ連軍アフガン侵攻により始まったのが1979年でしたので、十年遅れの防衛政策ですが、四国混成団創設の1981年と離隔を置かず実現したのは一つの僥倖といえるものでしたが、広すぎる第13師団管区の四国部分を独立した混成団へ移管するという方針が。

第2混成団が創設された背景には四国からへ自衛隊草創期に北海道へ向かった新隊員が北海道から郷里近くへ退官前の異動を願う時代、という実情を前述していますが、同時に第13師団が山陽山陰地区の防衛へ重点を置く必要性がありました、ソ連の海洋進出という。

ソ連の海洋進出は1979年にソ連太平洋艦隊初の航空母艦として空母ミンスクが回航され、従来のミサイル巡洋艦と共に強襲揚陸艦イワンロゴフ級の建造と太平洋への配備等、太平洋正面におけるアメリカ海軍の圧倒的な戦力への挑戦者が生まれた構図があったのですね。

日本海正面においては、日本海を隔ててソ連太平洋艦隊主力の展開するウラジヴォストークがあるのですが、空母ミンスクと強襲揚陸艦イワンロゴフと共に編成される両用作戦部隊が日本の本州日本海沿岸へ限定侵攻を加える可能性が現実的脅威として生じてきました。

西日本への大規模侵攻という蓋然性は後方連絡線の長大化からソ連軍にとり現実的ではありませんでしたが、海軍歩兵大隊を日本海沿岸の過疎地域や離島へ限定侵攻させ、政治的要求を我が国へ迫る、全面戦争と異なる制限戦争を仕掛けられる可能性は充分ありました。

第2混成団はこうした背景によりその創設が急がれると共に、流石に四国進攻という脅威は無い事から、太平洋からソ連軍が四国に着上陸するような状況であっては既に東京も京都も駄目になっていますからね、その上で四国の混成団は戦略予備となり得たといえます。

第14旅団に繋がる第2混成団、1981年新編時の編制は一個普通科連隊基幹とする増強戦闘団に近く、混成団本部、団本部中隊、第15普通科連隊、第2混成団戦車隊、第2混成団特科大隊、第2混成団施設隊、第2混成団後方支援中隊、第2混成団音楽隊、以上の通り。

1981年という年は陸上自衛隊変革の一年でもありました。新たに階級に陸曹長が創設されまして、一等陸曹の頭打ちとなった状況を打破した変革が行われました、言い換えれば幹部自衛官至上主義がアメリカ陸軍影響を受け下士官の地位向上が行われた年度なのですね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
第14旅団記念式典観閲行進は前回の第15普通科連隊観閲行進に続き第50普通科連隊、そして第14偵察隊の観閲行進へと進みます。

善通寺駐屯地の歴史は1961年の第2教育団善通寺移駐から始まりました。1959年に大久保駐屯地にて創設された第2教育団は信太山第4陸曹教育隊、大久保第107教育大隊、信太山第108教育大隊、大津第109教育大隊、善通寺第110教育大隊、という編成でした。

大久保駐屯地は京都府宇治市、京都市内から地下鉄で一本の大久保です。実はこの大久保駐屯地、困ったときは大久保駐屯地、という程に草創期の自衛隊には重視されていた駐屯地で、一時は中部方面総監部にあたる管区総監部も大久保に置く、という話が合ったほど。

管区総監部を置くという背景には当時京阪神地区の旧軍施設は朝鮮戦争に伴う国連軍施設として最大限活用されており、活用されていないものは大蔵省管理、日本経済は朝鮮特需により戦後不況を脱するかに見えていたものの財政状況は最悪で、とても土地余裕が無い。

宇治市では、しかし大阪中心部には遠すぎるという事で、しかし国連軍接収が解かれた場所はそのまま大蔵省管理となる為、書類上管理が終了する前に実質的に撤収した大阪中心部の適地を自衛隊が先に確保する、という構図で幕僚がジープにて巡回したという逸話も。

大阪第二空港、戦前から残る大阪の小型機用ローカル空港とその周辺の空き地が旧軍により飛行場とされていましたが、朝鮮戦争と共に国連軍が大阪第一空港だけでは必要な空輸能力を満たせず、大阪第二空港を拡張使用していましたがその近くに空き地があるという。

大阪第二空港の近くとはいっても空地は兵庫県側に在るといい、元々旧軍時代には大阪城が陸軍第四師団司令部庁舎として使用された歴史を振り返れば、大阪第二空港は大阪中心部からは遠いものの、神戸大阪に近い利点も。大阪第二空港はまたの名を伊丹空港という。

管区総監部、中部方面総監部と1962年の師団改編により創設された第3師団は、伊丹空港近くの伊丹駐屯地と千僧駐屯地に総監部と司令部を置く事となり今日に至ります。続いて続々入隊する新隊員へ第2教育団が大久保に置かれたのですが、手狭である事は否めない。

第4施設団と、新たに普通科連隊を従来の普通科大隊に戦車中隊までを有する大型編成を改め中隊基幹の小型編成とする際に大久保駐屯地には新編第45普通科連隊も将来的に置かれる事となります、要するに次の部隊が待っているので先にできた部隊は動く必要が、と。

1961年に善通寺駐屯地へ第2教育団は移駐しました。四国は京阪神地区や山陽広島地区と中京地区等と人口ではそれほど大きくはありませんが、多くの新隊員が志願しており、四国にて前期教育を終えた隊員は緊張高まるソ連を睨み北海道防衛の第一線へと赴きました。

四国防衛は広島第13師団、現在の第13旅団の所管となっています。第13師団の警備隊区は非常に広く、山陽山陰四国9県、つまり、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、一つの方面隊に匹敵する師団警備隊区といえますね。

当時の第13師団は師団司令部以下、米子第8普通科連隊、善通寺第15普通科連隊、山口第17普通科連隊、第13特科連隊、第13戦車大隊、第13偵察隊、第13通信大隊、第13武器大隊、第13輸送大隊、第13補給大隊、第13衛生隊、第13音楽隊、という編成です。

広島海田市へ師団司令部を置く一方で山陽地区に普通科連隊が無いのは有事の際の即応に問題が、という事で1970年に海田市へ第46普通科連隊が新編され、普通科連隊四個を基幹とする定員9000名の甲師団となりました。しかし、管区が広すぎる事に代わりはない。

山陽山陰四国9県は実際に広大だったようで、これを象徴する師団の装備がありました。第13飛行隊の装備でL-19観測機、という航空機が陸上自衛隊で最後まで装備されていたのです。L-19観測機、1965年の大怪獣ガメラやバルジ大作戦で登場した古い観測機ですね。

飛行隊にL-19観測機、既に観測ヘリコプターとしてOH-55やOH-6の配備が進んでいた時代ですが、第13師団の当時の管区は広すぎまして、連絡飛行にOH-55では全く航続距離が足りなかった為、固定翼機としてL-19が残されていたという構図です。それ程に広い。

四国善通寺に第2混成団が新編されたのは1981年、1976年に制定されました初の防衛大綱には四国への作戦部隊配置が明記されていまして、1976年は我が国が石油危機に伴う高度経済成長の終焉、狂乱物価と景気後退に見舞われている中の四国混成団創設決定でした。

緊張緩和の時代ではありましたが、我が国防衛政策は画定に10年を要する為、これも現在の中国脅威への西方シフトというべき統合機動防衛力整備事業が本格化したのは中国海洋進出が本格化した十年後に当る頃ではありますが、緊張緩和時代に決定したという訳です。

新冷戦がソ連軍アフガン侵攻により始まったのが1979年でしたので、十年遅れの防衛政策ですが、四国混成団創設の1981年と離隔を置かず実現したのは一つの僥倖といえるものでしたが、広すぎる第13師団管区の四国部分を独立した混成団へ移管するという方針が。

第2混成団が創設された背景には四国からへ自衛隊草創期に北海道へ向かった新隊員が北海道から郷里近くへ退官前の異動を願う時代、という実情を前述していますが、同時に第13師団が山陽山陰地区の防衛へ重点を置く必要性がありました、ソ連の海洋進出という。

ソ連の海洋進出は1979年にソ連太平洋艦隊初の航空母艦として空母ミンスクが回航され、従来のミサイル巡洋艦と共に強襲揚陸艦イワンロゴフ級の建造と太平洋への配備等、太平洋正面におけるアメリカ海軍の圧倒的な戦力への挑戦者が生まれた構図があったのですね。

日本海正面においては、日本海を隔ててソ連太平洋艦隊主力の展開するウラジヴォストークがあるのですが、空母ミンスクと強襲揚陸艦イワンロゴフと共に編成される両用作戦部隊が日本の本州日本海沿岸へ限定侵攻を加える可能性が現実的脅威として生じてきました。

西日本への大規模侵攻という蓋然性は後方連絡線の長大化からソ連軍にとり現実的ではありませんでしたが、海軍歩兵大隊を日本海沿岸の過疎地域や離島へ限定侵攻させ、政治的要求を我が国へ迫る、全面戦争と異なる制限戦争を仕掛けられる可能性は充分ありました。

第2混成団はこうした背景によりその創設が急がれると共に、流石に四国進攻という脅威は無い事から、太平洋からソ連軍が四国に着上陸するような状況であっては既に東京も京都も駄目になっていますからね、その上で四国の混成団は戦略予備となり得たといえます。

第14旅団に繋がる第2混成団、1981年新編時の編制は一個普通科連隊基幹とする増強戦闘団に近く、混成団本部、団本部中隊、第15普通科連隊、第2混成団戦車隊、第2混成団特科大隊、第2混成団施設隊、第2混成団後方支援中隊、第2混成団音楽隊、以上の通り。

1981年という年は陸上自衛隊変革の一年でもありました。新たに階級に陸曹長が創設されまして、一等陸曹の頭打ちとなった状況を打破した変革が行われました、言い換えれば幹部自衛官至上主義がアメリカ陸軍影響を受け下士官の地位向上が行われた年度なのですね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)