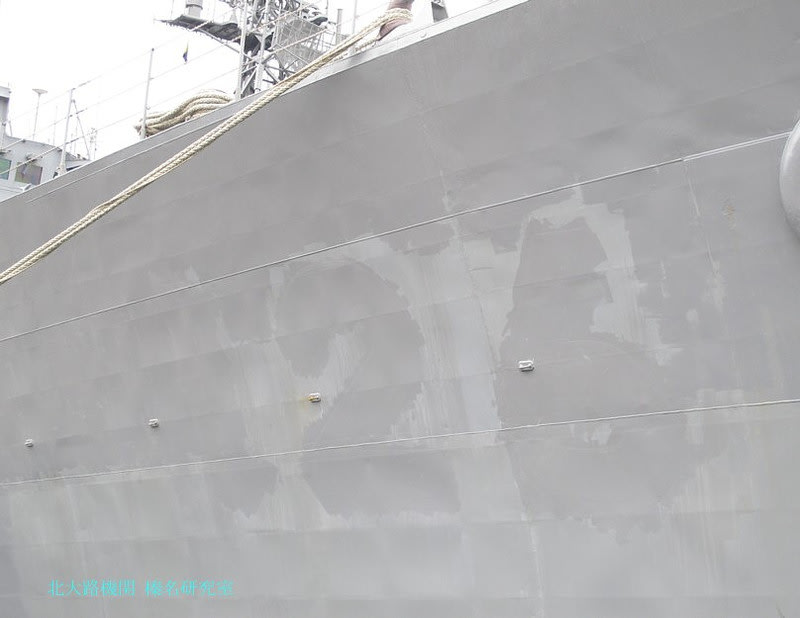2011年3月11日に東日本太平洋沿岸を襲った日本史上有数の大災害、それに伴う首相命令による十万自衛隊動員命令は当時さまざまな議論を巻き起こしました。
 しかし、実は震災の約一か月前、駒門駐屯地を中心に東海地震を想定した方面兵站演習が行われていました。実は首都直下型地震への自衛隊派遣が五万名規模と聞いていたのですが、これは過去の話であり現在ではより大規模な部隊の集中を可能としていたようでした。2月14日から18日にあけて実施されたこの演習は静岡県沖を震源とするマグニチュード8クラスの大規模地震が発生したという想定のもとで、災害派遣として全国から展開する部隊を受け入れ後方支援を行うという想定の演習です。
しかし、実は震災の約一か月前、駒門駐屯地を中心に東海地震を想定した方面兵站演習が行われていました。実は首都直下型地震への自衛隊派遣が五万名規模と聞いていたのですが、これは過去の話であり現在ではより大規模な部隊の集中を可能としていたようでした。2月14日から18日にあけて実施されたこの演習は静岡県沖を震源とするマグニチュード8クラスの大規模地震が発生したという想定のもとで、災害派遣として全国から展開する部隊を受け入れ後方支援を行うという想定の演習です。  大規模震災対処演習、この第一回となったこの演習では関口東部方面総監を統裁官に人員3400名、車両520両、航空機20機を投入され、朝霞駐屯地、松戸駐屯地、霞ケ浦駐屯地、古川駐屯地、宇都宮駐屯地、武山駐屯地、高田駐屯地、新発田駐屯地、松本駐屯地など16の駐屯地から缶詰など250tを輸送、関東燃料補給処から燃料のドラム缶3250本を輸送し駒門駐屯地の方面兵站施設FMAに運び込み、航空自衛隊浜松基地へも第1師団司令部が置かれている練馬駐屯地より物資を輸送したとのこと。
大規模震災対処演習、この第一回となったこの演習では関口東部方面総監を統裁官に人員3400名、車両520両、航空機20機を投入され、朝霞駐屯地、松戸駐屯地、霞ケ浦駐屯地、古川駐屯地、宇都宮駐屯地、武山駐屯地、高田駐屯地、新発田駐屯地、松本駐屯地など16の駐屯地から缶詰など250tを輸送、関東燃料補給処から燃料のドラム缶3250本を輸送し駒門駐屯地の方面兵站施設FMAに運び込み、航空自衛隊浜松基地へも第1師団司令部が置かれている練馬駐屯地より物資を輸送したとのこと。  方面兵站施設FMAへ集積された物資は、駒門駐屯地と浜松基地より静岡県庁や大規模運動公園など県内25か所へ物資を輸送したとのことです。駒門駐屯地と浜松基地は、地図を見れば静岡県の重要な地域にあり駒門の富士地区は首都圏と箱根を隔てており、孤立しやすい地域にありながら沿岸部の津波被害を避け得る高地にあり、他方浜松基地は沿岸に近いながら海抜は50mと一応東日本大震災規模の津波が襲来した場合でも滑走路や管制施設など基地機能を維持できることがわかるでしょう。
方面兵站施設FMAへ集積された物資は、駒門駐屯地と浜松基地より静岡県庁や大規模運動公園など県内25か所へ物資を輸送したとのことです。駒門駐屯地と浜松基地は、地図を見れば静岡県の重要な地域にあり駒門の富士地区は首都圏と箱根を隔てており、孤立しやすい地域にありながら沿岸部の津波被害を避け得る高地にあり、他方浜松基地は沿岸に近いながら海抜は50mと一応東日本大震災規模の津波が襲来した場合でも滑走路や管制施設など基地機能を維持できることがわかるでしょう。  11万名、驚くべきことはこの演習が想定していたのは11万名の部隊を東海地震の地域に投入し四日間行動する想定で物資が集積、正確には四日間の食料と支援物資に加え、部隊の行動を支えるために必要な七日分の燃料を首都圏と甲信越地方の駐屯地から集積する、という想定で、この運用計画が蓄積され、勿論東北方面隊が十分に訓練のじぎょぷ評価などを部隊運用へ反映できたのかは限界があったでしょうが東海地震と東北地方太平洋地震の想定は違えど、こうした想定が行われていたのは驚きと言えるかもしれません。
11万名、驚くべきことはこの演習が想定していたのは11万名の部隊を東海地震の地域に投入し四日間行動する想定で物資が集積、正確には四日間の食料と支援物資に加え、部隊の行動を支えるために必要な七日分の燃料を首都圏と甲信越地方の駐屯地から集積する、という想定で、この運用計画が蓄積され、勿論東北方面隊が十分に訓練のじぎょぷ評価などを部隊運用へ反映できたのかは限界があったでしょうが東海地震と東北地方太平洋地震の想定は違えど、こうした想定が行われていたのは驚きと言えるかもしれません。  東日本大震災への10万名動員、確かに自衛隊の限界を超えていた規模ではあったのですが、東海地震では四日間の想定ではあったものの11万の動員を想定していたわけで、もちろん、部隊の投入、例えば阪神大震災では被災地を警備管区とする第36普通科連隊が情報収集を行ったのちに必要な部隊投入の重点地域を検討し、結果、多くの人命を救えた、と言われています。そういう意味で無理はあったのですが、他方でこうした準備があったからこそ政治の要求に自衛隊は答えられたのだ、ともいえるのでしょうか。
東日本大震災への10万名動員、確かに自衛隊の限界を超えていた規模ではあったのですが、東海地震では四日間の想定ではあったものの11万の動員を想定していたわけで、もちろん、部隊の投入、例えば阪神大震災では被災地を警備管区とする第36普通科連隊が情報収集を行ったのちに必要な部隊投入の重点地域を検討し、結果、多くの人命を救えた、と言われています。そういう意味で無理はあったのですが、他方でこうした準備があったからこそ政治の要求に自衛隊は答えられたのだ、ともいえるのでしょうか。  備えよ常に、ということなのでしょうが、ともあれ、自衛隊は東海地震という、恐らく発生すれば日本史に残るであろう大規模地震への準備として11万の部隊動員を想定していたわけで、我が国では東日本大震災の被害や発生を想定外、と一言で片づけています。しかし自衛隊においては、少なくとも東海地震という災害を想定していた関係から、想定外、という呼称を動員の部分では使わずに済んでいるわけです。軍事機構に想定外という単語は禁忌ですが、この前提を自衛隊は履行した、ということ。東日本大震災は確かに巨大な災害でしたが、こうした準備があったからこそ、被害はあの規模に収めたのでしょう。備えよ常に、次の災害へは自衛隊の準備を見習うことが減災へつながるのだと考える次第です。
備えよ常に、ということなのでしょうが、ともあれ、自衛隊は東海地震という、恐らく発生すれば日本史に残るであろう大規模地震への準備として11万の部隊動員を想定していたわけで、我が国では東日本大震災の被害や発生を想定外、と一言で片づけています。しかし自衛隊においては、少なくとも東海地震という災害を想定していた関係から、想定外、という呼称を動員の部分では使わずに済んでいるわけです。軍事機構に想定外という単語は禁忌ですが、この前提を自衛隊は履行した、ということ。東日本大震災は確かに巨大な災害でしたが、こうした準備があったからこそ、被害はあの規模に収めたのでしょう。備えよ常に、次の災害へは自衛隊の準備を見習うことが減災へつながるのだと考える次第です。(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)