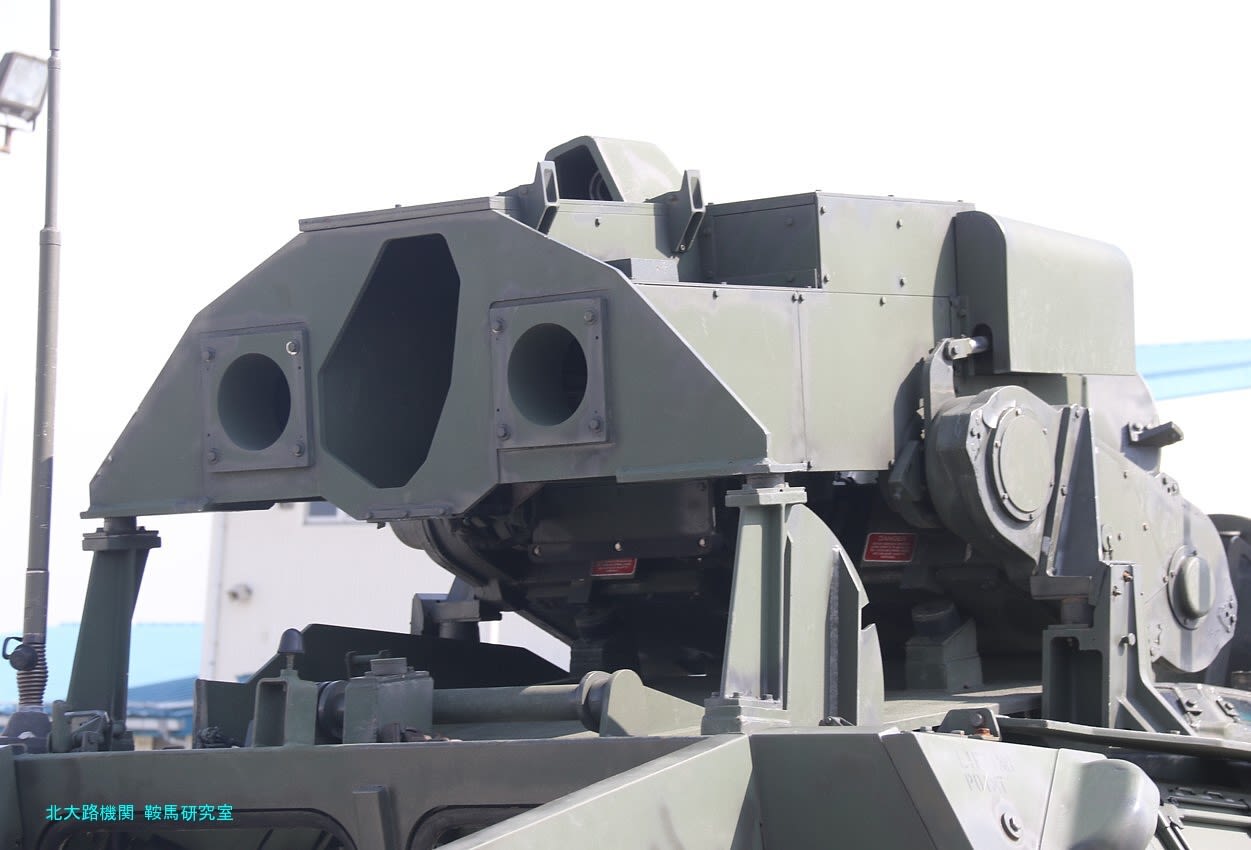■突然!舞鶴造船業廃止の衝撃
舞鶴基地を探訪しますと基地の北吸岸壁対岸に造船所が広がっている情景が日常となっています。舞鶴最大の製造業という。

舞鶴市のユニバーサル造船が今治造船に統合された際には、なるほどそれであの方が舞鶴へ戻られていたのか、と考えてしまったのですが、さらに驚いたのはユニバーサル造船舞鶴工場は今後新造を行わず、艦船整備に特化するという。これは舞鶴市には悲報のほかありません、日立造船の時代から護衛艦に掃海母艦、輸送艦も砕氷艦も建造した名門です。

今治造船の厳しい決断ですが、しかし、船舶需要の低下、特に安価な船舶造船需要が中国と韓国へシフトしているという。韓国のような政府支援があるわけでもなく、中国のような安価な人材もない、日本の造船業は苦境にあります、が、造船業が壊滅的な欧州や北米に比べればまだ産業として残り、8万の労働力が造船業界を支えています。貴重なものだ。

いずも型護衛艦建造費1100億円。日本の造船能力が高い水準で維持されていると象徴できるのは、満載排水量27000tの全通飛行甲板型艦艇を比較的安価に、ジェラルドフォード級原子力空母の十分の一という建造費です。また3900t型護衛艦、満載排水量で5000tを超える大型水上戦闘艦も500億円以下で量産できる、国力と工業力は非常に恵まれている。

2001年2月22日、鹿屋航空基地より哨戒飛行中であった第1航空群のP-3C哨戒機は異様な船団、この海域では見慣れない船団を確認する。中国海軍はこの日、沖縄本島北北西沖に6隻の艦隊を航行させました、単なる航行訓練ともいえるのですが、海上自衛隊によれば6隻の内訳は玉亭型戦車揚陸艦など揚陸艦4隻、海南型哨戒艇2隻からなるものでした。

21世紀に入ってばかりの中国艦隊出現ですが、これは歴史的な転換点でした、何故ならば中国海軍揚陸艦が日本近海で確認されたのは、この2001年2月22日が初めてのことだったのです。当時中国海軍は江把型フリゲイトなど小型艦が主力という牧歌的なもので下が、そしてこの後、中国海軍は大規模な海軍拡張を本格化させ、もうまもなく、20年となる。

おおすみ型輸送艦、海上自衛隊には優れた輸送艦が3隻配備されています、しかし、その輸送能力の見積もりはこの中国海軍による南西諸島への脅威以前のものであり、冷戦時代に北海道への急速な増援を念頭とし、陸上自衛隊は一つの目安として一個連隊戦闘団2000名の同時輸送能力を求めていました。しかし、現代と冷戦時代では運用要求の根本が違う。

北海道への増援、冷戦時代に北海道には陸上自衛隊4個師団、すべて機械化され内一個師団は機甲師団、そして特科団に高射特科団に戦車群が北海道を防衛しており、ここに増援を行う、という前提でした。一方で南西諸島防衛を考えるならば、南西諸島には沖縄本島に1個旅団、奄美大島と宮古島に、増強普通科中隊というべき警備隊が置かれるのみです。

自衛隊の海上機動能力を根本から認識を改めねばならないのではないか、特に作戦機動と業務輸送、この二つに分けて。北海道のように基盤がある地域に増強部隊を送るのではなく、南西諸島の場合は無数にある離島のなかから根本的に初動部隊を展開させねばなりません。すると求められる輸送力が根本から不足する、こうした厳しい実状があるのですね。

カーフェリー。自衛隊は政府傭船として高速カーフェリーはくおう、を運用中です。なるほどこの輸送力は特筆すべきものですが、大型フェリーが入港できる埠頭と港湾設備が整備され、受け入れられる事が大前提です。すると、揚陸艦がどうしても必要となる、自衛隊式に呼称するならば輸送艦艇、となりますか。おおすみ型輸送艦だけでは十分でない。

戦車揚陸艦LSTやドック型揚陸艦LSD,輸送艦艇といいますとこうしたものを連想するのですが、実はこれらは第二次世界大戦中に、私たちが港や造船所で日常的に目にするものを軍用に改良し転用したもので建造されています、当然といえば当然、戦時であるために変な新兵器よりは既存のものを改良し対応するものは利用できるものはすべて使う基本に。

LST戦車揚陸艦はもともと浅喫水の中型小型タンカーの設計を流用したものですし、LSDドック型揚陸艦は浮きドックの設計を大胆に改造したものです、従ってLST戦車揚陸艦については全長100m程度の内航タンカーを建造する造船所や浮きドックを建造できるメーカーであれば、LSDを建造可能、十分輸送艦艇を建造する能力がある、といえるのですね。

もちろん、ステルス性能とかデータリンク性能について考えれば専門的な技術は必要となりますが、敵前上陸をおこなう作戦輸送ではなく、事態緊迫化に先だって部隊を事前展開させる業務輸送であれば、それほど専門技術は必要ではありません。すると、日本国内の建造技術を最大限活用するならば、安価に輸送艦艇を増強する事は、充分に可能でしょう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
舞鶴基地を探訪しますと基地の北吸岸壁対岸に造船所が広がっている情景が日常となっています。舞鶴最大の製造業という。

舞鶴市のユニバーサル造船が今治造船に統合された際には、なるほどそれであの方が舞鶴へ戻られていたのか、と考えてしまったのですが、さらに驚いたのはユニバーサル造船舞鶴工場は今後新造を行わず、艦船整備に特化するという。これは舞鶴市には悲報のほかありません、日立造船の時代から護衛艦に掃海母艦、輸送艦も砕氷艦も建造した名門です。

今治造船の厳しい決断ですが、しかし、船舶需要の低下、特に安価な船舶造船需要が中国と韓国へシフトしているという。韓国のような政府支援があるわけでもなく、中国のような安価な人材もない、日本の造船業は苦境にあります、が、造船業が壊滅的な欧州や北米に比べればまだ産業として残り、8万の労働力が造船業界を支えています。貴重なものだ。

いずも型護衛艦建造費1100億円。日本の造船能力が高い水準で維持されていると象徴できるのは、満載排水量27000tの全通飛行甲板型艦艇を比較的安価に、ジェラルドフォード級原子力空母の十分の一という建造費です。また3900t型護衛艦、満載排水量で5000tを超える大型水上戦闘艦も500億円以下で量産できる、国力と工業力は非常に恵まれている。

2001年2月22日、鹿屋航空基地より哨戒飛行中であった第1航空群のP-3C哨戒機は異様な船団、この海域では見慣れない船団を確認する。中国海軍はこの日、沖縄本島北北西沖に6隻の艦隊を航行させました、単なる航行訓練ともいえるのですが、海上自衛隊によれば6隻の内訳は玉亭型戦車揚陸艦など揚陸艦4隻、海南型哨戒艇2隻からなるものでした。

21世紀に入ってばかりの中国艦隊出現ですが、これは歴史的な転換点でした、何故ならば中国海軍揚陸艦が日本近海で確認されたのは、この2001年2月22日が初めてのことだったのです。当時中国海軍は江把型フリゲイトなど小型艦が主力という牧歌的なもので下が、そしてこの後、中国海軍は大規模な海軍拡張を本格化させ、もうまもなく、20年となる。

おおすみ型輸送艦、海上自衛隊には優れた輸送艦が3隻配備されています、しかし、その輸送能力の見積もりはこの中国海軍による南西諸島への脅威以前のものであり、冷戦時代に北海道への急速な増援を念頭とし、陸上自衛隊は一つの目安として一個連隊戦闘団2000名の同時輸送能力を求めていました。しかし、現代と冷戦時代では運用要求の根本が違う。

北海道への増援、冷戦時代に北海道には陸上自衛隊4個師団、すべて機械化され内一個師団は機甲師団、そして特科団に高射特科団に戦車群が北海道を防衛しており、ここに増援を行う、という前提でした。一方で南西諸島防衛を考えるならば、南西諸島には沖縄本島に1個旅団、奄美大島と宮古島に、増強普通科中隊というべき警備隊が置かれるのみです。

自衛隊の海上機動能力を根本から認識を改めねばならないのではないか、特に作戦機動と業務輸送、この二つに分けて。北海道のように基盤がある地域に増強部隊を送るのではなく、南西諸島の場合は無数にある離島のなかから根本的に初動部隊を展開させねばなりません。すると求められる輸送力が根本から不足する、こうした厳しい実状があるのですね。

カーフェリー。自衛隊は政府傭船として高速カーフェリーはくおう、を運用中です。なるほどこの輸送力は特筆すべきものですが、大型フェリーが入港できる埠頭と港湾設備が整備され、受け入れられる事が大前提です。すると、揚陸艦がどうしても必要となる、自衛隊式に呼称するならば輸送艦艇、となりますか。おおすみ型輸送艦だけでは十分でない。

戦車揚陸艦LSTやドック型揚陸艦LSD,輸送艦艇といいますとこうしたものを連想するのですが、実はこれらは第二次世界大戦中に、私たちが港や造船所で日常的に目にするものを軍用に改良し転用したもので建造されています、当然といえば当然、戦時であるために変な新兵器よりは既存のものを改良し対応するものは利用できるものはすべて使う基本に。

LST戦車揚陸艦はもともと浅喫水の中型小型タンカーの設計を流用したものですし、LSDドック型揚陸艦は浮きドックの設計を大胆に改造したものです、従ってLST戦車揚陸艦については全長100m程度の内航タンカーを建造する造船所や浮きドックを建造できるメーカーであれば、LSDを建造可能、十分輸送艦艇を建造する能力がある、といえるのですね。

もちろん、ステルス性能とかデータリンク性能について考えれば専門的な技術は必要となりますが、敵前上陸をおこなう作戦輸送ではなく、事態緊迫化に先だって部隊を事前展開させる業務輸送であれば、それほど専門技術は必要ではありません。すると、日本国内の建造技術を最大限活用するならば、安価に輸送艦艇を増強する事は、充分に可能でしょう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)