突然500有余年前の歴史の話で恐縮である。戦国時代「最強の知将」とも称された毛利元就であるが、その策略により中国全土を支配下に収めるまでに勢力を拡大したが、その一方でお家安泰のために弱気な面も見せていたようである。

※ 毛利元就の肖像画であるが、その表情からも知略家らしい雰囲気が伺えますね。
歴史に詳しい人はこの稿は読まないでいただきたい。それほど私の歴史に関するレポートは拙い内容だからである。
7月28日(月)午後、毎月開講している「ほっかいどう学 かでる講座」の7月分の講座があった。講座は「戦国時代における大名の権力構造」と題して、北大文学研究科の助教・平井上総氏が務められた。
平井氏はテーマについて論じるにあたって、毛利家を題材として論じられた。
その講義の要旨を私なりにまとめてみることにする。
戦国大名の基本構造は、特定の武士の家(毛利家)が中核となり、それに多数の武士の家が従う、主従関係を基礎にして権力を構成するもの、とまずおさえた。
毛利家とて最初から特定の家だったわけではなく、中国地方(安芸国)に在する数多くの国人領主(小国の大名?)の一人にすぎなった。
元就が毛利家の家督を継ぐまでに安芸国は離合集散によりかなり国人領主は整理され、数は減っていたが依然として群雄割拠の状況には変わりなかった。
そうした中において知略に長けた元就は宿敵を撃破し、そして勢力を拡大した後は政略結婚などにより、ついには安芸の国を平定するまでに至ったのである。

※ NHK大河ドラマ(1997)で元就を演じた中村橋之助さんです。
さて戦国大名の権力構造とは、大名に従う家臣団にも二つのタイプがあるという。一つは主人に人身的に専属・隷属する「家人型」、そしてもう一つが主人への従属が定量的・契約的な「家礼型」の二つである。信長時代の柴田勝家や羽柴秀吉は「家人型」、徳川家康は「家礼型」と言えるだろうと平井氏は説明した。
そうした権力構造が西国一の大々名まで上り詰めた毛利元就を不安に陥れたようだ。
元就は当時の武家には珍しく筆まめだったようで、彼の書になるたくさんの文書を残したという。その中で、彼の嫡男隆元、吉川家に送り込んだ次男元春、小早川家に養子に出した三男隆景に対して、懇々と毛利家の安泰のために力を尽くすことを要求するのである。
その文書を現代文風に訳したものを平井氏が提供してくれたので、転写する。
(1)何度も言うように、毛利の名字が末代まで腐らないように心掛けるように。
(2)元春と隆景は他家を継いだが、これは今だけのこと。毛利を疎かにしてはいない。
(3)三人の仲が悪くなったら三人とも滅亡すると思え。(後略)
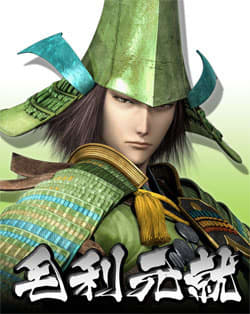
※ こちらはよく分かりませんがゲームか何かのポスターでしょうか?
平井氏は他にも元就が不安や後顧のために認めた文書を示してくれたが、多くの国人領主を従え大々名になったとはいえ、その多くは「家礼型」の家臣であったため、功成り名を遂げた元就でも不安は消えなかったのであろう。
「三本の矢」で知られる毛利元就だが(一般に知られているこの伝説はフィクションらしい)、戦国時代の権力構造の中で、頼りになるのは自分の肉親であり、息子たちだったということのようである。

※ 毛利元就の肖像画であるが、その表情からも知略家らしい雰囲気が伺えますね。
歴史に詳しい人はこの稿は読まないでいただきたい。それほど私の歴史に関するレポートは拙い内容だからである。
7月28日(月)午後、毎月開講している「ほっかいどう学 かでる講座」の7月分の講座があった。講座は「戦国時代における大名の権力構造」と題して、北大文学研究科の助教・平井上総氏が務められた。
平井氏はテーマについて論じるにあたって、毛利家を題材として論じられた。
その講義の要旨を私なりにまとめてみることにする。
戦国大名の基本構造は、特定の武士の家(毛利家)が中核となり、それに多数の武士の家が従う、主従関係を基礎にして権力を構成するもの、とまずおさえた。
毛利家とて最初から特定の家だったわけではなく、中国地方(安芸国)に在する数多くの国人領主(小国の大名?)の一人にすぎなった。
元就が毛利家の家督を継ぐまでに安芸国は離合集散によりかなり国人領主は整理され、数は減っていたが依然として群雄割拠の状況には変わりなかった。
そうした中において知略に長けた元就は宿敵を撃破し、そして勢力を拡大した後は政略結婚などにより、ついには安芸の国を平定するまでに至ったのである。

※ NHK大河ドラマ(1997)で元就を演じた中村橋之助さんです。
さて戦国大名の権力構造とは、大名に従う家臣団にも二つのタイプがあるという。一つは主人に人身的に専属・隷属する「家人型」、そしてもう一つが主人への従属が定量的・契約的な「家礼型」の二つである。信長時代の柴田勝家や羽柴秀吉は「家人型」、徳川家康は「家礼型」と言えるだろうと平井氏は説明した。
そうした権力構造が西国一の大々名まで上り詰めた毛利元就を不安に陥れたようだ。
元就は当時の武家には珍しく筆まめだったようで、彼の書になるたくさんの文書を残したという。その中で、彼の嫡男隆元、吉川家に送り込んだ次男元春、小早川家に養子に出した三男隆景に対して、懇々と毛利家の安泰のために力を尽くすことを要求するのである。
その文書を現代文風に訳したものを平井氏が提供してくれたので、転写する。
(1)何度も言うように、毛利の名字が末代まで腐らないように心掛けるように。
(2)元春と隆景は他家を継いだが、これは今だけのこと。毛利を疎かにしてはいない。
(3)三人の仲が悪くなったら三人とも滅亡すると思え。(後略)
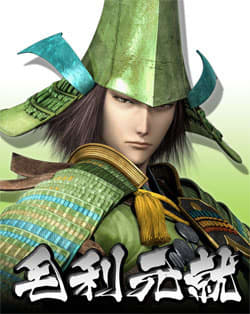
※ こちらはよく分かりませんがゲームか何かのポスターでしょうか?
平井氏は他にも元就が不安や後顧のために認めた文書を示してくれたが、多くの国人領主を従え大々名になったとはいえ、その多くは「家礼型」の家臣であったため、功成り名を遂げた元就でも不安は消えなかったのであろう。
「三本の矢」で知られる毛利元就だが(一般に知られているこの伝説はフィクションらしい)、戦国時代の権力構造の中で、頼りになるのは自分の肉親であり、息子たちだったということのようである。









