昨晩のブラタモリは「目白」の話、椿山荘が紹介されたが隣の細川家には及ばなかった。
今朝ほど悪友が連絡してきたが、「どうだ目白生まれ?」と小馬鹿にしたような言いようである。
東京での生活はたかだか2年程過ごしたばかりで、熊本地吾郎を自認しているが、私の感覚では生まれ故郷は「小石川」とか「高田老松町」であって、目白という感覚は全くない。
「神田川は目白じゃないよね」とタモリ氏が言っていたが、「ああそうなんだ」という位の認識である。
祖父が細川邸で働いた町、父が療養の甲斐なく死んだ町、母や姉が十年弱住んだ町であり、私には全く記憶にない井戸の側で遊ぶ写真一枚の証拠しかない町である。
今一度訪ねてみたいと思っていたが、最近では体力的に難しいことを大いに自覚している。
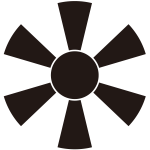
先日訪れた禅定寺に真新しい木下家のお墓があったので墓誌を見てみると、なんと日出藩木下家の五男・俊之を初代とする木下家のお墓であり、地震後幾つもあった一人墓をまとめられてとの事であった。
豊臣一族木下家の一族であることを示す、まごう事なき「日足紋」が穿たれていた。
但し本家の「木下日足紋」は使われていないが、遠慮あっての事だろうか。
禅定寺様に少々資料を差し上げるに当たり、判りやすい系図を整えようと思って、以下の略系図を作ってみた。
細川藤孝と木下勝俊(長嘯子)の和歌を通じての親交や、藤孝の女・加賀が延俊に嫁ぎ、その娘が足守の木下利当に嫁ぐなど、細川家と木下家の関係が理解できよう。
木下家利ーーー朝日 長嘯子
‖ーーーーーー+ーーーーー家定ーーーーーー+ーーー勝俊
養子定利 | |
| 豊臣秀吉 +ーーー利房ーーーーーーーー利当・・・・・・・・・・・・・・・→足守藩・25,000石
| ‖ | ‖
+ーーーーーねね | ●
| | ⇧
+ーーーーーやや | +ーーーー●延俊正室・加賀(細川藤孝女)の長女
‖ | |
浅野長政 +ーーー延俊ーーー+ーーー俊治・・・・・・・・・・・・・・・→豊前日出藩・20,000石
| |
| +ーーー延次・・・・・・・・・・・・・・・→寄合交代・5,000石
| |
| +ーーー俊之・・・・・・・・・・・・・・・→肥後細川家家臣
|
+ーーー小早川秀秋
■ 木下嘉納 (南東48-1)
肥後守家定(豊臣秀吉室ねね・実兄 姫路城主)![]()
右衛門大夫延俊(三男 豊後日出藩主 室・細川藤孝女・加賀)![]()
![]()
長兄・木下勝俊(長嘯子)
次兄・宮内少輔利房(二男 備中足守藩主)![]()
次弟・小早川秀秋
1、三郎左衛門・俊之(孫市・孫三郎 陰入)
長岡監物組 御番頭 弐千石 (寛文四年六月・御侍帳)
長兄・伊賀守俊治、豊後日出藩主![]()
次兄・縫殿助延次、五千石内分・交代寄合衆
承応元年三月~延宝元年十二月 番頭
延宝四年一月(備頭)~元禄二年七月(致仕)備頭大頭
2、平馬(三郎左衛門)
人持衆并組外衆・清左衛門組 三千石 (御侍帳・元禄五年比カ)
宝永六年九月~正徳元年四月(病死)備頭大頭
3、伊学(三郎左衛門・俊親) 三千石 御備頭五番御城代着座 屋敷・一丁目
享保元年二月~享保十七年九月 城代
享保十七年九月~元文二年二月 備頭大頭
4、伊織(養子 実・交代寄合木下家四代栄俊弟 俊允)
5、廣之助
6、平馬 上着座 三千石 宝暦二申六月廿七日当役
明和五年四月~安永二年三月(病死) 備頭大頭
7、嘉納 安永六年二月~天明六年七月 小姓頭
天明六年七月~寛政元年三月 番頭
寛政元年三月~寛政六年九月 留守居大頭
8、勇(三郎左衛門)
寛政十二年閏四月~享和二年十月 番頭
享和二年十月~文化八年七月 用人
享和元年九月~享和二年十月 鶴崎番頭
9、渋八(平馬) 上着座・持座七人着座・大木組 二千七百石 御小姓頭
文政四年六月~文政七年閏八月 番頭
文政七年閏八月~文政十一年九月 小姓頭
文政十一年九月~文政十二年十一月 番頭
10、孫一郎(三郎左衛門)
天保十年十二月~弘化二年四月 番頭
11、哲太(伊織) 御番頭 二千七百石
木下哲太差出(嘉永六年) 二千七百石
木下伊織差出(安静二年) 二千七百石
安政三年十月~文久二年七月 番頭
12、嘉納 二千七百石
元治元年八月~元治元年九月 番頭
元治元年九月~慶応三年十一月 小姓頭
慶応三年十一月~明治元年二月 番頭
明治元年五月~明治二年十月 備頭大頭・後、士大隊長















