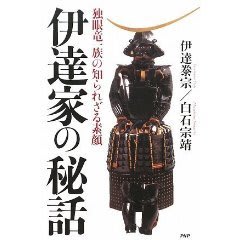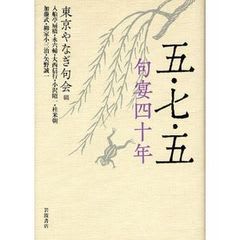翁草巻77 元寶荘子下 「吉保誇権」
吉保権に誇て大名旗本の屋敷を無體に所望し、或は繁昌の市店を追退て己が下屋敷とし、
又賄賂の金銀堆く層■を成せば、用達菱屋庄左衛門より、江府中へ貸付させ、高歩を取り、若
し返済滞るときは、其町より辨へさせ、其厳なる事公儀御為替銀拝借にも過たり、又萩原近
江守等と謀つて、あらゆる新法運上課役を以て世を虐し、其公納半を過て、吉保が有とす、斯
く金銀を聚て銅の筥を製して金千両宛を納め、竊び/\に領國甲府へ差登せて、城内に埋
て要害金とする吉保が底意の程こそ測られぬ、総じて天下の列侯も吉保へ不諂輩へは、忽
過分の御手傳御用、或は臨時の課役をかくるに仍り、大に是を迷惑して、さしも功家の歴々、
各吉保に手を拱て因み寄り、其難を避ん事を欲す、吉保に諂ふ輩大家國主の内にては、藤堂
和泉守、松平伊豫守豊前 細川越中守等、其餘勝て計りがたし、中にも 細川越中守綱利は、細川
三齋の曾孫にて、世に知られたる家柄なるに、などやらん諸家に抜んでゝ、柳澤家へ追従諂
世の人口を不愧、常に夜食を送り、後には御夜食料とて代銀にて遣し、又柳澤武運祈之為と
て、護持院の月輪院へ大業なる祈祷をあつらへ、様々軽薄を盡さるれば、皆人嘲て夜食越中
と異名せり因て吉保も細川事を殊に贔屓して、御城北之丸御普請御手傳を表向は越中守
に願はせて勤之させ、内々金銀の出方は吉保が手法を以て細川方へは掛けざりしとぞ
綱利は吉保の子を継嗣として養子に迎えようと画策している。これは老中の反対により頓挫した。
吉保権に誇て大名旗本の屋敷を無體に所望し、或は繁昌の市店を追退て己が下屋敷とし、
又賄賂の金銀堆く層■を成せば、用達菱屋庄左衛門より、江府中へ貸付させ、高歩を取り、若
し返済滞るときは、其町より辨へさせ、其厳なる事公儀御為替銀拝借にも過たり、又萩原近
江守等と謀つて、あらゆる新法運上課役を以て世を虐し、其公納半を過て、吉保が有とす、斯
く金銀を聚て銅の筥を製して金千両宛を納め、竊び/\に領國甲府へ差登せて、城内に埋
て要害金とする吉保が底意の程こそ測られぬ、総じて天下の列侯も吉保へ不諂輩へは、忽
過分の御手傳御用、或は臨時の課役をかくるに仍り、大に是を迷惑して、さしも功家の歴々、
各吉保に手を拱て因み寄り、其難を避ん事を欲す、吉保に諂ふ輩大家國主の内にては、藤堂
和泉守、松平伊豫守豊前 細川越中守等、其餘勝て計りがたし、中にも 細川越中守綱利は、細川
三齋の曾孫にて、世に知られたる家柄なるに、などやらん諸家に抜んでゝ、柳澤家へ追従諂
世の人口を不愧、常に夜食を送り、後には御夜食料とて代銀にて遣し、又柳澤武運祈之為と
て、護持院の月輪院へ大業なる祈祷をあつらへ、様々軽薄を盡さるれば、皆人嘲て夜食越中
と異名せり因て吉保も細川事を殊に贔屓して、御城北之丸御普請御手傳を表向は越中守
に願はせて勤之させ、内々金銀の出方は吉保が手法を以て細川方へは掛けざりしとぞ
綱利は吉保の子を継嗣として養子に迎えようと画策している。これは老中の反対により頓挫した。