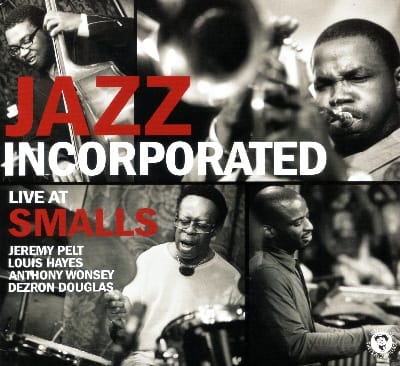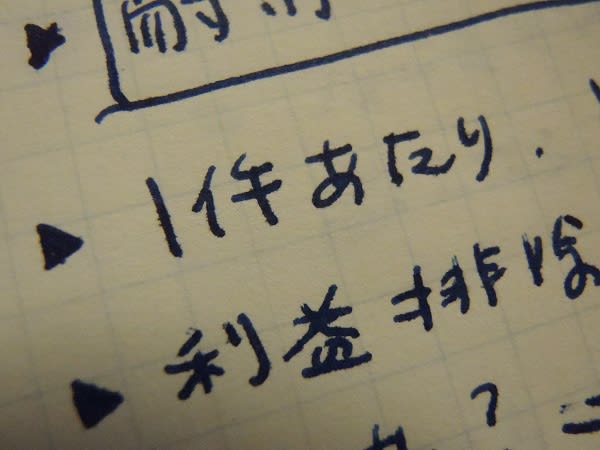鬼頭昭雄『異常気象と地球温暖化 ―未来に何が待っているか』(岩波新書、2015年)を読む。

著者は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2013-14年に提出した最新の「第5次評価報告書」の執筆にも参加している。本書もその知見を活かして、気候システムや、それを解き明かそうとする各種モデルについて説いたものになっている。その点で、気候変動に関する最新の評価を紹介しており、今、全体をつかむには良い本である。(もっとも、新書という分量の限界があるためか、もう少し図表を使って丁寧に解説すべきではないかと思う箇所が少なくない。)
最近のトピックとして、1998年に起こったエルニーニョ現象以降、2014年に至るまで、気温がわずかな上昇傾向にとどまっていることがよく挙げられる(ハイエスタス)。その原因としてわかってきたことは、海水の熱の蓄積が、この間、深層でなされていたということだという。すなわち、今後また海水の表層部分で熱を蓄積し海水温度が上昇するようになれば、また温暖化が加速するのではないかという予測がなされている。
また、氷期がまた来るのではないかという問いに対しては、CO2濃度が300ppmを超えているような状況では、それは起こりえないとの答えである。過去200万年の間、工業化がはじまるまで、300ppmを超えた時期はない。
本書は、最後に、気候工学の適用による温暖化の抑制について言及している。例えば、大気中(成層圏)にエアロゾルを撒いて太陽エネルギーの到達量を少なくする方法、CO2を分離回収して地中に貯留する方法(CCS)、海に鉄分を撒いて肥沃化する方法などである。それらについては、一時的な手段なのかどうかに加え、どのような副作用が出るかわからないという危険性を指摘している。この冷静な記述には好感を覚える。ナオミ・クライン『This Changes Everything』のように過激にそれを訴える方法は、ときに逆効果である(ナオミ・クラインは、『世界』2015年5月号におけるインタビューでも、着実な努力を否定する発言を繰り返している)。
●参照
大河内直彦『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』
多田隆治『気候変動を理学する』
米本昌平『地球変動のポリティクス 温暖化という脅威』
小嶋稔+是永淳+チン-ズウ・イン『地球進化概論』
ジェームズ・ラブロック『A Rough Ride to the Future』
ナオミ・クライン『This Changes Everything』
ナオミ・オレスケス+エリック・M・コンウェイ『The Collapse of Western Civilization』
ナオミ・オレスケス+エリック・M・コンウェイ『世界を騙しつづける科学者たち』
ノーム・チョムスキー+ラリー・ポーク『複雑化する世界、単純化する欲望 核戦争と破滅に向かう環境世界』
ノーム・チョムスキー+ラレイ・ポーク『Nuclear War and Environmental Catastrophe』
ノーム・チョムスキー講演「資本主義的民主制の下で人類は生き残れるか」
『グリーン資本主義』、『グリーン・ニューディール』
吉田文和『グリーン・エコノミー』
ダニエル・ヤーギン『探求』
『カーボン・ラッシュ』
『カーター大統領の“ソーラーパネル”を追って』 30年以上前の「選ばれなかった道」