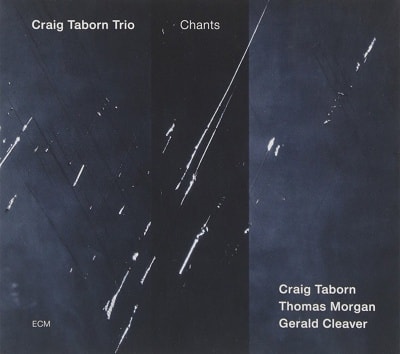政野淳子『四大公害病 水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害』(中公新書、2013年)を読む。

四大公害病については、環境問題・公害問題を象徴するものとして知らぬ者はない。しかし、これらは過去の「歴史」ではない。なぜならば、(1) すべての被害者が金銭的・精神的に救済されたわけではなく、命と記憶とによってその体験が生き続けており、(2) 行政の不作為や、責任を問われるべき企業の免責が上からなされるという過程が、2011年以降また悪夢のように顕在化してしまった、からである。
(2)については、本書に多くの指摘がある。たとえば、水俣病においては、既に浦安の「黒い水事件」(1958年)に端を発して制定された「水質二法」が適用されなかった(もっとも、寺尾忠能編『「後発性」のポリティクス』によれば、同法は甘く、公害追認法として機能し、その後の水俣病の被害拡大を招いてしまった面があるという)。新潟水俣病が公表される6年前の1959年には、通産省による水銀利用量調査が化学企業に対してなされていたにも関わらず、政治問題化することを避けて調査が秘匿されていた(なお、これを掘り起こしたのは故・宇井純氏だった)。産業界に配慮して原因の特定を遅らせたことは、すべてに共通している。
教養としてではなく、現在を視るための本として推薦。
●参照
原田正純『豊かさと棄民たち―水俣学事始め』
石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』
『花を奉る 石牟礼道子の世界』
土本典昭『水俣―患者さんとその世界―』
土本典昭さんが亡くなった
工藤敏樹『祈りの画譜 もう一つの日本』(水俣の画家・秀島由己男)
鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』
佐藤仁『「持たざる国」の資源論』(行政の不作為)
桑原史成写真展『不知火海』
桑原史成写真展『不知火海』(2)
ハマん記憶を明日へ 浦安「黒い水事件」のオーラルヒストリー
浦安市郷土博物館『海苔へのおもい』
寺尾忠能編『「後発性」のポリティクス』