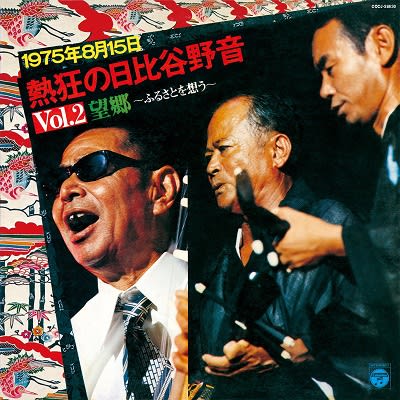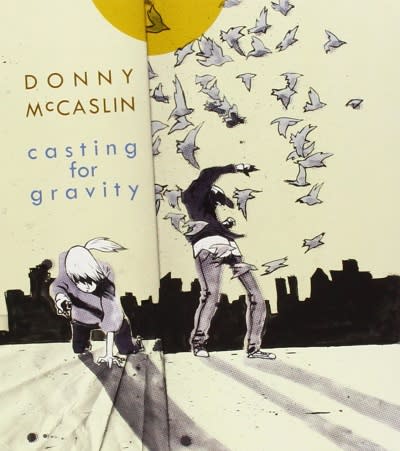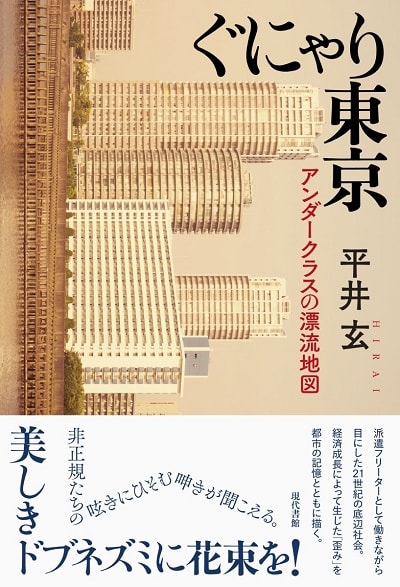『MOSQ』(Rectangle、2001年)を聴く。

Erikm (turntables, live sampling)
Charlie O (hammond organ)
Akosh Szeleveny (ts, ss, fl, kaual, bombarde)
Quentin Rollet (as)
いまだに何をどうしているのかよくわからない。フランスのRectangleレーベルはしばらく活動休止後、2011年からデジタル配信のみで復活していた。そして今回のCDリリース(他に、フィル・ミントン+ロル・コクスヒル+ノエル・アクショテ『My Chelsea』を入手した)。やはりマテリアルとして出してほしいと思うのだがどうだろう。
この音源も最近のものではなく、2001年の録音。それでも、カンタン・ロレという変態サックス奏者を聴けるだけでもよしとする。
ここでは、Erikmのターンテーブルやサンプル音源とチャーリー・Oのオルガンがドローンを創り出し、くたびれた、手垢と機械油とゴミにまみれた人工空間に連れていかれる。その環境において、アコシュ・セレヴェニとカンタン・ロレとが、さらに生存をアピールするかのようにぐちゃぐちゃのサックスソロを提示する。聴いていて喜んでいいのか絶望に身を任せるべきなのかわからなくなってしまい、脳味噌テリーヌ。
よくわからずアコシュ・セレヴェニについて検索していると、剛田武さんが紹介していた。
>> 21世紀ヨーロピアン・ジャズの潮流と謎のカオス系リードプレイヤー、AKOSH S.(アコシュ・セレヴェニ)
そしてまた、JOEさんも妙なアルバムを紹介している。なんだこのタイトルは。
>> Akosh S. - Omeko (Live)