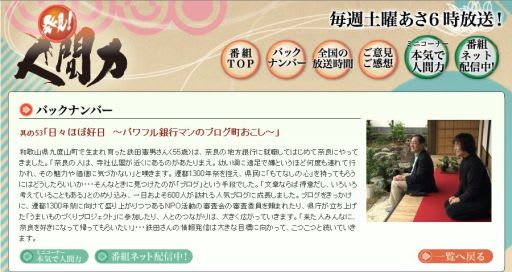前回(7/7)の当ブログ記事(快走!阪神なんば線)に、海のない奈良県人は海が大好きだ、と書いたところ、仙台のたけさんから《奈良県民待望の海! こんにちわ! 仙台は雲の合間から太陽が覗いています。奈良県って海がなかったんですね、そう言われれば…》というコメントをいただき「こんなに遠方の人が、奈良ローカルのブログを読んで下さるようになったのだな」と、しみじみ感じ入った。
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/638331bc0c14729ad99e506230679a1d
奈良県民は、海に憧れている。憧れるあまり「(海の幸のない)奈良には美味しいものがない」などと、不用意に口にしてしまう。野菜や果物、川魚(アユ、アマゴ)、畜産物(大和肉鶏、大和牛、ヤマトポーク、やまとなでしこ卵)などのことはすっかり忘れて。
阪神なんば線の開通で、近鉄奈良~阪神三宮~山陽須磨(須磨海水浴場)は約2時間の近さになったが、これまで奈良県民にとって海といえば伊勢志摩だった(近鉄奈良~大和八木~賢島は、近鉄特急で約2時間半)。
賢島や鳥羽での「食」の楽しみといえば、目の前で焼く貝やエビや魚だ。貝焼き、磯焼き、残酷焼きなどといって、生きたままの魚介類を七輪やコンロで焼くのである。素材の新鮮さと、自分で好きなように焼く楽しみがあいまって、ホテル・旅館や町の食堂だけでなく、「船上バーベキュー」として遊覧船の名物料理だ。

「蛙のへそ」のおまかせ料理の一品(トップ写真とも)
奈良でこんな焼き物を食べたいものだと思っていると、「蛙のへそ」(奈良市杉ヶ町)がおまかせメニューとして、貝類の焼き物(しかも炭火焼き)を出して下さるようになり、有り難くいただいていた。
※蛙のへそ(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/65fff510841f1cacbdfaac653b912b2d
最近になって、安くてお手軽な「波平」(奈良市大宮町)という店が、コンロで焼く魚介メニュー(漁港直送海鮮焼き)を提供していることを生駒のいぐいぐさんのブログで知った。早速訪ね、写真を撮ってきたのでご覧いただきたい。
http://d.hatena.ne.jp/iguchi_akira/20090526#1243351920

ハタハタ2尾380円(うまい!)、フグ2尾380円、イカ380円。すべて一夜干し


アワビ580円

セット料理の一部。単品では鮎380円、サザエ2個390円、ホタテ1個250円など
※「浜焼き・串かつ酒場 波平」(近鉄新大宮駅前)の紹介サイト
http://www.walkerplus.com/gourmet/168080388005/
ざっとこんな具合である。店側にとっては、焼く手間が省ける(料理人が不要)ので、人件費の節約になり、それでこんなに安く提供できるのだろう。魚介類は、注文を聞いた女性が店内の(アイスクリームのショーケースのような)冷蔵庫から運んでくる仕組みだ。
海のない奈良で船上バーベキューの気分が味わえるこのお店、いちどお試しいただきたい。
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/638331bc0c14729ad99e506230679a1d
奈良県民は、海に憧れている。憧れるあまり「(海の幸のない)奈良には美味しいものがない」などと、不用意に口にしてしまう。野菜や果物、川魚(アユ、アマゴ)、畜産物(大和肉鶏、大和牛、ヤマトポーク、やまとなでしこ卵)などのことはすっかり忘れて。
阪神なんば線の開通で、近鉄奈良~阪神三宮~山陽須磨(須磨海水浴場)は約2時間の近さになったが、これまで奈良県民にとって海といえば伊勢志摩だった(近鉄奈良~大和八木~賢島は、近鉄特急で約2時間半)。
賢島や鳥羽での「食」の楽しみといえば、目の前で焼く貝やエビや魚だ。貝焼き、磯焼き、残酷焼きなどといって、生きたままの魚介類を七輪やコンロで焼くのである。素材の新鮮さと、自分で好きなように焼く楽しみがあいまって、ホテル・旅館や町の食堂だけでなく、「船上バーベキュー」として遊覧船の名物料理だ。

「蛙のへそ」のおまかせ料理の一品(トップ写真とも)
奈良でこんな焼き物を食べたいものだと思っていると、「蛙のへそ」(奈良市杉ヶ町)がおまかせメニューとして、貝類の焼き物(しかも炭火焼き)を出して下さるようになり、有り難くいただいていた。
※蛙のへそ(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/65fff510841f1cacbdfaac653b912b2d
最近になって、安くてお手軽な「波平」(奈良市大宮町)という店が、コンロで焼く魚介メニュー(漁港直送海鮮焼き)を提供していることを生駒のいぐいぐさんのブログで知った。早速訪ね、写真を撮ってきたのでご覧いただきたい。
http://d.hatena.ne.jp/iguchi_akira/20090526#1243351920

ハタハタ2尾380円(うまい!)、フグ2尾380円、イカ380円。すべて一夜干し


アワビ580円

セット料理の一部。単品では鮎380円、サザエ2個390円、ホタテ1個250円など
※「浜焼き・串かつ酒場 波平」(近鉄新大宮駅前)の紹介サイト
http://www.walkerplus.com/gourmet/168080388005/
ざっとこんな具合である。店側にとっては、焼く手間が省ける(料理人が不要)ので、人件費の節約になり、それでこんなに安く提供できるのだろう。魚介類は、注文を聞いた女性が店内の(アイスクリームのショーケースのような)冷蔵庫から運んでくる仕組みだ。
海のない奈良で船上バーベキューの気分が味わえるこのお店、いちどお試しいただきたい。