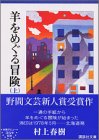以前、当ブログで「奈良県宿泊施設経営者セミナー」(7/2、9、16の3回)のことを紹介した。私は参加できなかったが、参加された方に聞くと、とても良かったという。宿泊観光客の増加は、県の最重要施策の1つだ。今後もこのような機会を作っていただきたいものである。
※「宿泊施設経営者セミナー」が開催されます!(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/afcffd88d85849b842855e5c230c7482
セミナーに参加した同僚のK嬢によると、7/2の渡壁ほづみ氏(株式会社リサージュ 代表)の話が特に印象に残ったという。「古都のホスピタリティ・観光宿泊で求められるおもてなし」という講話と「経営者が身につける接客基本トレーニング」というロールプレイングの二本立てだったそうだ。
彼女は渡壁さんのお話を克明にノートしていたので、それを見せてもらったところ、奈良の宿泊観光の問題点が浮き彫りにされていた。以下、かいつまんで内容を紹介することにしたい。
1.古都のホスピタリティ・観光宿泊で求められるおもてなし
(1)京都ではなく奈良を訪れる観光客の思いと現実
■奈良は期待通りの観光地か?
奈良に対する期待は、日本のまほろば、歴史の原点、万葉集、世界遺産 など。奈良が発祥のものも多い(能、相撲、饅頭、清酒、そうめん など)。京都は派手、奈良はしっとり落ち着いている。京都では若い人(=お土産物を買う)からお年寄りまで楽しめる。年を重ねると「奈良の方がゆっくり、ほっこりできる」と感じてもらえる。奈良は次の世代へのアピールが弱い。
奈良は期待通りの観光地ではない。奈良らしい食べ物がない(美味しい食べ物には期待が集まる)。体験観光が難しい。宿泊施設が少ない。観光地が点在しているため「次のお寺へ」と回るのが難しい。「楽しいなぁ」と感じてもらえないから、泊まってもらえない(お客様に積極的なアプローチができていない)。
奈良は説明不足、知識不足。宿泊施設の従業員は、もっと知識を身につける必要がある(飛鳥鍋に牛乳を使う理由 など)。
奈良に関する知識のある人が来れば楽しめるが、深すぎて、知識のない人には難しい。奈良は、情報を求めない限り入ってこないというイメージがある。もっと情報を発信し、若者の心をつかもう。中谷堂(餅つきのパフォーマンス)のように「わあっ」と楽しめる空間を作ろう。奈良には特級クラスの観光資源があるのに、PR下手のため、観光資源がうまく生かせていない。もっと自信と誇りを持って対処しよう。

(2)奈良のお宿に求められるお客様満足度と売上の関係
■売上アップに繋げられる人とそうでない人との差とは
遠方の人は奈良を知りたいが、知識が少ないと案内できない(どこを訪ねたら良いのか分からない。無愛想な人が多い)。しっかりと案内できる人が売上をアップできる。奈良の葛餅を持って帰りたいが、3時間しかもたない→「奈良にお連れ下さい」と伝える必要がある。「何かお薦めがありますか」→お薦めして、さらに知識があると説明できる。それが売上アップに繋がる。
(3)今こそ求められる古都・大和の国のホスピタリティ
■宿泊のお客様に100%の思いを向ける。
「わざわざ来ていただいて有り難い」という気持ちをぶつける。もっと「お客様」という意識を持つ、愛想よくする。重厚で愛想よく、いい笑顔でお出迎えを。
■古都・大和の国のご案内という誇りを持つ
今は知識不足。誇りを持って案内できる所があるか。観光に携わっている人は、何を聞かれても案内できるように。「思い入れ」があれば、自然と説明したくなるもの。
■思いを声と動作で表現する
奈良と京都の違いを明確にし、奈良の良さ・奈良にしかないお薦めを伝える(人に案内してもらうと、よく学べ、感動できる)。案内した人との出会い・ふれあいが観光客の心に残る。知らない場所を知ることができたという喜びが中高年には受ける。
2.経営者が身につける接客基本トレーニング~お客様の満足度を高めるための人材育成を考える~
(1)スタッフ教育のポイント
■押し売りと満足感、紙一重の指導
気持ちよく案内・説明する。お客様に高い満足度を持っていただくと、自然と売上がアップする。業務知識が必要。
■施設の特徴、個性を伝え続ける、マイナス箇所を好ましい箇所に変える表現
デメリットは必ずしもマイナスではない。マイナス面もプラスの表現で説明する。
■知識と好ましいご案内・説明方法は接客の要
AIDMAの法則では、消費者がある商品を知って購入に至るまでに次のような段階があるとされる。Attention (注意)→Interest (関心)→Desire (欲求)→Memory (記憶)→Action (行動)。
まずお客様に「へぇ」「ほぅ」と言ってもらえるよう(Attention) 、五感に訴える話し方をする(ウンチクも)。例えば「柿の葉寿司」などと、品名だけを伝えてはいけない。商品の特徴を伝えて、少しマイナス面も話すと「正直な人だな」と思ってもらえる。「この人は良い人だ」と思われ、聞き耳を立ててもらえる(Interest)。

■「出来て当然のこと」の徹底指導
第一印象が大切。接客3点セットとは、
・アイコンタクト…せめて2~3秒、お客様と目を合わせる
・笑顔…4番目の歯(スマイルティース)が見えるのが自然な笑顔
・明るい声…ドレミファの「ファ」から「いらっしゃいませ」
説明・案内・業務知識を身につける。「いらっしゃいませ」に+αの言葉を添える(自分らしい言葉で)。観光資源をいろんな角度から見ていく。
■ホスピタリティの素(もと)
・自信を持つ、持たせる
・宿泊施設経営者自ら、笑顔・知識・話法(+α)ができているか←もてなしの心
・奈良に対する誇りがあるか
K嬢のノートはここで終わっているが、ネットで検索すると、尾鷲市(三重県)の「東紀州宿泊施設ホスピタリテイ・アップセミナー」(東紀州観光まちづくり公社主催)で、渡壁さんの講話がブログに紹介されていた。
http://higashikishu-koyou.org/info/?itemid=196
ある中国人が《日本の田舎を体感したいという事で、先生はこの東紀州にお連れしたそうなんですが、それはそれは、この海・山に囲まれた日本ならではの田舎風景に感動されたそうです》。
しかし宿泊施設では《(質問した)料理について説明もできない、料理が残っているお皿を勝手に片付ける、といった事で、その中国人の方はとても残念がっていたそうです。その中国人のお客様は、料理に添えられているオレンジを最後に食べようと残していたもので、その接客係の人は食べないんだと勝手に判断し、さげようとしたそうです。そこで、「お下げしてもよろしいでしょうか?」の一言を添えるだけで何も問題は起こらないはずなのに、全くの自分の考え方だけでお皿を下げてしまった店員には「おもてなし」の気持ちはあるのでしょうか?》。
《細かい事ですが、何事に対してもそのお客様に対する(利用していただきありがとうございますという)感謝の気持ち、その人の立場になって考える思いやりの気持ち、というのは、全てお客様には伝わっています》。
《宿泊施設(=サービス業)というのは、料理がおいしい・お風呂がキレイ、それは当たり前です。観光地に来て、普段見られない景色や思い出を作り、その土地にまた来たい、と思わせるには、宿泊施設はとても重要な役割をもっているのだそうです》。
《全く知らない土地にやってきたお客様を暖かくお出迎えし、その土地でしか味わえない料理を出し、気持ちよくお風呂に入って頂く、そして宿を出発する朝には温かい出来立ての朝ご飯を召し上がって頂き、その1泊を最高の思い出にする。その1回の宿泊がその観光客にとっての、その土地の良し悪しイメージに繋がるそうです》。
このブログ記事は、次のような言葉で締めくくられている。《サービスとは、期待どおりの事。「おもてなし」とは、期待以上のサービス。だそうです。それは各ホテル・旅館・民宿それぞれの個性でもあり、「経営者の生き様(心意気)=おもてなし」に現れるのだと、渡壁先生はお話くださいました》。
これは良いお話だ。私としては、K嬢のノートの最後にあった「奈良に対する誇りがあるか」という言葉に強く惹(ひ)かれた。誇りを持っていれば、わざわざ奈良市が条例化するまでもなく、自然と知識欲も自信も湧(わ)いてきて、ちゃんとした「もてなし」ができるはずなのだ。ドラマ「ひとつ屋根の下」の名文句「そこに愛はあるのかい」ではないが、愛情も湧いてくるに違いない。
奈良に住みながら、他府県人に奈良の悪口を言いふらす人が絶えないのは、奈良に対する誇りも愛情も持ち合わせていないからだろう。いくら世界遺産が3つあっても、地元の人がほめないような所へなど、観光客が足を向けないのは当然だ。
渡壁さんの話から、奈良に関する知識不足→関心不足→誇り・愛情不足という悪循環が見て取れる。確かに、奈良の人は奈良のことを知らなさすぎる。それが私には悪の根源のように思えてならない。だからこれを逆に回し、誇り・愛情をもつ→関心を持つ→知識を持つ、という好循環に変えなければならない。奈良の悪口を言いそうになったとき「そこに愛はあるのかい」と、自らに問いかけてみるのも一法だろう。
※写真はすべて東向北商店街(奈良市)で、7/17の会社帰りに撮影。奈良では住民と鹿が共生している。
※「宿泊施設経営者セミナー」が開催されます!(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/afcffd88d85849b842855e5c230c7482
セミナーに参加した同僚のK嬢によると、7/2の渡壁ほづみ氏(株式会社リサージュ 代表)の話が特に印象に残ったという。「古都のホスピタリティ・観光宿泊で求められるおもてなし」という講話と「経営者が身につける接客基本トレーニング」というロールプレイングの二本立てだったそうだ。
彼女は渡壁さんのお話を克明にノートしていたので、それを見せてもらったところ、奈良の宿泊観光の問題点が浮き彫りにされていた。以下、かいつまんで内容を紹介することにしたい。
1.古都のホスピタリティ・観光宿泊で求められるおもてなし
(1)京都ではなく奈良を訪れる観光客の思いと現実
■奈良は期待通りの観光地か?
奈良に対する期待は、日本のまほろば、歴史の原点、万葉集、世界遺産 など。奈良が発祥のものも多い(能、相撲、饅頭、清酒、そうめん など)。京都は派手、奈良はしっとり落ち着いている。京都では若い人(=お土産物を買う)からお年寄りまで楽しめる。年を重ねると「奈良の方がゆっくり、ほっこりできる」と感じてもらえる。奈良は次の世代へのアピールが弱い。
奈良は期待通りの観光地ではない。奈良らしい食べ物がない(美味しい食べ物には期待が集まる)。体験観光が難しい。宿泊施設が少ない。観光地が点在しているため「次のお寺へ」と回るのが難しい。「楽しいなぁ」と感じてもらえないから、泊まってもらえない(お客様に積極的なアプローチができていない)。
奈良は説明不足、知識不足。宿泊施設の従業員は、もっと知識を身につける必要がある(飛鳥鍋に牛乳を使う理由 など)。
奈良に関する知識のある人が来れば楽しめるが、深すぎて、知識のない人には難しい。奈良は、情報を求めない限り入ってこないというイメージがある。もっと情報を発信し、若者の心をつかもう。中谷堂(餅つきのパフォーマンス)のように「わあっ」と楽しめる空間を作ろう。奈良には特級クラスの観光資源があるのに、PR下手のため、観光資源がうまく生かせていない。もっと自信と誇りを持って対処しよう。

(2)奈良のお宿に求められるお客様満足度と売上の関係
■売上アップに繋げられる人とそうでない人との差とは
遠方の人は奈良を知りたいが、知識が少ないと案内できない(どこを訪ねたら良いのか分からない。無愛想な人が多い)。しっかりと案内できる人が売上をアップできる。奈良の葛餅を持って帰りたいが、3時間しかもたない→「奈良にお連れ下さい」と伝える必要がある。「何かお薦めがありますか」→お薦めして、さらに知識があると説明できる。それが売上アップに繋がる。
(3)今こそ求められる古都・大和の国のホスピタリティ
■宿泊のお客様に100%の思いを向ける。
「わざわざ来ていただいて有り難い」という気持ちをぶつける。もっと「お客様」という意識を持つ、愛想よくする。重厚で愛想よく、いい笑顔でお出迎えを。
■古都・大和の国のご案内という誇りを持つ
今は知識不足。誇りを持って案内できる所があるか。観光に携わっている人は、何を聞かれても案内できるように。「思い入れ」があれば、自然と説明したくなるもの。
■思いを声と動作で表現する
奈良と京都の違いを明確にし、奈良の良さ・奈良にしかないお薦めを伝える(人に案内してもらうと、よく学べ、感動できる)。案内した人との出会い・ふれあいが観光客の心に残る。知らない場所を知ることができたという喜びが中高年には受ける。
2.経営者が身につける接客基本トレーニング~お客様の満足度を高めるための人材育成を考える~
(1)スタッフ教育のポイント
■押し売りと満足感、紙一重の指導
気持ちよく案内・説明する。お客様に高い満足度を持っていただくと、自然と売上がアップする。業務知識が必要。
■施設の特徴、個性を伝え続ける、マイナス箇所を好ましい箇所に変える表現
デメリットは必ずしもマイナスではない。マイナス面もプラスの表現で説明する。
■知識と好ましいご案内・説明方法は接客の要
AIDMAの法則では、消費者がある商品を知って購入に至るまでに次のような段階があるとされる。Attention (注意)→Interest (関心)→Desire (欲求)→Memory (記憶)→Action (行動)。
まずお客様に「へぇ」「ほぅ」と言ってもらえるよう(Attention) 、五感に訴える話し方をする(ウンチクも)。例えば「柿の葉寿司」などと、品名だけを伝えてはいけない。商品の特徴を伝えて、少しマイナス面も話すと「正直な人だな」と思ってもらえる。「この人は良い人だ」と思われ、聞き耳を立ててもらえる(Interest)。

■「出来て当然のこと」の徹底指導
第一印象が大切。接客3点セットとは、
・アイコンタクト…せめて2~3秒、お客様と目を合わせる
・笑顔…4番目の歯(スマイルティース)が見えるのが自然な笑顔
・明るい声…ドレミファの「ファ」から「いらっしゃいませ」
説明・案内・業務知識を身につける。「いらっしゃいませ」に+αの言葉を添える(自分らしい言葉で)。観光資源をいろんな角度から見ていく。
■ホスピタリティの素(もと)
・自信を持つ、持たせる
・宿泊施設経営者自ら、笑顔・知識・話法(+α)ができているか←もてなしの心
・奈良に対する誇りがあるか
K嬢のノートはここで終わっているが、ネットで検索すると、尾鷲市(三重県)の「東紀州宿泊施設ホスピタリテイ・アップセミナー」(東紀州観光まちづくり公社主催)で、渡壁さんの講話がブログに紹介されていた。
http://higashikishu-koyou.org/info/?itemid=196
ある中国人が《日本の田舎を体感したいという事で、先生はこの東紀州にお連れしたそうなんですが、それはそれは、この海・山に囲まれた日本ならではの田舎風景に感動されたそうです》。
しかし宿泊施設では《(質問した)料理について説明もできない、料理が残っているお皿を勝手に片付ける、といった事で、その中国人の方はとても残念がっていたそうです。その中国人のお客様は、料理に添えられているオレンジを最後に食べようと残していたもので、その接客係の人は食べないんだと勝手に判断し、さげようとしたそうです。そこで、「お下げしてもよろしいでしょうか?」の一言を添えるだけで何も問題は起こらないはずなのに、全くの自分の考え方だけでお皿を下げてしまった店員には「おもてなし」の気持ちはあるのでしょうか?》。
《細かい事ですが、何事に対してもそのお客様に対する(利用していただきありがとうございますという)感謝の気持ち、その人の立場になって考える思いやりの気持ち、というのは、全てお客様には伝わっています》。
《宿泊施設(=サービス業)というのは、料理がおいしい・お風呂がキレイ、それは当たり前です。観光地に来て、普段見られない景色や思い出を作り、その土地にまた来たい、と思わせるには、宿泊施設はとても重要な役割をもっているのだそうです》。
《全く知らない土地にやってきたお客様を暖かくお出迎えし、その土地でしか味わえない料理を出し、気持ちよくお風呂に入って頂く、そして宿を出発する朝には温かい出来立ての朝ご飯を召し上がって頂き、その1泊を最高の思い出にする。その1回の宿泊がその観光客にとっての、その土地の良し悪しイメージに繋がるそうです》。
このブログ記事は、次のような言葉で締めくくられている。《サービスとは、期待どおりの事。「おもてなし」とは、期待以上のサービス。だそうです。それは各ホテル・旅館・民宿それぞれの個性でもあり、「経営者の生き様(心意気)=おもてなし」に現れるのだと、渡壁先生はお話くださいました》。
これは良いお話だ。私としては、K嬢のノートの最後にあった「奈良に対する誇りがあるか」という言葉に強く惹(ひ)かれた。誇りを持っていれば、わざわざ奈良市が条例化するまでもなく、自然と知識欲も自信も湧(わ)いてきて、ちゃんとした「もてなし」ができるはずなのだ。ドラマ「ひとつ屋根の下」の名文句「そこに愛はあるのかい」ではないが、愛情も湧いてくるに違いない。
奈良に住みながら、他府県人に奈良の悪口を言いふらす人が絶えないのは、奈良に対する誇りも愛情も持ち合わせていないからだろう。いくら世界遺産が3つあっても、地元の人がほめないような所へなど、観光客が足を向けないのは当然だ。
渡壁さんの話から、奈良に関する知識不足→関心不足→誇り・愛情不足という悪循環が見て取れる。確かに、奈良の人は奈良のことを知らなさすぎる。それが私には悪の根源のように思えてならない。だからこれを逆に回し、誇り・愛情をもつ→関心を持つ→知識を持つ、という好循環に変えなければならない。奈良の悪口を言いそうになったとき「そこに愛はあるのかい」と、自らに問いかけてみるのも一法だろう。
※写真はすべて東向北商店街(奈良市)で、7/17の会社帰りに撮影。奈良では住民と鹿が共生している。