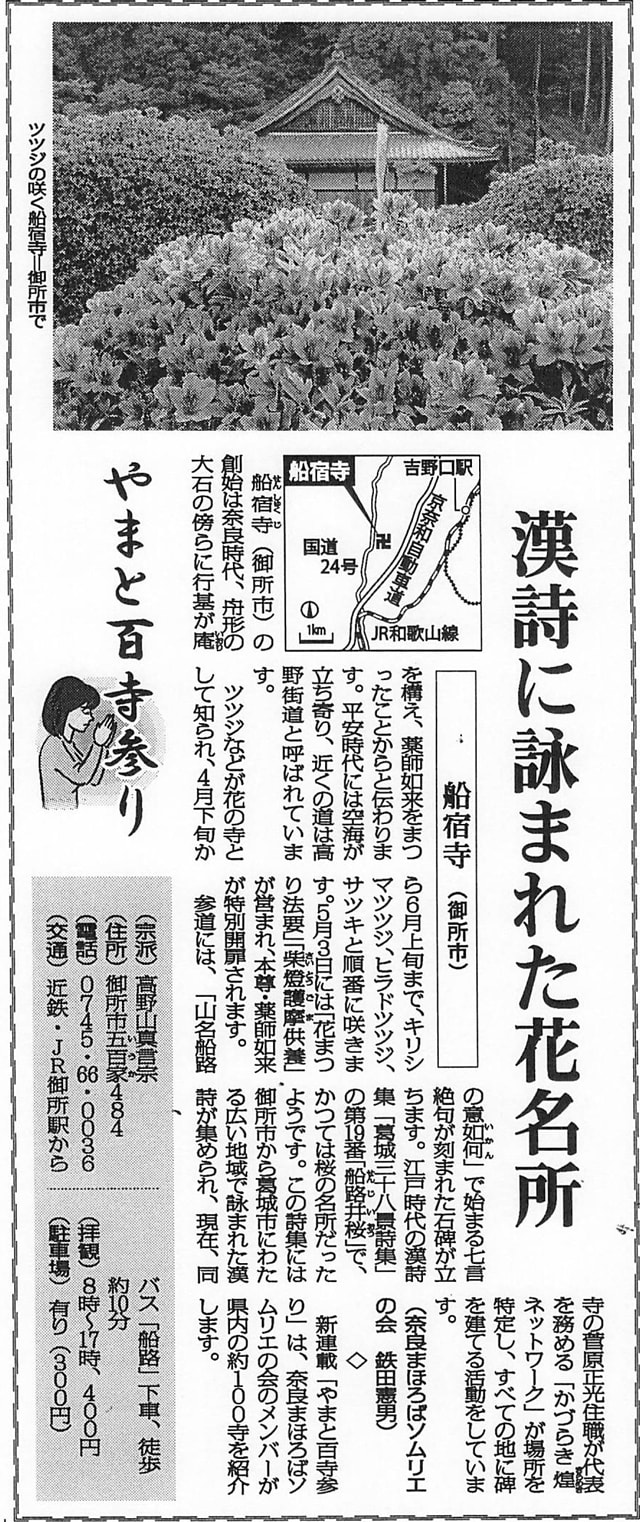壷阪寺(高市郡高取町壷阪3)では毎年4月上旬~5月中旬にヤマブキ(山吹)が咲き、それを「やまぶきまつり」と呼んでいる。お寺のHPによると、2019年4月17日(水)時点の「やまぶき開花状況」は「一重の山吹は満開、八重の山吹は咲き始め」ということだ。
※写真はすべて、2012年4月29日に壷阪寺で撮影



桜(八重桜)はもう散ったようだが、ヤマブキは境内一円に咲くので、これは見ごたえがある。

今朝(4/20)の奈良新聞によると、般若寺(奈良市般若寺町221)のヤマブキも見ごろを迎えているそうだ(過去の当ブログ記事は、こちら)。「見ごろは今月いっぱい。春らしい黄色い花が境内を彩る」とある。ただしお寺のHPには、境内はコスモスを準備するため整備中で、足元が悪くなっているそうなので、注意しながらお参りいただきたい。
※写真はすべて、2012年4月29日に壷阪寺で撮影



桜(八重桜)はもう散ったようだが、ヤマブキは境内一円に咲くので、これは見ごたえがある。

今朝(4/20)の奈良新聞によると、般若寺(奈良市般若寺町221)のヤマブキも見ごろを迎えているそうだ(過去の当ブログ記事は、こちら)。「見ごろは今月いっぱい。春らしい黄色い花が境内を彩る」とある。ただしお寺のHPには、境内はコスモスを準備するため整備中で、足元が悪くなっているそうなので、注意しながらお参りいただきたい。