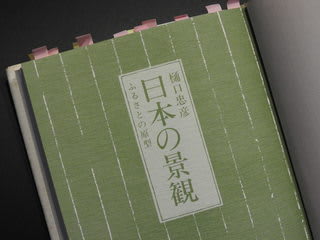
『日本の景観 ふるさとの原型』樋口忠彦/春秋社 の再読を終えた。
本書で著者の樋口氏は日本の景観を次のようなタイプに分ける。「盆地の景観」「谷の景観」「山の辺の景観」「平地の景観」。タイポロジーが研究のスタートだ。
更に、樋口氏は盆地の景観を「秋津洲やまと」型と「八葉蓮華」型に、谷の景観を「水分神社(みくまり)」型と「隠国(こもりく)型」に、そして山の辺の景観を「蔵風得水」型と「神奈備山」型、「国見山」型の各景観に分ける。
そして平地の景観は後世になってそこに手を加えることによって山の辺の代償景観や国見山の代償景観などを生み出してきたことを指摘する。平地にそびえる天守は国見山景観の延長線上に位置づけられるという。
**盆地は、「場の平衡状態を維持」するという、母性原理が最も働きやすい空間であり、「みなと」で受け止められた異種文化は、盆地空間に入るや、この母性原理に包みこまれ、日本独得の重層的文化を形成し、新たな装いをこらして日本各地に発信されていった。さらに、これらの文化を重層的に温存させている小盆地が「小やまと」型景観として日本各地に点在し、小京都として今でも日本人に好まれている。**(167頁)
引用が長くなったが、それぞれの景観についてこのような論考をしている。興味深いのは最終章で都市の景観を上記のような地形景観のアナロジーとして捉えて論じていることだ。
**(前略)背後に建物を負い、前方に開けた街路や広場の活動的な景観を見通しながら休息しているという景観の型は、谷や盆地や平野の山の辺の棲息地の景観と全く同じ型であるといってもよい。**(247、8頁)
都市景観を地形景観のアナロジーとして捉えることで、心地良い棲息地景観として都市景観を創造していくための方策が見えてくる。
論理的な筋書きが明解な論考。









