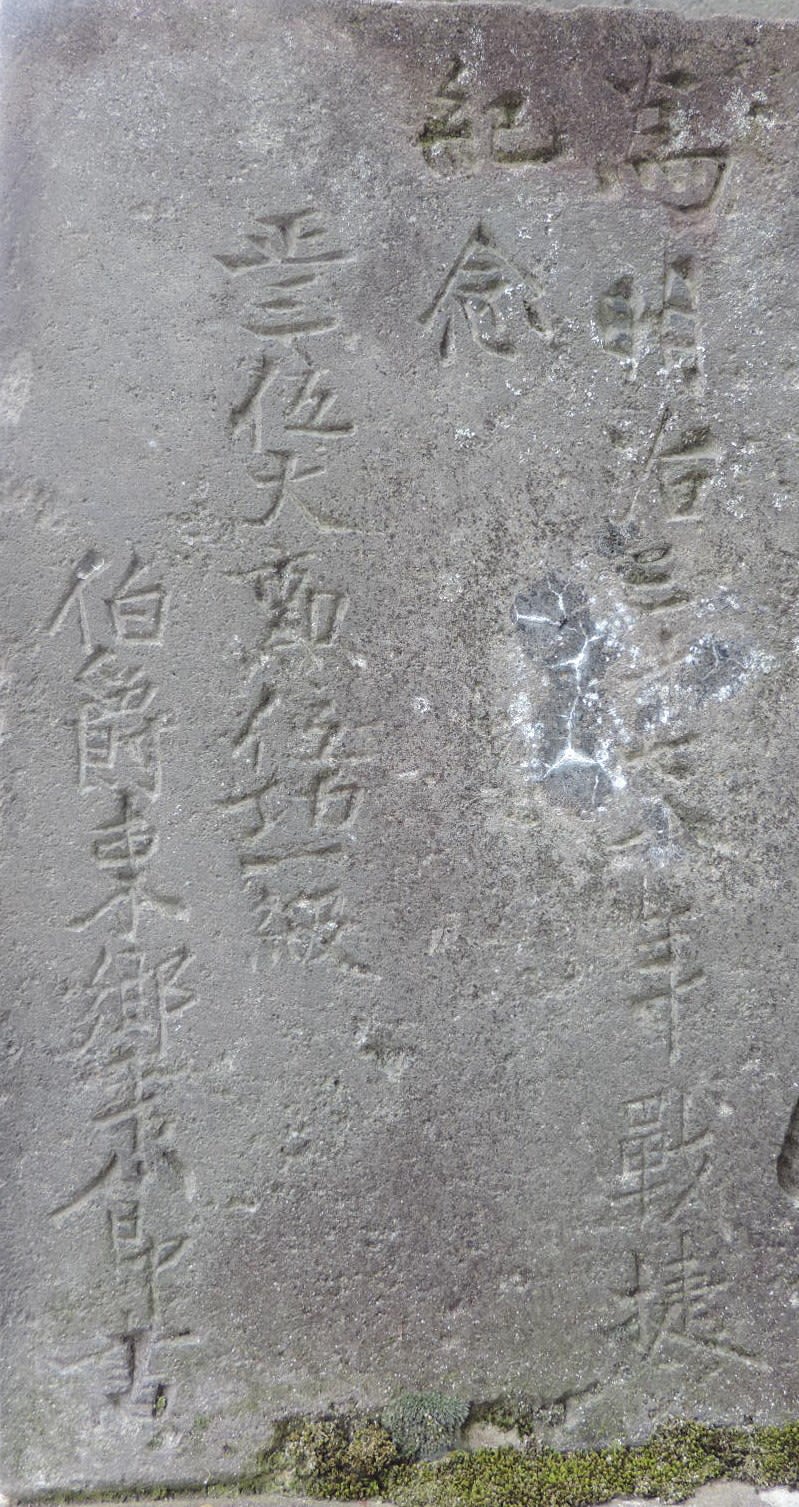540 須坂市須坂太子町にて 撮影日150510
■ 高山村の火の見櫓巡りをしたいと前から思っていたが、ようやく10日の日曜日に出かけることができた。カーナビで高山村役場を目的地にセットして、朝7時半過ぎに家を出た。カーナビの音声ガイドに従って行けば難なく目的地に着くことができる。
須坂長野東インターで上信越自動車道を下りて須坂市を通って高山村へ。途中、須坂市内でこの火の見櫓を見つけた。東北信でよく見かけるタイプの火の見櫓。
4角形の櫓、中間に櫓の中に納まっている踊り場があり、その上にカンガルーポケットが付いている。ここの手すりに消火ホースを掛けるフックがあり、消火ホースが1本掛けてある。消火ホースの長さは20mだから、高さの推測ができる。見張り台まで15mくらいか。
4角錘(方形)の屋根の頂部の避雷針には細い丸鋼の飾りがついている。4隅には蕨手。
櫓のブレースは下半分はリング式ターンバックル付きブレースで上半分は山形鋼をブレースとして用いている。なぜこのような使い分け? 両者の機能的な違いは櫓のゆがみ(変形)を調整できるかどうか。櫓上部は各構面が小さいので、ほとんど変形しない。だから調整機能付きのブレースは不要、という判断ではなかろうか。もっとも、よく観察しなかったからこの火の見櫓のリング式ターンバックル付きブレースが調整できるようになっているかどうかは定かではないが・・・。
脚部 柱脚部分に根巻きコンクリート(という理解でいいのかな)を施工してある。
櫓の中に入って上を見上げると、こんな感じ。梯子段に山形鋼を用いている。丸鋼と比べて昇り降りする際、足掛かりはよいが、手でつかみにくい。とすると、丸鋼と山形鋼のどちらがいいのだろう・・・。
ここを昇り降りするのは怖そう・・・。