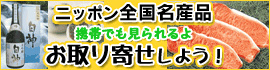【まくら】
自分の死後に財産が他人に渡るのを嫌がる僧侶と、その財産を奪おうと企む男を通して人間の深い欲望を描いた、珠玉のブラックコメディである。
出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
【あらすじ】
下谷の僧侶・西念(さいねん)は、寺を持たずに長屋で貧しい生活を送っていた。西念は風邪に感染して体調を崩し、寝込んでしまう。長屋の隣りの部屋に住んでいる金兵衛(きんべい)が西念を看病する事になった。
何か食べたい物はあるかと金兵衛が尋ねると、餡子入りの餅が食べたいと答える。
金兵衛が大量の餡子餅を購入して西念の部屋に届けると、人の居る前で食事をするのは好きでないと言って金兵衛を帰宅させる。
何か不思議に思った金兵衛は自分の部屋の壁穴から西念の部屋を覗いてみた。西念は密かに蓄えておいた大量の硬貨を取り出した。
その硬貨を餅で一つずつ包み、口に入れて丸飲みしていく。
全ての硬貨を飲み終えた西念は、苦しそうに呻き声をあげる。
驚いた金兵衛は西念の部屋に入り餅を吐き出すように勧めるが、西念は決して口を開かず、そのまま死亡する。
金兵衛は突然の出来事に戸惑いつつも、何とか西念の腹中の硬貨を自分の物にしてしまいたいとの欲望を抑えられない。
金目のものは売り払って酒に換えた生臭坊主に、いい加減な経を読ませ、西念の葬儀が寺で行われる。
金兵衛は葬儀の出席者の長屋の住人や家主と別れ、西念の遺体を入れた樽を荷車で引いて火葬場へ急ぐ。
このときの火葬場は現在の麻布十番あたりに設定されており、下谷から麻布までの情景描写を交えた地名の羅列がある。
焼き場に着き、今は夜だから翌朝に火葬するとは説明するが、金兵衛はを脅して即座に火葬させる。
腹部は生焼けにするよう強く念を押し、金兵衛は火葬場を出る。
翌朝、金兵衛は火葬済みの遺体を引き取りに行く。
を離れさせ、用意した包丁で遺体の生焼けの腹部を切開する。
中を探ると、胃の中には損傷を免れた大量の硬貨が入っていた。
金兵衛は喜んで全ての硬貨を自分の懐中に収める。
目当ての硬貨を手に入れたので、残った遺骨に用は無かった。
戸惑うと遺骨を置いて、金兵衛は嬉々として火葬場を飛び出した。
金兵衛は手に入れた大金を資金にして、目黒に餅店を開いた。
商売は大成功し、店の餅は黄金餅と呼ばれ江戸の名物となった。
出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
【オチ・サゲ】なし
【語句豆辞典】
【生臭坊主】(なまぐさぼうず)僧侶が食べることを禁じられていた、魚肉・獣肉などの生臭物を平気で食べる坊主のこと。または、戒律を守らない僧のこと。品行の悪い僧。
【吝嗇】(りんしょく)けち。
【頭陀袋】(ずたぶくろ)行脚の僧が僧衣などを入れる木綿の袋。
【薬礼】(やくれい)医者に払う薬代や治療費。
【胴巻】(どうまき)細長い帯状の布袋。金銭などを入れ、腹に巻き付けて使う。
【この噺を得意とした落語家】
・五代目古今亭志ん生
・七代目立川談志
【落語豆知識】 出囃子(でばやし)
高座に上がるときのテーマソング。
二つ目以上の噺家は、一人一人自分の曲を持っている。
したがって、通な客になると出囃子を聴くだけで登場する噺家が分かるのである。例えば
・桂米丸(金比羅舟々)
・桂歌丸(大漁節)
・三遊亭円楽(元禄花見踊)
・林家木久蔵(宮さん宮さん)
・柳家小三治(二上りかっこ)
・立川談志(木賊=とくさ、刈り)
・立川志の輔(梅は咲いたか)
・橘家円蔵(虎退治)
・春風亭小朝(さわぎ)
・三遊亭小遊三(ボタンとリボン)
・春風亭昇太(デイビー・クロケット)
出囃子に合わせて高座の中央に歩き、座布団に座り、客席に向かって深々とおじぎをし、ゆっくりと頭をあげて正面を向くと同時に出囃子が終わる、というのが一人前の噺家。
なお、寄席でトリを取る時は、自分の出囃子とは別に、「今日の最後の出演者だ。」と観客に知らせるため、「中の舞」を使う。



自分の死後に財産が他人に渡るのを嫌がる僧侶と、その財産を奪おうと企む男を通して人間の深い欲望を描いた、珠玉のブラックコメディである。
出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
【あらすじ】
下谷の僧侶・西念(さいねん)は、寺を持たずに長屋で貧しい生活を送っていた。西念は風邪に感染して体調を崩し、寝込んでしまう。長屋の隣りの部屋に住んでいる金兵衛(きんべい)が西念を看病する事になった。
何か食べたい物はあるかと金兵衛が尋ねると、餡子入りの餅が食べたいと答える。
金兵衛が大量の餡子餅を購入して西念の部屋に届けると、人の居る前で食事をするのは好きでないと言って金兵衛を帰宅させる。
何か不思議に思った金兵衛は自分の部屋の壁穴から西念の部屋を覗いてみた。西念は密かに蓄えておいた大量の硬貨を取り出した。
その硬貨を餅で一つずつ包み、口に入れて丸飲みしていく。
全ての硬貨を飲み終えた西念は、苦しそうに呻き声をあげる。
驚いた金兵衛は西念の部屋に入り餅を吐き出すように勧めるが、西念は決して口を開かず、そのまま死亡する。
金兵衛は突然の出来事に戸惑いつつも、何とか西念の腹中の硬貨を自分の物にしてしまいたいとの欲望を抑えられない。
金目のものは売り払って酒に換えた生臭坊主に、いい加減な経を読ませ、西念の葬儀が寺で行われる。
金兵衛は葬儀の出席者の長屋の住人や家主と別れ、西念の遺体を入れた樽を荷車で引いて火葬場へ急ぐ。
このときの火葬場は現在の麻布十番あたりに設定されており、下谷から麻布までの情景描写を交えた地名の羅列がある。
焼き場に着き、今は夜だから翌朝に火葬するとは説明するが、金兵衛はを脅して即座に火葬させる。
腹部は生焼けにするよう強く念を押し、金兵衛は火葬場を出る。
翌朝、金兵衛は火葬済みの遺体を引き取りに行く。
を離れさせ、用意した包丁で遺体の生焼けの腹部を切開する。
中を探ると、胃の中には損傷を免れた大量の硬貨が入っていた。
金兵衛は喜んで全ての硬貨を自分の懐中に収める。
目当ての硬貨を手に入れたので、残った遺骨に用は無かった。
戸惑うと遺骨を置いて、金兵衛は嬉々として火葬場を飛び出した。
金兵衛は手に入れた大金を資金にして、目黒に餅店を開いた。
商売は大成功し、店の餅は黄金餅と呼ばれ江戸の名物となった。
出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
【オチ・サゲ】なし
【語句豆辞典】
【生臭坊主】(なまぐさぼうず)僧侶が食べることを禁じられていた、魚肉・獣肉などの生臭物を平気で食べる坊主のこと。または、戒律を守らない僧のこと。品行の悪い僧。
【吝嗇】(りんしょく)けち。
【頭陀袋】(ずたぶくろ)行脚の僧が僧衣などを入れる木綿の袋。
【薬礼】(やくれい)医者に払う薬代や治療費。
【胴巻】(どうまき)細長い帯状の布袋。金銭などを入れ、腹に巻き付けて使う。
【この噺を得意とした落語家】
・五代目古今亭志ん生
・七代目立川談志
【落語豆知識】 出囃子(でばやし)
高座に上がるときのテーマソング。
二つ目以上の噺家は、一人一人自分の曲を持っている。
したがって、通な客になると出囃子を聴くだけで登場する噺家が分かるのである。例えば
・桂米丸(金比羅舟々)
・桂歌丸(大漁節)
・三遊亭円楽(元禄花見踊)
・林家木久蔵(宮さん宮さん)
・柳家小三治(二上りかっこ)
・立川談志(木賊=とくさ、刈り)
・立川志の輔(梅は咲いたか)
・橘家円蔵(虎退治)
・春風亭小朝(さわぎ)
・三遊亭小遊三(ボタンとリボン)
・春風亭昇太(デイビー・クロケット)
出囃子に合わせて高座の中央に歩き、座布団に座り、客席に向かって深々とおじぎをし、ゆっくりと頭をあげて正面を向くと同時に出囃子が終わる、というのが一人前の噺家。
なお、寄席でトリを取る時は、自分の出囃子とは別に、「今日の最後の出演者だ。」と観客に知らせるため、「中の舞」を使う。