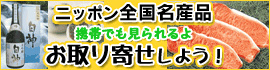【まくら】
人情噺の一つ。 別名は「唐茄子屋」。
上方では「南京屋政談」、「南京政談」、「なんきん政談」と呼ばれる。 東西では少し内容が違っていたりする。
大店の若旦那が遊びをすごして勘当される。
こういうテーマは江戸時代からたくさんあるが、その後の展開はさまざまだ。
この咄の場合はカボチャを売ることになった。
江戸時代に野菜の種類がぐんと豊富になるが、それはこのカボチャをはじめとして新大陸やアジア方面から新しい野菜が次々ともたらされたからである。
このひときわ重い野菜を売る苦労をして、徳さんはかつて出入りしていた華やかな吉原とは別の世界を、浅草で発見することになる。
それは浅草寺の西に位置する誓願寺のはずれ、東本願寺の北側の石塀に沿った「誓願寺店」という貧しい地帯であった。
江戸時代も明治以降も、浅草は華やかで賑やかな繁華街であるとともに、苦しい生活をしている人たちの生活の場でもあったのだ。
徳さんは勘当されたことで、世間の深みを知るのである。
出典: 『TBS落語研究会』
【あらすじ】
遊びすぎて、”お天道様と釜の飯は付いてくる”と自ら勘当された若旦那”徳”は最初の内は良かったが、その内誰にも相手にされなくなった。
雨も上がって吾妻橋までさしかかり欄干から飛び込もうとするところを、たまたま叔父さんに助けられた。
何でもするからと、達磨横丁の叔父さんの家に連れられていった。
おばさんに挨拶して食事もすむと疲れがどっと出て、死ぬ様に眠った。
翌朝、叔父さんに起こされ、今日から「唐茄子」を売り歩けという。
みっともないから・・と言うと、さとされ天秤を担いでヨロヨロしながら長屋を出ていった。
アミダになった傘も直せず、天秤にしがみついて歩いていたが、吾妻橋を渡って田原町に来た時にはたまらず、荷を投げ出して倒れてしまった。
親切な住民が手分けして買ってくれた。
残った二つを担いで歩き始めたが売り声も出ない。
吉原脇の田んぼの中で売り声の練習をしながら、道楽三昧の日々を思い出していた。
声も出る様になって、誓願寺店に入って来ると、質素だが品のいい奥さんに声を掛けられ、売り切った。
弁当を使わしてくれと頼んで食べ始めると五つ位の男の子が「おまんまだ!」と言って離れない。
事情を聞くと亭主の送金が無く買う事も出来ずに、困っていると言う。
ひもじいのはよく分かると、子供に弁当をやって、売り上げを全部渡して振り切る様にして戻ってきた。
完売した事に叔父さんも喜んでくれた。食事の出る間、顛末を聞いていたが、売り上げを見せろと言うが無い。
誓願寺店で親子に弁当とお金を全部上げたというと本当ならイイが、これから行こうと提灯を持って立ち上がった。
誓願寺店に着いてみると、長屋では大騒動。
話を聞いてみると、あげたお金を因業大家が全部、店賃として取り上げてしまったので、奥さんが悲観して首をくくってしまった。
徳は感極まって大家の家に怒鳴り込んで、やかん頭にやかんで殴りつけ、溜飲を下げた。
奥さんは医者に診てもらい、寿命があったと見えて助かり、叔父さんが親子を引き取り暮らした。
収まらないのは徳さんで、自分が行かなければ奥さんは助からなかっただろう。
この事を奉行に願って出た。
裁きの結果、大家はきついおとがめ、徳さんは人助けをしたとして、青差し十貫目の褒美をもらい、勘当が許されたという。
”情けは人の為ならず”唐茄子屋政談の一席。
出典: 『落語の舞台を歩く』
【オチ・サゲ】不明
【語句豆辞典】
【唐茄子】カボチャのこと。地域によって呼び名がいろいろあり、唐茄子のほかナンキンと呼ばれる。
【半纏(はんてん)】庶民が愛用した、羽織に似て丈の短い上着。
【股引(ももひき)】江戸っ子はモモシキという。ズボンを細くしたようない退く出、下着と作業衣がある。
【誓願寺店(せいがんじだな)】後半の舞台になる誓願寺店は、現在の台東区元浅草四丁目にあたり、旧東本願寺裏の誓願寺門前町に実在した裏長屋。
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『傾城の恋は誠の恋ならで、金持って来いがほんの恋』
『後悔を先に立たせて後からみれば、杖をついたり転んだり』
『菜の花や向こうに蝶の屋根が見え』
『玉の輿乗りそこのうてもくよくよするな、まさかみそこしゃさげさせぬ』
【この噺を得意とした落語家】
・五代目 古今亭志ん生
・六代目 三遊亭圓生
・三代目 古今亭 志ん朝
・四代目 桂福団治
【落語豆知識】 上下(かみしも)
落語演出の基本。客席から見て右が上手(かみて)左が下手(しもて)。
噺す向きを変える事で登場人物を描き分ける。



人情噺の一つ。 別名は「唐茄子屋」。
上方では「南京屋政談」、「南京政談」、「なんきん政談」と呼ばれる。 東西では少し内容が違っていたりする。
大店の若旦那が遊びをすごして勘当される。
こういうテーマは江戸時代からたくさんあるが、その後の展開はさまざまだ。
この咄の場合はカボチャを売ることになった。
江戸時代に野菜の種類がぐんと豊富になるが、それはこのカボチャをはじめとして新大陸やアジア方面から新しい野菜が次々ともたらされたからである。
このひときわ重い野菜を売る苦労をして、徳さんはかつて出入りしていた華やかな吉原とは別の世界を、浅草で発見することになる。
それは浅草寺の西に位置する誓願寺のはずれ、東本願寺の北側の石塀に沿った「誓願寺店」という貧しい地帯であった。
江戸時代も明治以降も、浅草は華やかで賑やかな繁華街であるとともに、苦しい生活をしている人たちの生活の場でもあったのだ。
徳さんは勘当されたことで、世間の深みを知るのである。
出典: 『TBS落語研究会』
【あらすじ】
遊びすぎて、”お天道様と釜の飯は付いてくる”と自ら勘当された若旦那”徳”は最初の内は良かったが、その内誰にも相手にされなくなった。
雨も上がって吾妻橋までさしかかり欄干から飛び込もうとするところを、たまたま叔父さんに助けられた。
何でもするからと、達磨横丁の叔父さんの家に連れられていった。
おばさんに挨拶して食事もすむと疲れがどっと出て、死ぬ様に眠った。
翌朝、叔父さんに起こされ、今日から「唐茄子」を売り歩けという。
みっともないから・・と言うと、さとされ天秤を担いでヨロヨロしながら長屋を出ていった。
アミダになった傘も直せず、天秤にしがみついて歩いていたが、吾妻橋を渡って田原町に来た時にはたまらず、荷を投げ出して倒れてしまった。
親切な住民が手分けして買ってくれた。
残った二つを担いで歩き始めたが売り声も出ない。
吉原脇の田んぼの中で売り声の練習をしながら、道楽三昧の日々を思い出していた。
声も出る様になって、誓願寺店に入って来ると、質素だが品のいい奥さんに声を掛けられ、売り切った。
弁当を使わしてくれと頼んで食べ始めると五つ位の男の子が「おまんまだ!」と言って離れない。
事情を聞くと亭主の送金が無く買う事も出来ずに、困っていると言う。
ひもじいのはよく分かると、子供に弁当をやって、売り上げを全部渡して振り切る様にして戻ってきた。
完売した事に叔父さんも喜んでくれた。食事の出る間、顛末を聞いていたが、売り上げを見せろと言うが無い。
誓願寺店で親子に弁当とお金を全部上げたというと本当ならイイが、これから行こうと提灯を持って立ち上がった。
誓願寺店に着いてみると、長屋では大騒動。
話を聞いてみると、あげたお金を因業大家が全部、店賃として取り上げてしまったので、奥さんが悲観して首をくくってしまった。
徳は感極まって大家の家に怒鳴り込んで、やかん頭にやかんで殴りつけ、溜飲を下げた。
奥さんは医者に診てもらい、寿命があったと見えて助かり、叔父さんが親子を引き取り暮らした。
収まらないのは徳さんで、自分が行かなければ奥さんは助からなかっただろう。
この事を奉行に願って出た。
裁きの結果、大家はきついおとがめ、徳さんは人助けをしたとして、青差し十貫目の褒美をもらい、勘当が許されたという。
”情けは人の為ならず”唐茄子屋政談の一席。
出典: 『落語の舞台を歩く』
【オチ・サゲ】不明
【語句豆辞典】
【唐茄子】カボチャのこと。地域によって呼び名がいろいろあり、唐茄子のほかナンキンと呼ばれる。
【半纏(はんてん)】庶民が愛用した、羽織に似て丈の短い上着。
【股引(ももひき)】江戸っ子はモモシキという。ズボンを細くしたようない退く出、下着と作業衣がある。
【誓願寺店(せいがんじだな)】後半の舞台になる誓願寺店は、現在の台東区元浅草四丁目にあたり、旧東本願寺裏の誓願寺門前町に実在した裏長屋。
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『傾城の恋は誠の恋ならで、金持って来いがほんの恋』
『後悔を先に立たせて後からみれば、杖をついたり転んだり』
『菜の花や向こうに蝶の屋根が見え』
『玉の輿乗りそこのうてもくよくよするな、まさかみそこしゃさげさせぬ』
【この噺を得意とした落語家】
・五代目 古今亭志ん生
・六代目 三遊亭圓生
・三代目 古今亭 志ん朝
・四代目 桂福団治
【落語豆知識】 上下(かみしも)
落語演出の基本。客席から見て右が上手(かみて)左が下手(しもて)。
噺す向きを変える事で登場人物を描き分ける。