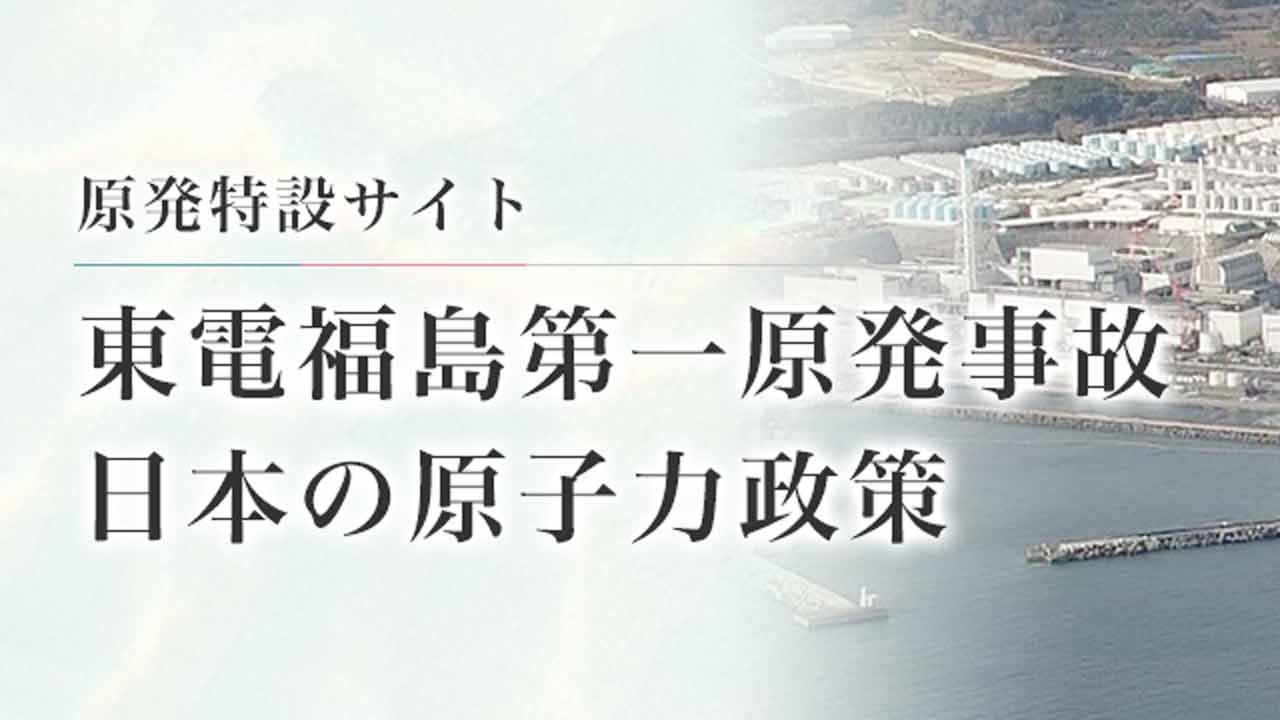3月11日。鎮魂の日の朝は心静かに迎えたいといつも思う。東の空が明るみ始めたら目を閉じて祈ろう、今年はまた少し顔を上げてみようと。ふくしまは今、落ち着きを取り戻している。
しかし、その日が近づくと、10年前のように感情が高ぶってくる。途中の記憶はすでに薄れたのに。あの日、果てしなく続くかと思われた揺れの後、多くの命が失われた。ほどなく海が巨大な壁になって押し寄せ、もっと多くの命をのみ込んだ。放射性物質の恐怖が人々を追い立てた。寒さと苦痛と余震の恐怖に顔がゆがんだ避難所、息苦しい仮設住宅暮らし、先の見えない不安と疲労と絶望の果てに、さらに多くの命に終止符が打たれた。
追悼すべきは記録された犠牲者4151人だけではない。復興への闘い道半ばで倒れた人、帰郷がかなわないまま逝った県人、家族同然の生き物たちも葬らざるを得なかった。200万県民の誰しもが味わった悔しさは、怒りに変わった。
東京電力福島第1原発事故の被災者は一日千秋で待った一時帰宅で、獣と盗賊に荒らされた家に驚き、防護服と土足で踏む畳に涙した。中通りの子育て家族は、放射線の専門家が泣き叫び識者が悲観論をあおる中で、逃げるかとどまるか、苦渋の選択に泣いた。会津の観光地は人出がぱったり止まり静まり返った。もう10年か、まだ10年か。心の奥にしまった怒りが、廃炉作業トラブルや閣僚・官僚の心ない発言の度に一気によみがえる。東電と政府は、県民の複雑な感情を侮ってはならない。
マイナスから始まった復興
原子力災害からの復興はマイナスからのスタートとされる。ゼロから復旧を図る自然災害と違い、原発事故は火口ほどもある大穴を手仕事で埋め戻すような辛苦を県民に強いた。
それでも、ふくしまはここまで来た。県土の12%を占めた避難区域は2.4%に減った。帰還困難区域以外の人里の空間放射線量は毎時0.1マイクロシーベルトを切る水準で、世界の主要都市を下回るほどだ。往来が認められたJR双葉駅前は毎時0.27マイクロシーベルトまで下がり、除染で目指す毎時0.23マイクロシーベルトに迫る。最大16万人台を数えた避難者は記録上は3万人台までになった。帰還困難区域を除けば、ごく普通の生活ができ、子どもたちの笑顔にも会える。
10年前、ここまで回復できると確信できた人は少なかったはずだ。大人たちは本当によく頑張った。農家は産品から放射性セシウムが検出できないほどの安全性を実現し、先端技術農場やワイナリーなど新たな挑戦も続く。地震で寸断された道路網は格段に向上し、ロボットテストフィールドや水素製造拠点など産業基盤の整備も進んだ。県民は互いに奮闘をたたえながら、胸を張ろう。
全国から駆け付けた警察官や応援職員は異郷の住民に寄り添い支え続けた。廃炉作業員や除染作業員は荒れた大地を整えてくれた。国内外からの声援は人々に力を与えた。感謝の言葉しかない。
溝を埋める努力続けよう
2021年3月11日午後2時46分。私たちは新たな10年を迎える。健やかに成長した子どもたちが加わり、新たな世代が課題への挑戦を始める。
大きな穴が埋まったわけではない。原子力災害は、家族のつながりと地域コミュニティーを分断する最大の罪を犯した。しかも現在進行形だ。再起し前進する人と、自立できず心に痛みを抱えたままの人との格差を広げ続けている。行政は、立ち上がれない人を個人の問題と片付けてはならない。私たちも溝を一つ一つ埋める努力を続けよう。
誤解や偏見が強い痛みを与えることを、ふくしまの人は知った。その教訓はコロナ禍にも生きる。私たちが石を投げてはいけない。「励ましの社会」を実現していこう。
自分だけ良ければいいという考えは厳に慎みたい。中間貯蔵施設を受け入れてくれた大熊、双葉両町の住民の痛みをわがこととして考えようと、多くの識者が取材に答えてくれた。では、福島第1原発でたまるトリチウムを含む処理水はどうか。科学的、現実的な方法と向き合ってはいけないか。それが汚染土壌の2045年県外搬出や、廃炉の前進につながるはずだ。
国内流通業界もしかり。放射線を正しく理解する最前線に立ってほしい。県産品には、もはや風評はないという指摘がある。あるのは消費者心理を過剰に推測して県産品を棚から外す流通業界の誤った判断だと。民間ならではのスピード感をもった方針転換を願う。
政府と東電は当事者意識を
東電は、ふくしまを最優先で考えなければならない。被災地での謝罪がパフォーマンスと化していないか。組織が緩んでいないか。廃炉の確実な前進と、隠蔽(いんぺい)を疑われない社内体質への転換しか、失った信用を取り戻すすべはない。原子力技術者の先細りをどう克服するか、業界を挙げた対策も講じる時に来ている。
政府はこの10年間、「知恵を出した被災地を支援する」と言い続けた。勘違いは困る。原発事故は加害者のいる災害だ。加害者たる政府と東電は「上から目線」でなく、当事者意識を高めてほしい。
福島民友は被災者の「自立」と「自律」を訴えてきた。復興予算の使途も同様だ。しかし、霞が関省庁間で予算削減論が活発化していると聞けば「時期尚早」と叫びたい。ふくしまは、ようやくゼロの一歩手前まで来たばかり。帰還困難区域には荒れ果てた地域が、まだ広がっている。人が戻らなければ無駄という発想を捨て、中長期の視点で大地の浄化を考えてほしい。古里再生が住民に夜明けを告げる。世界に名をはせた「ふくしま」が日本の宝として輝きだすと、私たちは信じる。