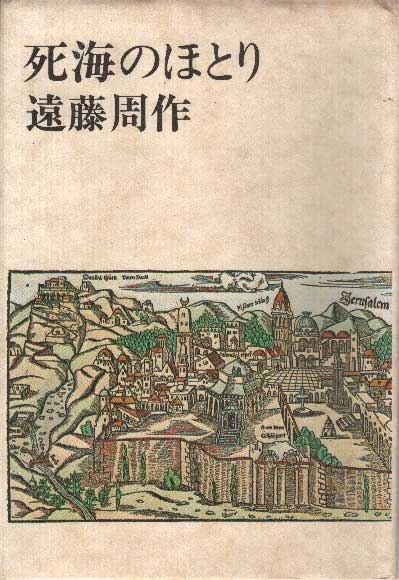「MASTER KEATON」を探しに古本屋に行ったとき、店頭によりどり3冊200円という札のついたかごがあった。興味本位でのぞいて見ると、遠藤周作の「死海のほとり」というハ-ドカバーの本が目についた。来年、ヨルダンへ行く予定があるので、読んでみようと手にとった。
遠藤周作が洗礼も受けたクリスチャンで、イエスと向き合っていることは以前から知っている。ということは、内容は死海のほとりでもイスラエル側だな、とは思った。
主人公の小説家はエルサレムを訪ね、エルサレムに住んでいる聖書学を研究している友人に連れられてエルサレムや死海のほとりを巡礼する。
そこに戦時中、クリスチャンが白い目で見られた彼らの学生時代の思い出がかぶる。学生寮にいた二人の神父と修道士、ねずみとあだ名され、姑息に生きていた修道士がユダヤ人強制収容所にいたことを追って、忌まわしい収容所につながる。巡礼と群像という二つの物語が交互に、まったく違った時間ながら、イエスその人を浮かび上がらせる。
現代から見たイエス、これはストレートに私にも入ってくる。イエスの生きていた周りの人間、ごく身近でない群像の一人にイエスをどう見ていたかを語らせ、それぞれの立場とメシアに求める人間の弱さ、勝手さを描いている。群像の方は重くて、読んでいて胸が痛くなる。
作中、聖書研究家の友人が聖書のナゾだという、イエスが生きているとき、弟子たちはイエスを見捨てた。その彼らがイエスが死んでからどうして立ち上がったんだろう、という件。ここは命題だな、それは復活であり、これこそが信仰なのだろう。
私は私なりにキリスト教を学んだので、イエスが本質的に愛の人であったことは理解している。イエスは聖書に書かれているようなスパースターではなく、心底人を愛する人だったのではないか。クリスチャンの彼と無宗教の私とは意外に接点がある。突き放したように書いている遠藤周作に、「あんた、イエスを捉えているよ。なによりもイエスを深く愛している」」と思わずうなってしまった。
イエスの処刑、刑場にいた群像の一人、ねずみのガス室送り、そこではなんの奇跡も起こらなかった、しかしその向こうに存在していたものは・・・。
もう少し突っ込んでみよう。彼の「イエスの生涯」を買って来よう。 今頃になってからだけど。