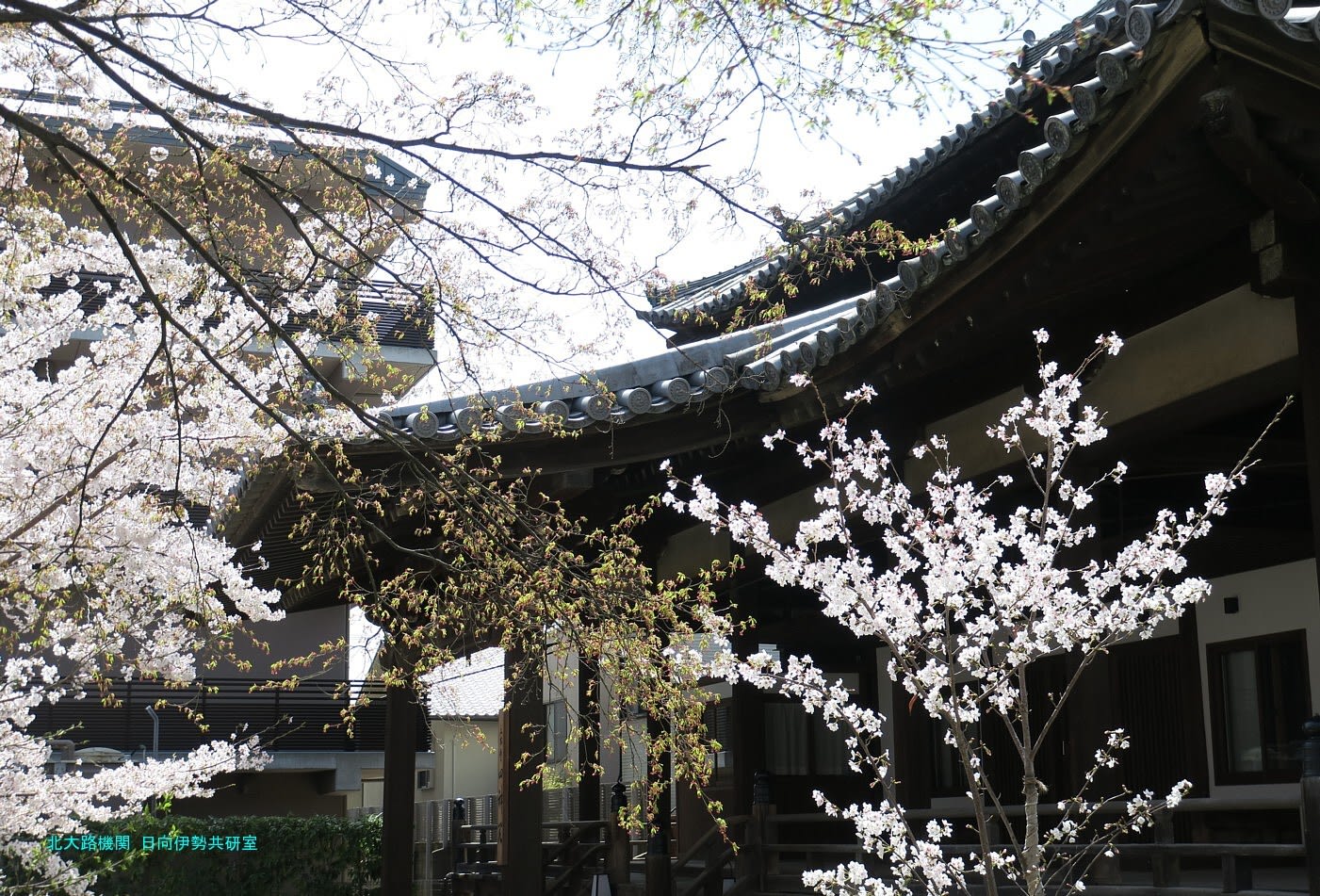■航空祭大団円
岐阜基地航空祭も大団円へ向かう。

ブルーインパルスの飛行展示もいよいよ最終盤にはいってきます、いろいろありましたが航空祭名物お化粧室渋滞に巻き込まれて一時はブルーインパルス撮影も難しいかと危惧したのですが、まあ、何とかなったということで由としなければならない。

垂直系の展示飛行は曇天では視界不良により中止されてしまいますから、それでもまわりから、わあっ、というような歓声が上がる様子とともにT-4練習機の限界を示す最大限の飛行展示をみていますと、航空祭が日常に戻ってきたことを実感できるのだ。

航空祭というのは天候に左右されるのだなあ、ということは毎回知識として走っているのですけれども、曇天の航空祭でも苦い経験はいつしか上書きされて快晴の航空祭という記憶がのこるものでして、しかし改めて曇天の航空祭を探訪しますと、ああ。

曇天、南側会場は順光というのが売りなのだから、滑走路回って曇天のままだと残念な気分となるのですが、それでも人口密度はメイン会場ほど凄いことにはなっていませんので、ほぼほぼ最前列を確保できましたが、メイン会場の混雑は凄いですよね。

岐阜基地航空祭、実のところ航空祭全般にいえることなのですけれども、ブルーインパルスが飛行展示を行う場合は、ざっと四万から五万ほど来場者が増える、という印象です。一万の誤差は周辺人口により左右されるというところなのですけれども。

混雑の度合いは、南側会場からも有る程度みえていました、滑走路に着陸した航空機と管制塔やメイン会場の地上展示航空機を構図に含めて航空祭らしさを演出しようとしますと、おお混雑が凄いんだなあ、というのはと梅にもわかりますから。

滑走路脇の最前列、というものをこのメイン会場で狙いますと、それはもう大変なことになるのですが、岐阜基地と小牧基地、日常的に撮影する基地の場合は無理に最前列へ行かずとも後ろのほうから撮影すると、混雑している航空祭、という情景が。

満員御礼、そんな言葉がありますが実際のところここまで混雑していると、いろいろな視点を通り越してもはや潔い、いや心地よいなんていう情感がわき起こります、けれども地上展示航空機を撮影するにはここを横断しなければならないのだなあ。

T-4練習機の続々と着陸する様子を望見する。岐阜基地航空祭はなにが公開されているのか、地上展示のなかにXASM-3やJDAMなんかが初公開された場所が岐阜ですから、地上展示をしっかり撮影しなければ後々に、出ていたのか、と驚き残念に思うことも。

格納庫のなかを順番にみてから、そして航空機の方をみるか。あまりのんびりしていると格納庫の一般公開が終わってしまうけれども、問題はこの観衆をかき分けて移動するのは難しいので混雑していない側を、凪をみて撮影に移動することかなあ。

岐阜基地航空祭、基地の規模としては巨大すぎるものではないのですが、なにしろ見所が覆い基地ですし、それ以上に滑走路の北側と南側を移動できる航空祭というのはそれほど多くありません、それでいて南北とも見所がおおいだから忙しい。

航空祭は体力を使うのですけれども、配備されている航空機の種類も多いものですし、異機種大編隊というここでしかみられない展示もありますから、帰路にいっぱいやりに寄ってみてグラスを片手に写真をカメラでみるだけでも、達成感を感じられるのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
岐阜基地航空祭も大団円へ向かう。

ブルーインパルスの飛行展示もいよいよ最終盤にはいってきます、いろいろありましたが航空祭名物お化粧室渋滞に巻き込まれて一時はブルーインパルス撮影も難しいかと危惧したのですが、まあ、何とかなったということで由としなければならない。

垂直系の展示飛行は曇天では視界不良により中止されてしまいますから、それでもまわりから、わあっ、というような歓声が上がる様子とともにT-4練習機の限界を示す最大限の飛行展示をみていますと、航空祭が日常に戻ってきたことを実感できるのだ。

航空祭というのは天候に左右されるのだなあ、ということは毎回知識として走っているのですけれども、曇天の航空祭でも苦い経験はいつしか上書きされて快晴の航空祭という記憶がのこるものでして、しかし改めて曇天の航空祭を探訪しますと、ああ。

曇天、南側会場は順光というのが売りなのだから、滑走路回って曇天のままだと残念な気分となるのですが、それでも人口密度はメイン会場ほど凄いことにはなっていませんので、ほぼほぼ最前列を確保できましたが、メイン会場の混雑は凄いですよね。

岐阜基地航空祭、実のところ航空祭全般にいえることなのですけれども、ブルーインパルスが飛行展示を行う場合は、ざっと四万から五万ほど来場者が増える、という印象です。一万の誤差は周辺人口により左右されるというところなのですけれども。

混雑の度合いは、南側会場からも有る程度みえていました、滑走路に着陸した航空機と管制塔やメイン会場の地上展示航空機を構図に含めて航空祭らしさを演出しようとしますと、おお混雑が凄いんだなあ、というのはと梅にもわかりますから。

滑走路脇の最前列、というものをこのメイン会場で狙いますと、それはもう大変なことになるのですが、岐阜基地と小牧基地、日常的に撮影する基地の場合は無理に最前列へ行かずとも後ろのほうから撮影すると、混雑している航空祭、という情景が。

満員御礼、そんな言葉がありますが実際のところここまで混雑していると、いろいろな視点を通り越してもはや潔い、いや心地よいなんていう情感がわき起こります、けれども地上展示航空機を撮影するにはここを横断しなければならないのだなあ。

T-4練習機の続々と着陸する様子を望見する。岐阜基地航空祭はなにが公開されているのか、地上展示のなかにXASM-3やJDAMなんかが初公開された場所が岐阜ですから、地上展示をしっかり撮影しなければ後々に、出ていたのか、と驚き残念に思うことも。

格納庫のなかを順番にみてから、そして航空機の方をみるか。あまりのんびりしていると格納庫の一般公開が終わってしまうけれども、問題はこの観衆をかき分けて移動するのは難しいので混雑していない側を、凪をみて撮影に移動することかなあ。

岐阜基地航空祭、基地の規模としては巨大すぎるものではないのですが、なにしろ見所が覆い基地ですし、それ以上に滑走路の北側と南側を移動できる航空祭というのはそれほど多くありません、それでいて南北とも見所がおおいだから忙しい。

航空祭は体力を使うのですけれども、配備されている航空機の種類も多いものですし、異機種大編隊というここでしかみられない展示もありますから、帰路にいっぱいやりに寄ってみてグラスを片手に写真をカメラでみるだけでも、達成感を感じられるのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)