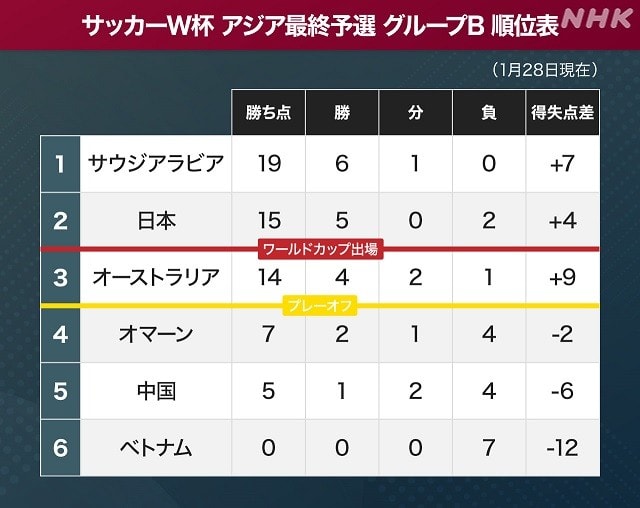残念!というだけではない。光がはるか遠くにしか見えない敗戦だった…。対戦した信州ブレイブウォリアーズの3Pシュートに成す術なく敗れ去った印象だった。懸命に戦うレバンガ北海道の選手たちに光は見えるのか?

※ きたえーるの会場の様子を魚眼レンズ風に撮ってみました。
昨夜、3月9日(水)夜、北海きたえーる(北海道立総合体育センター)で行われたB1リーグ、レバンガ北海道 vs 信州ブレイブウォリアーズの一戦を観戦した。

※ 試合前、レバンガ北海道の代表、折茂武彦氏に協賛企業からの寄贈がありました。
“スポーツは生もの” というのは私の造語だろうか?スポーツの結果は時間が経つにつれてニュース性が落ちてくることから私はそう呼んでいるのだが…。したがって、時系列的には一昨日夜のコンサートを先にレポすべきだが、敢えて昨夜のバスケットボールB1リーグの一戦をレポすることにした。

※ レバンガ北海道 対 信州ブレイブウォリアーズのテイップオフの瞬間です。
レバンガの21番ロング選手がジャンプしています。
対戦の結果は次のとおりである。クォーター(Q)別の両チームの得点を示すと…、(先に記すのが北海道の得点である)
第1Q 23 ― 29 第2Q 28 ― 18 第3Q 24 ― 28 第4Q 22 ― 22
試合全体の結果は 《北海道 94 ― 103 信州》
バスケットボールにおいて相手チームに3ケタ得点を許すということは、守備が機能していなかったということになるそうだが、まさにこの試合は相手にいいようにやられたといった印象だった。

※ バスケットボールの試合会場は非常に華やかなのが特徴の一つです。
象徴的だったのは第1Qの信州の攻撃だった。信州の77番岡田選手が放つ3Pシュートがことごとくゴールに吸い込まれるのを私は唖然として観ていた。結果的に岡田選手は7本の3Pシュートを決め、計34得点を記録した。岡田選手の動きを見ていると、絶えず3Pシュートを狙っているような位置取りをしていた。対する北海道に3Pシューターという役割の選手は見当たらなかった。試合経過を見ると、北海道は第2Q終了時点でこの試合で唯一リードして終えた。この第2Qでリードできた一つの要因は岡田選手が狙った3Pシュートの何本かを落としたことがその要因と思えた。信州の強さは岡田選手だけではなく、熊谷というPGの動きも鋭く、彼もチーム2位の14得点を記録していた。つまり信州は北海道同様に助っ人外国人もいるのだが、彼らに頼ることなく試合を運んでいた点にあるように思えた。

※ この日入場者に配られた折茂武彦選手(?)の引退試合を記念するユニフォーム(背番号9番)を着用して観戦する観客です。(私もいただきました)
一方、北海道は助っ人外国人頼りのチームに思えた。得点を見てもロング、ブルックスの二人に頼っり切っているかのようだった。ロングが44得点、ブルックスが16点と二人で60得点とチームの得点のおよそ2/3を占め、日本人選手で二けた得点はゼロだった。この差が大きすぎた。

※ 今シーズンからヘッドコーチに就任した佐古HCです。(立位の左側)
この日の敗戦で北海道は今季12勝22敗となり、東地区11チーム中で第8位と低迷している。レバンガ北海道は今シーズンだけではなくここ数年いつも下位に低迷している。このことに関連してたまたま昨日、レバンガ北海道の代表を務める折茂武彦氏(元レバンガの代表的選手)が北海道新聞に寄稿していた。それによると、資金的に豊富なチームは優秀な選手を獲得することが容易なためにどうしても上位を占める傾向があるという趣旨のことを寄稿していた。(このことを折茂氏は言い訳的に述べていたわけではない)私は同じような言葉をコンサドーレ札幌の前社長の野々村芳和氏から何度も聞いたことがあった。だから「あゝ、プロバスケットにおいてもプロサッカーと同じような事情なのだなぁ」と思いながら読んだ。北海道は残念ながら大企業などは皆無で大きな資金的援助を得ることが難しい地域事情がある。折茂氏を先頭に企業としてのPR活動にも力を入れていると聞く。とても厳しい環境下にあることは承知の上だが、成功の道を歩みつつあるコンサドーレのように地道な努力を積み重ねていただき、将来には力量の優れた選手を呼べるくらいの球団に成長してもらいたいと思う。

※ 試合結果を表示するスコアボードです。

※ 敗戦に肩を落とすレバンガ北海道の選手たちです。
視点は変わるが、北海道に3Pシューターが不在、という点についてである。東京五輪で日本女子バスケットチームが銀メダルに輝いた要因は積極的に3Pシュートを狙いに行った点にあると聞いている。ことほど左様に、現代のバスケットにおいて3Pシュートは昨日の試合のように試合結果を左右するほど重要な戦術となっているようだ。バスケットボールの観戦の醍醐味は、厚い守備網をかいくぐり突破したり、素早いバスを通したりしてのゴールシーンが何より観ていて楽しく醍醐味を感ずる。それに比して3Pシュートは鮮やかさこそあれ、醍醐味のようなものを感ずることはできない。しかし、ルールの上では1ゴール3点を得ることができるプレミアムなプレーである。レバンガ北海道が光を見出すためには3Pシューターの発掘が急務であるように思える。しかし、信州の岡田選手のようなシューターはそうそう簡単には育てることは難しい注文なのかもしれない。あの正確性は選手の資質的なもののような気がしているからだ。だから 3Pシューターは育てるのではなく、スカウティングで発掘するか、資金的に豊富になって3Pシューターを移籍で獲得することを考えるか、ではないだろうか?現代バスケットボールのおいては確率の高い3Pシューターがチーム内にいるか否かはチーム成績を左右する大きな要因となるのではないか、ということを昨日の試合を観ながら考えていた私だった…。