時代の幸運、出会いの幸運、そして何より彼自身の不屈の精神力、そうしたことが相まって大黒屋光太夫は歴史の人となった。史実を丹念に探し、掘り起こし、吉村昭の抜群の筆力で読者を惹きこみ一気に読み進むことができた。
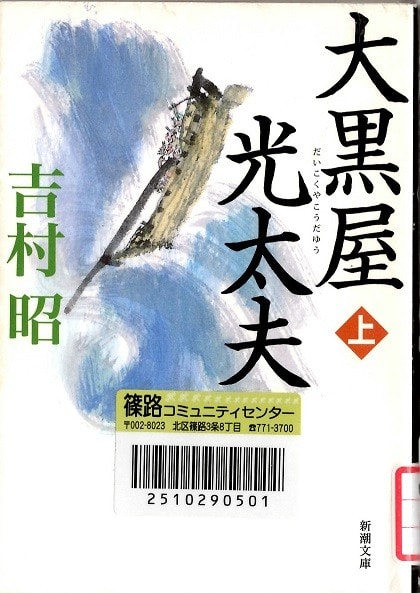
大黒屋光太夫とは、伊勢国白子浦(現在の三重県鈴鹿市白子町)の廻船問屋が所有する「神昌丸」の沖先導(船長)だった。天明2(1782)年12月13日、光太夫32歳の時、「神昌丸」は米・酒をはじめたくさんの荷物を満載して白子浦から江戸へ向かった。ところが大しけに遭遇し、船は漂流しておよそ一年後に流れ着いたのは当時ロシア人が支配していたアリューシャン列島のアムチトカ島だった。ここから光太夫の本当の苦難が始まるのだが、漂流中、そしてアムチトカ島で白子浦から出た時は17人だった船員などは病気によって、この時点で8人を亡くしている。
何としても故国へ帰りたいという光太夫たちはアムチトカ島からカムチャツカ半島、樺太島のはるか北方の寒村オホーツク、そしてヤクーツクを経てイルクーツクに至る。この間、まったく未開の大地を往く光太夫たちの苦労は想像を絶するものであった。その上、シベリアの冬の寒さは尋常ではなかった。仲間の一人はその寒さのために片足を切断しなければならないほどだった。また、光太夫たちは彼ら以前にも漂流してシベリアに流れ着いた日本人がいたことを知った。それらの日本人は望郷の念に駆られながらもロシアの政策によって帰国は許されず、日本語教師として一生を終えるものばかりだったことを知る。
光太夫たちが幸運だったのは、イルクーツクでキリロ・ラクスマンという陸軍中佐で、鉱物の知識が豊富な学者であり、ロシア皇帝の信頼もあつい高官と出会ったことである。キリロは光太夫たちの帰国の思いが強いことを知り、親身になって光太夫たちの世話をかつて出てくれた。その際たることは帰国を皇帝に直訴するためにキリロが光太夫を私費で帝都ペテルブルクまで同道したことである。イルクーツク⇒ペテルブルク間はロシアの里数で5,823里だそうである。私が計算したところ現在の距離数で約6,200kmということになる。この間を馬車で約1ヵ月余走り続けて到達したということだから、いかなる大旅行だったかが窺い知れる思いである。ベテルブルクにキリロと光太夫は約1年間滞在した末に、キリロの粘り強い交渉の結果、光太夫はついに女帝エカテリーナとの会見が実現したのだった。当時ロシアは日本との通商を行いたいという国策もあって皇帝はその感触を探る意味からも光太夫たちの帰国を認めたのである。
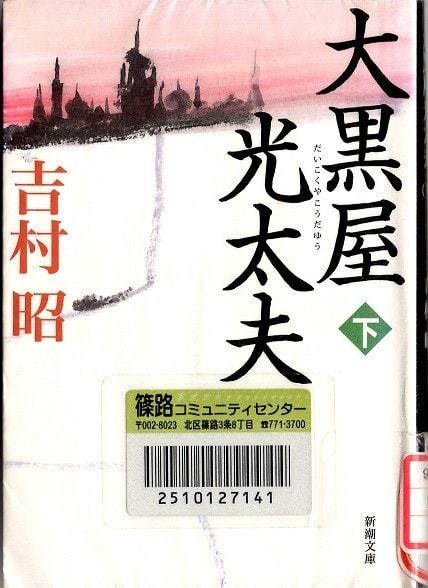
光太夫の絶対に帰国するという硬い意志、キリロという得難い人物との出会い、そしてロシアの対日政策の変換、といったことが積み重なったことで、ついに光太夫は寛政4(1792)年9月3日、根室の近く西別の浜に帰国の一歩を記したのだった。その間、漂流してから実に10年の月日が流れていたのだった。
実はアムトチカ島で多くの仲間を失った光太夫だったが、その後も病没した者、あるいは帰国を諦めてロシアの教会で洗礼を受けたことで帰国の道を自ら閉ざした者も2人いた。そうしたことで結局帰国できたのは漂流した17人のうちたったの3人だけだった。その3人の中の1人も北海道(当時の蝦夷)に辿り着いたものの、家族との再会も叶わず病死してしまい。結局、本当の意味で無事に帰国できたのは、光太夫と磯吉という若者の二人だけだった。
ずーっと粗筋のようなことを紹介する文章となってしまった。それも私自身がこの壮大な叙事詩のような物語を反芻してみたいとの思いが強く、いつもの感想文的文章とは異なってしまったことをお断りしておきたい。
う~ん。吉村昭という作家の読者をぐいぐいと惹き付ける筆力には改めて恐れ入る思いである。私の吉村昭詣ではまだまだ続く…。









