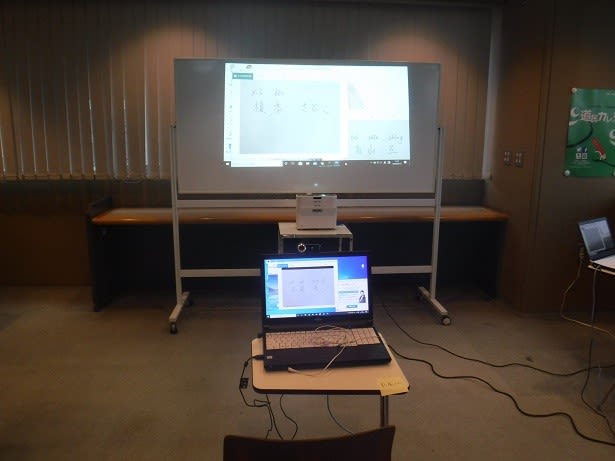復路の「新川緑地」は往路の対岸である。それほど大きな差はない。ゴールの西陵橋に向かって黙々と歩くだけだったが、よ~く目を凝らしてみると、右岸独特の光景も見えてきた。

※ 右岸の散策路の一部には写真のように化粧タイルで舗装された休憩所もありました。
新 川 緑 地 238,083㎡(ドーム約4.5個分)

新川の左岸沿いには手稲区の住宅街が広がっている。対して復路とした右岸はまだ住宅地としては開発されていないところが多く、「前田森林公園」が目立つ程度で閑散とした光景が広がっている。(もっとも、西陵橋が近づいてくるにつれて右岸にも住宅は目立ってくるが…)したがって、散策路を行き交う人も左岸に比べるとグッと少なくなった。

※ 新川の最も石狩湾に近い位置に架かっている「第一新川橋」です。

※ 「第一新川橋」は道央新道が走る幹線のため交通量も多いのが特徴です。
右岸の散策路でまず気が付いたのが、左岸はアスファルト舗装だったのに対して、右岸にはレンガ風焼成ブロックが敷かれてあったことだ。見た目には焼成ブロックの方がいかにも歩くのが楽しくなる雰囲気がある。ところが長い時間が経つと、ブロックを敷いた隙間から雑草が顔を出してくるのだ。右岸の散策路もブロックを敷いた両側から雑草が進出し、人が独り歩く幅程度しかブロックが顔を出していないところがあった。そういえば「あいの里緑道」の場合も同様だった。散策路の舗装をどうするか?考えるべき問題かもしれない。

※ 右岸の散策路は写真のようなレンガ風焼成ブロックが敷かれていたのですが雑草が目立ち、人が通る幅しかブロックが見えません。

※ 本来は幅1.5mくらいにブロックが敷かれているのですが…。
次に、右岸には樹木の少なく河川敷が広がったところがあった。そこには一面にタンポポが咲き誇っていた。しかし傍によってよく見ると、それは私たちがタンポポと言っているものとは違っていた。茎が空洞状ではなく、針のように細く固い茎なのだ。帰宅して調べてみると、それはどうやら「ブタナ」というタンポポモドキの種だった。しかし、一面に咲き誇る様子は壮観だった。

※ 一見タンポポと見えたのですが、正式名は「ブタナ」という外来植物(?)でした。

※ ブタナを大写ししたものです。
花と言えば、一本だけ高くそびえていたニセアカシアが木全体に白い花をいっぱいに付けた様子も豪快だった。

※ ご覧のようにニセアカシアの大木には白い花がびっしり付いていました。
堤防の法面に掲げられた子どもたちの壁画は右岸にももちろんあった。壁画が飾られたある一帯は緑地の造成当時にちょっとした公園風に造られたようだ。壁画の周りは花壇風になっていた。また辺り一帯も花壇のようなものが2~3あったが、いずれもが雑草に覆われていたのが残念だった…。

※ 右岸にも子どもの壁画が掲示されていました。周りにシバザクラが配されています。

※ 同じ所には写真のような花壇が配されていたのですが…。
向かいの左岸から見たとき、堤防の法面の雑草が刈り取られているように見えた、と書いたが、実際に傍に寄ってみると業者がきれいに刈り取った跡が見て取れた。やはり雑草が刈り払われた後は気持ちの良いものである。

※ 右岸の堤防法面はご覧のように雑草が刈り取られていました。

そんなあれこれを目にしながら、やはり復路も2時間近くかかってスタートした西陵橋に還ってきた。

※ スタートした地点の西陵橋に還ってきました。
「新川緑地」の河川敷(散策路)を往復しての印象だが、「中の川緑地」のときも感じたことであるが、私の印象では「緑地」というよりも「緑道」というイメージが強かった。ことほど左様に「都市緑地」とは、さまざまな働き、役割をもったものを総称する名称なのかな?と思えてきた。