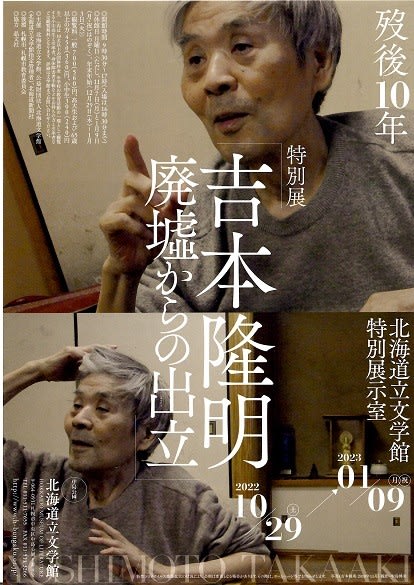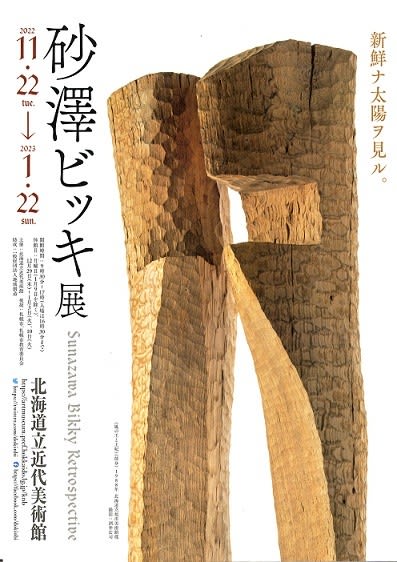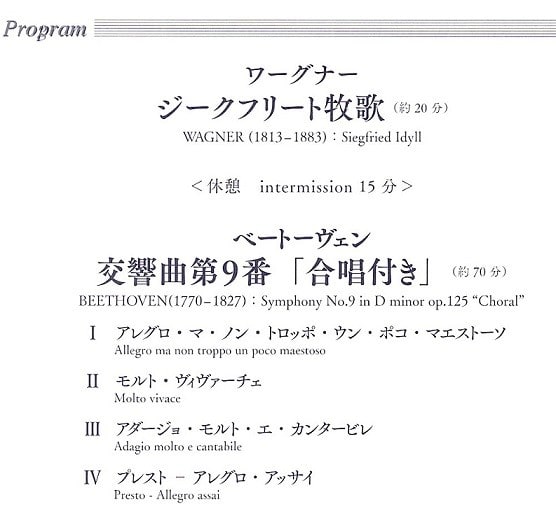大きな空が懐かしかった…。青い海が懐かしかった…。13年前に僅か3日間の滞在だった与那国島だが、その時の思い出がスクリーン上で鮮やかに蘇った。しかし、それよりもヒューマンなストーリーは映画の醍醐味を十分に堪能させてくれた2時間半だった。

昨日、12月20日(火)午後、映画「Dr.コト―診療所」が上映されている札幌シネマフロンティアに足を運んだ。話題の映画の封切直後(12月16日公開)とあって、平日にも関わらずかなりの観客で客席は埋まっていた。
「Dr.コト―診療所」はTVドラマとして人気だった作品だが、TVドラマの放送が終わってから16年ぶりに映画で復活するということで話題となっている映画である。私は基本的にTVドラマは観ない方なので、TVの「Dr.コト―診療所」もほとんど観ていない。ただ、与那国島の旅から帰って再放送分を多少観た記憶はあった。

映画の出演陣は主演の吉岡秀隆、柴咲コウをはじめ、ほとんどの出演陣が同じということも話題を集めている。吉岡秀隆や時任三郎が白髪交じりとなっていたところに16年の年月を感じさせられたが…。またTVドラマで子役の原剛洋役を演じていた富岡涼は、その後芸能界を引退していたのだが本作に限って復帰したことも話題となっていた。
映画はDr.コト―(吉岡秀隆)が20年前に赴任した志木那島で相変わらず離島の医師として島民の健康を守っていた。ただ16年前と変わったのはDr.コト―が診療所の看護婦だった彩香(柴咲コウ)と結婚し、彼女が身籠ったというところからスタートし、そこからさまざまな話題が展開するというストーリーだった。
さて、映画の舞台となった「志木那島」とは架空の島で、実際は日本の最西端に位置する「与那国島」をモデルとして、実際に与那国島でロケされた映画である。その与那国島に私は13年前の2009年にわずか3日間だけだったけれど滞在した体験があり、そのTVドラマで使われた診療所の建物が与那国島の比川地区に残されていたのを見学もしていた。私の与那国島の旅はとても刺激的な旅だったので非常に濃く記憶に残る島なのだ。しかし、そのことを語るのが本旨ではないので触れないが、映画に映し出されるシーンの一つ一つがとても懐かしかった。

映画はさまざまな要素が含まれる内容だったが、主題は離島においてDr.コト―の厚意に頼らねばならない医療体制の貧弱さを問うものだったと私はみた。そのことを本作で始めた登場した研修医役の高橋海人(King & Princeのメンバーの一人)が指摘する演技がなかなか好演だったと私には映った。
映画レビューを覗いてみると、TV版「Dr.コト―診療所」の熱烈ファンが多く投稿していたようだが、期待が大きかっただけにやや厳しめの批評が多く感じたが、私には脚本の確かさ、吉岡秀隆をはじめベテランの方々の演技の巧さが相まって十分に楽しむことができた映画だった。また映画の終末もDr.コト―の運命がどうなったのかを、観ている者に委ねたところも、私には「なるほど…」と思わせるものだった。

比川の穏やかな海辺、久部良の活気ある港、西崎(いりざき)の荒々しい断崖、東埼(あがりざき)の与那国馬が草を食む草原、そしてDr.コト―が自転車で往診に駆け回る与那国島の広々としたサトウキビ畑…。そのどれもが私の目には懐かしく、懐かしく映った映画「Dr.コト―診療所」だった…。
※ 掲載した写真は全てウェブ上から拝借したものであることをお断りします。