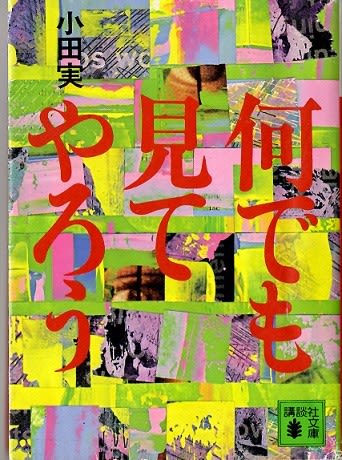「冬を迎えて彫刻、モニュメント巡りもないだろう」との突っ込みを入れられれば、その通りなのだが…。実は訳あって雪を被った彫刻やモニュメントを巡り歩いた。思わぬ新発見もあった。
雪を被った彫刻を見て歩いた訳とは?
拙ブログに時折り登場する「めだかの学校」では、現在来年度の学習計画の立案作業が渦中を迎えている。いろいろとアイデアが出ているのだが、その中の一つとして昨年、一昨年とコロナ禍のために戸外出ての社会見学などに取り組むことができなかった。そこで「来年度はぜひ実施したい!」という声があった。検討したところ工場見学などはまだ先方が受け入れてくれないところが多いため、「ウォーキングを兼ねて、札幌市内の公園の魅力を再発見しよう!」ということになった。
訪れる公園として候補に挙がったのが、大通公園、中島公園、円山公園(+円山動物園)、西岡公園(西岡水源池)、百合が原公園、モエレ沼公園、などであった。そこで私は自らの健康づくりも兼ねて、自主的に事前踏査をしてみようと思い立ったのだ。
その第一弾として過日(12月2日)、まずは大通公園を巡って歩いたということである。
大通公園の彫刻たちは皆雪を被っていたが、そのような写真を撮る人はそう多くはないはずだ。とすればそれも一興と思い、雪を被った彫刻の写真を公開することにした。コメントも付けずに羅列します。(大通公園の西1丁目から札幌市資料館に向かって順に羅列していきます)
◆北1条西1丁目
【山内壮夫 作 「希望」の像】
※ 正確には大通公園内に建てられた像ではないが、大通公園に隣接していることから仲間に入れることにした。

◆大通公園西2丁目
【山内壮夫 作 花の母子像「愛」】

【「ベンソンの水飲み」碑】

【「北海道電話交換創始の地」碑】

【佐藤忠良 作 「開拓の母の像」】

◆大通公園西3丁目
【坂胆道 作 「石川啄木像」と歌碑】

【峯孝 作 「牧童」の像】

【本郷新 作 「泉の像」】

【山田良定 作 「湖風」】

◆大通公園西4丁目
【小谷博貞 作 「札幌の木 ライラック(吉井勇歌碑)」】

◆大通公園西5丁目
【聖恩碑】

◆大通公園西6丁目
【開拓紀念碑】

【峯孝 作 「奉仕の道」】

◆大通公園西7丁目
【田畑一作 作 「漁民の像」】

新たな発見もあった。その一つは、大通西7丁目の片隅に目立たない形で「集団帰国記念」と書かれた小さな石碑があったのだ。調べてみると、戦時中に不足していた労働力を補うために多くの朝鮮人が日本に送り込まれたことは史実でも明らかだが、本道にもたくさんの朝鮮人が送り込まれていた。戦後、日本赤十字社と朝鮮赤十字会との協定によって朝鮮人の帰国事業が始まり、北海道からも約2,000人の朝鮮人が帰国したそうだ。そのことを記念した石碑であるが、私はこの石碑のことをこの日まで知らなかった。あまりにも小さな石碑のために札幌に住む人でも知らない人が多いのではないか?私たちは史実としてそのことを知る必要があるのではないか、と思うのだが…。
【「集団帰国記念」碑】

◆大通公園西8~9丁目
【イサム・ノグチ 作 「ブラック・スライド・マントラ」】

◆大通公園西9丁目
【藤川基、山本一也 作 「有島武郎文学碑」】

◆大通公園西10丁目
【野々村一男 作 「ホーレス・ケプロン像」】

【雨宮次郎 作 「黒田清隆像」】

◆大通公園西11丁目
【マイバウム】

【オリンピックマーク】

◆大通公園西12丁目
【佐藤忠良 作 「若い女の像」】

もう一つ、札幌市資料館の正面玄関外壁に「法の女神」テミスが目隠しをしている頭部像が掲げられているのは知っていた。そしてその横には剣と秤の彫刻も掲げられている。それらが一体となった女神像があると聞いたのだが、資料館に行っても見つけることができなかった。そこで担当者に伺ったところ、なんと資料館の玄関を入ったところの左手に高さ40cm程度の小さな女神像がガラスケースに入って陳列されていた。私は大通公園にある他の彫刻と同じような大きさと勝手に想像していたために見つけるができなかったのだった。
◆大通公園西13丁目(札幌市資料館内)
【山本新蔵 作 法の女神「テミス」の像】

また彫刻やモニュメントではないが、西11丁目の中央付近にある大きな建造物が気になっていたが、これは「地下鉄通風口」だということが判明した。

大通公園は札幌における最も重要なランドマークである。だからさまざまな意味で記念する彫刻やモニュメントが多いのも頷ける。これらを改めて見て回り、その意味を知ることには大きな意味があると思っている。来年度の本番が楽しみである。
なお、事前踏査で大通公園を往復した歩数は約3,800歩、距離にして約2.4キロだった。お年寄りのウォーキングとしてはけっして無理な距離ではないと思っている。
《WCサッカーカタール大会 情報》
今夜、というより今深夜(12時より)森保ジャパンはベスト8進出をかけてクロアチアと対戦する。メディアは大騒ぎをして日本有利を伝えるが、私はそんなに簡単じゃないと考えている。いや、むしろかなり難しいのでは?とさえ思っている。何といってもクロアチアは前回大会の準優勝国である。だから森保ジャパンが不幸にも負けたとしても、私は潔くその敗戦を受け入れようと思っている。今大会の森保ジャパンはドイツ、スペインといったサッカー強国から勝利しただけで十分な仕事をしたと思っている。
だから今夜は今までより冷静に観戦したいと思っている。そしてもし幸運にも勝利できたとしたら直に喜びたいと思っている。
願わくば、今大会に入って期待されたほど輝いていない鎌田、伊東両選手が輝いて悔いなく今大会を終えてほしいと思っている。何せ二人は森保ジャパンをWCに導いた立役者なのだから…。頑張ろう!ニッポン!