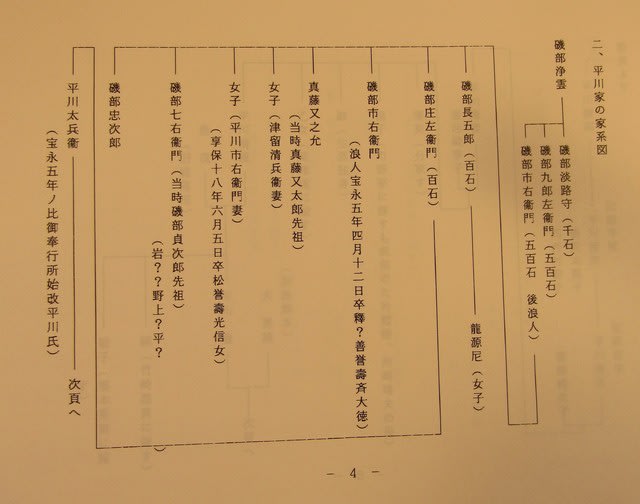(元和十年四月)廿八日
|
|一、廿八日 甚左衛門〇 道倫 当番 晴天
|
| (左)
左官天守ノ辰口壁 |一、川田八右衛門・御佐官内田平蔵登城候而、御天守ノ辰口ぬり申ニ付而、玉子しまい仕候、玉子御
塗用ニ玉子ヲ求ム | 郡へ被仰付可被下由ノ事
鷹師江戸ヘノ使ニ |一、御鷹師冨田彦右衛門登城候而、江戸へ御使ニ可遣由、被仰付候へ共、眼気相煩申候条、養生仕度
眼病故養生ヲ乞ウ | 存候、其御心得被成可被下由、申候へバ、両人之御奉行衆飯後被上候哉、談合可申由、横山進助
| 被申候事
| (吉弘統幸)
豊後ノ陣ノ戦死者 |一、宇野七右衛門登城ニ而被申候、 殿様御れう分ニ、吉ひろ加兵衛、ふん後ぢんノ時打じに仕候、
ノ弔所建立ヲ願ウ | 其御とぶらい所を、子共とも立申度由申候か、いかゝ御座候哉、御奉行衆へうかゞい被申候、く
| るしかるま敷由ニ候事
|
| (河井) (富田) 被 申候
江戸ヘノ使ノ鷹師 |一、御鷹師権丞へ被申渡候、彦右衛門眼気煩申候ニ付、よ人へ差替候様ニと左候へゝ、せいし被仕候
ヲ差替ウ 病気故 | 〃〃〃〃
ノ誓紙ヲ書カシム | やうニと被申渡候事、心得申候由ニ候、大野弥兵衛と申御鷹師被参候事
子供ノ礫打ノ禁制 |一、佐分利作左衛門登城ニ而、主前ニ而、子供ともつぶてうち仕候間、高札御立候て可被下候由、被
願 | 申候事
台所人眼気ニツキ |一、御台所新蔵眼気相煩申候ニ付、御上洛前ニ、深野左介を以替え、御いとま申上候、然は、女子召
暇願 | 連、在所へ罷帰候間、御川口御切手被下候様ニと申候、其時、御奉行衆へ左介何共不被申候間、
| (有之) 存たる由、
| 如何候哉、せうこ人■■は、可遣由、被申候、則、吉田喜雲、書を可仕候ニ付、さし帋被遣候事
|
(元和十年四月)廿九日
|
|一、廿句日 道倫 助二郎 当番
| 帳
下毛郡麦帳 |一、下毛郡御奉行衆ゟ麦参候事
| (田代等甫) (風脱)
絵師等甫ニ金屏風 |一、中津ノ等浦ニ、金屏弐双被 仰付候、御奉行を遣可然、不入儀かと、矢野少右衛門ニ被相尋候、
二双ヲ命ズ | (箔)
制作奉行ノ要 | 小右衛門申候ハ、御奉行不仰付候ハヽ、薄之積り・日手間ノつもりしれ申間敷候条、御奉行被仰
箔日手間ノ積リ | (沢村吉重)
| 付可然之由申候事、又、沢大学殿ゟへ、只今以使、被尋候ヘハ、等甫かたへ飛脚を被遣、御たつ
| 〃
三斎召船ノ船幕 | ね可然候よし候、御奉行衆被申候ハ、中津御舟まくの儀を、御船頭衆ゟ■中津御船頭衆へたつね
| ニ遣候ヘハ、其まゝ 三斎様立 御耳候間、等甫儀も、中津御奉行衆ニへ可申入との返事不申候
| 事 〃
| (奈良鍛冶)
奈良鍛冶口入銀 |一、林太郎左衛門登城ニ而、ならかち左兵衛ニ口入銀仕候、然は、銀切手出次第ニ、切手ニ而取立候
切手ニテノ取立ハ | へとの約束仕置候、然は共、切手ニ而ヲさへ申儀、御法度之由承及候、如何可被仰付哉と、相尋
法度 | 〃
奉行所関与セザル | 候へバ、借銀之儀、御奉行所ニ而取沙汰無之儀ニ候条、あいたい次第たるへき由、被仰申渡候事
故ニ相対タルベシ | 〃
石垣ニ石ヲ支ウ |一、勘平・與介登城候而、所々石垣かい石不死候は、崩可申所御座候条、かい石可申付由、うかゞい
| 候ヘハ、仕候而可然由、被申渡候事
金山へ秤天秤針口 |一、金山へはかり五ケ、天秤之針口被遣候事
幕府蔵入由布院横 |一、由布院・横灘ノ目録仕立ニ、御惣庄や・御郡代宇野七右衛門登城仕候事
灘ノ目録仕立ニ惣 |
庄屋郡奉行等登城 |